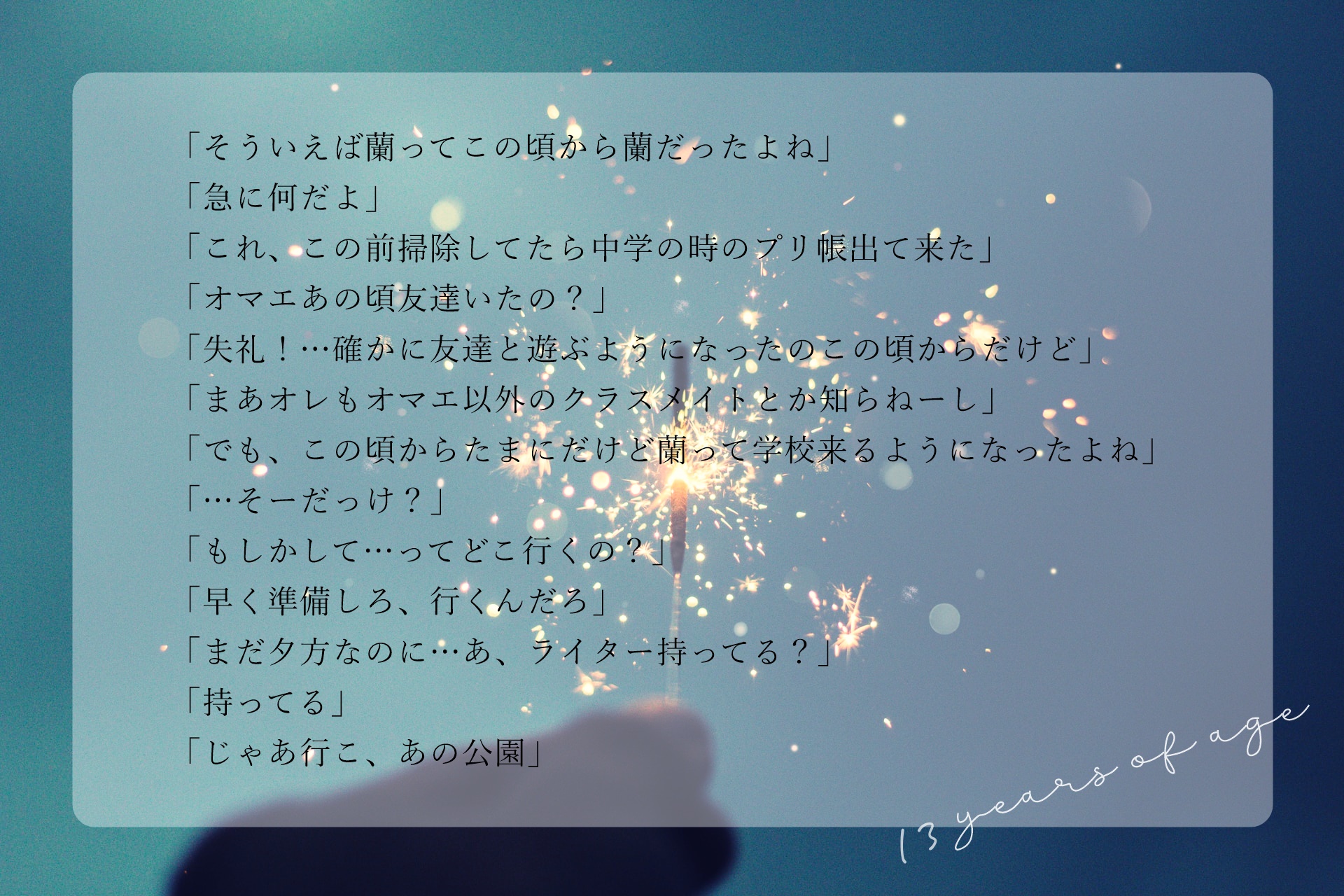満天の星なんてまぼろしかと思うほど夜は虚しくて、人工的な光ばかりが主張する東京の夜は明るいのにどこか暗い。塾の帰りにいつも通り家へ帰ろうとしたら、下水道の夜間工事とかで歩道まで塞がれてしまったのでいつもと違う道を通ることにした。頭の中の地図では何となくどの道とどの道が繋がっているのか理解しているけど、知らない道をこんな時間に通るのは迷子になったようなスリルを感じる。朝昼は平和に包まれている和やかな公園も、夜になれば不気味さを醸し出してくるような二面性があるから、潜在的に生まれていたであろう恐怖心から、無意識のうちに早歩きになっていた。そんなわたしの視界の端に、見覚えがあるような無いようなどこか曖昧な記憶を呼び起こすひとりの人物が映り込む。木製ベンチの上で、頼りない外灯よりもまばゆくて、月よりも見惚れてしまうほどの髪色が、黒と紺で塗りつぶしたみたいな背景に映えるように存在している。
「あれ、灰谷くん?」
「…誰だオマエ」
まるでそこだけが別世界のように思わされたのは、この宵闇の中でも堂々と存在出来ることに憧憬したからかもしれない。わたしより長いと思われる髪の毛はいつから伸ばしているのだろう。まだ染めたことの無いわたしの黒髪と対照的なその色は、明るい太陽の下よりも静かに澄んだ今日みたいな夜に調和する気がした。
「あー…知らないと思うけど同じクラスの」
「ふーん、知らねー」
「灰谷くん学校来ないもんね…って、ケガしてるの?」
「あ?オマエに関係ねーだろ」
彼、灰谷蘭くんは学校内でも有名な不良だった。学校に来たのも1~2回しか見たことが無いような気がする。髪型だけでなくこの目立つ容貌に、近寄りがたくて怖いと言いながらもどこか惹かれている女子は多いらしい。部活にも入らず、まだ3年生でもないのにすでに高校受験を意識して毎日勉強ばかりしている平凡なわたしとは、生きている世界が違う人間くらいにしか認識していなかった。だって、灰谷くんにとっては日常の一部であろうこの夜の公園も、わたしにとっては心拍数が自然と上がってしまうほど非日常の空間だから。そんな中で知った顔が見えて少し安堵したのか、わたしは気づいたら灰谷くんの隣に座っていた。
「灰谷くんって本当に不良だったんだね」
「本当にって何だよ」
「はい、これでちゃんと血拭いて」
「要らねー」
「わたしが見てて痛々しいからダメ」
「じゃあ見んなよ」
整ったその顔立ちに似合わない傷は、改めて彼が別世界の人間だと物語っているようだった。出ていた血に怯えるどころか、半ば強引に持っていたハンカチを押し当てたのは、知らない世界へ旅をしている感覚になっているからかもしれない。普段の、昼の優等生なわたしだったら絶対話し掛けることなんてせず、知らないフリをして見えている景色と同化させて無関心に通り過ぎたと思う。
傷や怪我自体は大したこと無さそうだったので安心した。平然としている様子からもきっと、わたしが転んで怪我したのと同程度の感覚なのだろう。白い肌に鮮明に浮かぶ内出血が痛々しそうなのにどこか惹かれてしまったのは「美しさ」と「傷」と言う正反対が織り成す作品のように思えてしまったからかもしれない。
「家帰ったらちゃんと消毒して冷やしてね」
「…つーか見た感じオマエ優等生だろ?こんな時間にこんなとこ歩いてんじゃねーよ」
「今日は塾の帰り道が工事で迂回になってただけ。いつもなら通らないよ」
「あっそ」
「じゃあわたしそろそろ帰るね。灰谷くんも早く帰りなよ」
すっかりこわくなくなった公園を、普通の歩幅と速度で通り抜ける。特に返事は無かったけど、そんなこと全く気にならない。いつもより少し遠回りしただけで味わえた非日常みたいな時間に陶然としているような気さえする。今までと違う自分になれたような気がしてスキップ出来そうなほど足が軽く感じた。けど、いつもの見慣れている道に出ると安心する筈が不思議と足枷が急についたみたいに身体が重くなる。不自由なく育ってきたコンクリートの固まりみたいな家の中に入ると、息が詰まるように感じてしまって、どんなに暗くても壁なんて無い夜の公園の方がずっと居心地が良いと思ってしまった。
△▼△
気付いたら制服は長袖から半袖になっていて、夜は短くなっていた。けど、昼や夕方の明るい時間が長くなったと同時に夜が窮屈な思いをしているという感じはせず、むしろまだまだこれからが夜なんだと思えるようになったのは、少し前の一夜のおかげかもしれない。塾の帰り道の工事は一週間ほど続き、その間は毎夜公園を突き抜けて帰っていたけど灰谷くんに会うことはあの日以来なかった。それでも、たった一度灰谷くんと夜の公園でおしゃべりしたという事実が過去に存在するだけで、夜の遅い時間にこの道を通るのが少しだけこわくなくなった。学校のHRでもこの近辺で起きている事件や乱闘について注意喚起されたり、夜遅い時間には極力出歩かないようにと言われていたから、何にも巻き込まれなかったのは運が良かっただけなのかもしれないけど、あの日の一瞬が少しだけわたしを強くしてくれたような気さえした。
―もちろんそれは勘違いで、結局わたしは何も変われてなんていなかった。模試の結果が今日返ってきた。自信がそれなりにあったせいか、予想外の不出来にダメージが大きすぎて周りの子たちの声が自分の中から消失する。ぐしゃりと皺を寄せたこの結果が書かれた紙を、最初から存在しなかったみたいにビリビリに破きたかったけど、その潔ささえも無い。家に帰るのが憂鬱過ぎて、ひさびさにあの公園に行ってみた。相変わらず静かで、以前はこわいと思っていたこの場所も、むしろ落ち着くような空間になっていた。ブランコに腰掛けるとギィという鉄の軋む音がやたらと響くように感じる。まばたきをすることも忘れてただ伸ばした自分の足元を見つめていると、急に影が落ちてきた。いきなり変化が生じた視界に驚いて顔を上げると、そこには月に代わるかのように灰谷くんが立っていた。
「こんな時間にこんなとこいるなんて不良じゃん」
「…不良に言われたくない」
「この辺治安わりーの知ってんだろ、早く家帰れよ」
当然のように学校にも来ないから、会うのはあの夜以来だった。けど、なんとなく今日は正面から灰谷くんの顔を見ることが出来ない。微かに存在していた自信が喪失されてしまった今、わたしが欲しいと思っているものを持っている彼を見てしまったら、その何もかもを見透かすような深みのある紫の双眸に焦がされて、つまらない自分を炙り出されるような気がしたからだ。灰谷くんからしたら、元々わたしなんてつまらない普通の優等生にしか見えてなかったかもしれないけど、そんな自分を認められるほどわたしのこころはまだ出来上がっていない。
「帰りたくない」
「日付変わるくらいに多分ここで抗争起きっから巻き込まれんぞ」
「抗争…?」
「面倒くせーけど送ってってやるから、ほらさっさと立てよ」
多少心配してくれているのだろうか。それとも邪魔に思われているのかもしれない。「抗争」と言う聞きなれないワードに改めてこの辺の治安の悪さを実感してしまったけど、危機を感じるとの同じくらい今日は家に帰りたくなかった。家に帰ったって結局成績の悪さを親から咎められる。灰谷くんが言う「抗争」に巻き込まれたら身体に痛みが生じるのかもしれないけど、家に帰ったってこころがきっと軋むように傷つく。期待に応えられない自分が悪いのだと分かっているから、すでに生まれている傷をきっと更にえぐられる。周囲からしたら「模試の結果ごときで」と思われるかもしれないけど、せまい世界で生きているわたしにとっては、これが全てなのだ。
「…花火したい」
「は?」
「灰谷くん不良でしょ?ライターくらい持ってるよね」
「なんだその短絡的思考」
「明日花火買って持ってくるからここで待ち合わせしよ」
「ダリいからヤダ」
「約束してくれたら今日はもう帰る!」
自分でもどうしてそんなことを言ったのか分からない。ただ、星も外灯も大して輝かない夜に自分で明かりを灯すことが、何かのきっかけになるかもしれないと思ったんだと思う。うつくしい顔面を心底面倒くさいと言うように歪ませた灰谷くんだけど、最後は折れてくれたので実はやさしいのかもしれない。楽しみが出来たわたしは帰り際に時間も気にせず大きな声で「約束だからねー!」と静寂に包まれた公園内に声を響かせた。灰谷くんはしっしと手で払うようにしていたけど、このちいさな約束がまたあの日の夜みたいに少しだけわたしのこころを元気づけてくれた。鉛のように重くて、氷のように冷たく感じる玄関の扉の向こうに待っているのは、恐らく帰りが遅いことを心配しているのではなく世間体を気にして腹を立てているであろう親。そして模試の結果を伝えればその怒りは加熱されるに違いない。きっと「夜遊びなんてしているからだろ」と言われる。そんな脚本を脳内に描いたけど、今日みたいな惨めな心情ではなく堂々と明日の夜を迎えたいから、その先の展開はその時の自分の本音に任せることにした。
△▼△
翌日、生まれて初めて塾をサボった。勉強をしていないとこんなに時間を持て余すものなのかと衝撃的に感じた。わたしが機械のように無心で勉強していた時間を、人はみなどのように使っているのだろう。
時間は特に決めていなかったけど、なんとなく塾が終わるくらいの時間に公園にやってきて、相変わらず寂れたブランコに腰掛けた。もしかしたら来ないかもしれない、と思う反面でまだ大して彼のことを知らないのに何となく約束を破るような人間ではないと勝手に思っている。普段なら煩わしいと思う虫が鳴く音をバックミュージックにしながら、月が出ていない夜空を見上げる。曇りでも月が見えづらくなるくらいで、この街の夜は何も変わらない。
「」
「うわ…びっくりした。っていうか名前覚えててくれたんだ」
「この前オマエが押し付けたハンカチに刺繍…」
ヴェールに包まれたような紺色の空を見上げていると、夜に溶け込むような声色で急に名前を呼ばれたので驚いた。名前を覚えてくれていたのも意外だったけど、友達が少ないわたしを名前で呼ぶ人間なんて家族以外いないから、何だか少し戸惑ってしまう。喫驚していると、灰谷くんも同じように驚いている表情をこちらに向けていた。まるで鏡かと見紛うような表情だ。見紛うと言ってもわたしの凡人みたいな顔とじゃ造形が全然違うけど、何事にも動じないと思っていた彼でも驚くことがあるのだと印象的だった。
「…どーしたソレ」
「ソレって?」
「その顔に決まってんだろ」
「…わたしも喧嘩してきました」
1日経てば治まると思っていた頬の痛みは、残念ながら完全には引かなかった。昨夜、自分が描いたシナリオ通りに物語が進み、良い子ちゃんを演じてきたわたしは生まれて初めてと言っても過言では無いくらい自分の心情をノンストップで親に吐き出した。勉強が嫌いなわけでは無いけれど、見えないプレッシャーと言うものに早くも押し潰されそうになって、家でも学校でも塾でも窒息しそうなほど息が詰まる。いっしょに食事をしても、会話はほぼ皆無。たまに交わされる会話はぜんぶ勉強や受験のことばかり。下らなくて良いから日常的な会話をして、他の家族みたいに談笑したりしたい。家の中で笑った記憶なんて、最初から存在してなかったみたいに消えていた。友人とだって、もっと楽しく過ごしたい。友達が少ないのを勉強のせいにするわけではないけど、例えば放課後に寄り道をして時間を忘れるくらい夢中で暗くなるまでおしゃべりをする、なんて言うほとんどの中学生にとって当たり前のひとときを過ごしたい。そんなこころの奥底に閉じ込めていた願望の数々を、勇気を出して吐露した。ここで「そうだよね」と理解してくれる親ならば、きっと最初からそうしていたと思う。激高した親は「誰のためにお金を払って塾に行かせていると思っているんだ」とか何だとか、わたしにぶつけられたのはそんなありきたりなセリフと平手打ちだった。
「…へえ、どーだった」
「後悔は無いかな…勝ったわけじゃないけど喧嘩も悪くないかもね」
パンパンに腫れた不細工な顔で笑って言うと、灰谷くんもつられるように「そーだろ?」と言って笑ってくれたので、何だか少し救われた気分になった。それから一夜経った今、親との距離は何も変わっていない。けど、言いたいことをようやく言えたという爽快感みたいなものが自分の中には存在していて、客観的な状況は何も変わっていないどころか悪化しているのかもしれないけど、何ひとつ後悔は無かった。
わたしは多分、灰谷くんに羨望のようなものを抱いているんだと思う。同級生なのに何にも怯えることなく好きなように生きている彼が羨ましい。
「そんなことより花火しよ。灰谷くん火つけて」
コンビニで買った花火をバケツに入れていたので、そこから2本取り出して1本を灰谷くんにも渡す。持ってきてくれたライターで2本の花火に火をつけてくれると、真っ直ぐ前方に細長い火花が放たれる。火花の勢いや色がコロコロ変わるので変化がある度にわたしは無邪気にはしゃいでいた。適当に買った花火セットには数種類の手持ち花火が入っており、パチパチと華やかに弾けるものや地面に置いて噴水のように火花が吹き出すものなど、色々入っていた。最初は無理矢理付き合わされている感を出していた灰谷くんも、不良らしく危ない持ち方をしてこちらを揶揄うように脅してきたりしたけど、大人っぽく見えていた灰谷くんがようやく同級生に思えるような笑顔をしていて、何故かは分からないけど嬉々とした感情がわたしの中に生まれていた。
「夜に抜け出して花火なんて、わたしも悪くなったみたいでドキドキする」
「オマエ花火やる友達とかいなそーだもんな」
「いるよ?今となりに」
灰谷くんは呆れながらも「オレかよ」と笑って散った花火を水が入ったバケツに入れた。残りは線香花火だけ。どうして線香花火は最後にしてしまうのだろう。あんなに華やかな花火たちと比べると、こんなに静かで光もちいさいのに、どうしてか惹かれてしまう。かわいらしいオレンジ色の火の玉がふたつ並んで、パチパチと落ち着きさえ感じる音が始まりと終わりのふたつを感じさせる。
「花火ってちょっとさみしいよね」
「あ?」
火花がついてる時の明るさと、終わると一気に暗くなる時のコントラストを顕著に感じてしまうからだろうか。まさにうつくしい花が散っていくような儚さと憂いさが胸を貫くような気がする。わたしの始まったばかりの夏は、きっと今日で終わる。
「思い出作りに付き合ってくれてありがとう」
「…転校でもすんの?」
「しないけど、多分ここにはもう来ない」
いつの間にか逃げ場みたいにしてしまっていたこの公園は居心地が良いけど、きっとわたしの時間はここで止まって動き出さなくなってしまう。このまま親に反抗しているだけでは、きっとわたしが過ごしたい日常なんて訪れない。それならばいっその事、誰にも文句を言わせないくらいめちゃくちゃ勉強して、好きなことをしていく方が、わたしはずっと良い。そんな風に前向きに思えたのは、1回逃げ出して、離れて、そのおかげで知ることが出来た今みたいなひとときを、誰にも邪魔されずまた過ごしたいと思えたおかげ。これらの瞬間が集まって形成された「今」が或るおかげだ。
「灰谷くんたち不良風に言うと、戦おうかなって思って」
「ナンダソレ」
「勉強、頑張るって決めたの」
「やっぱ優等生だな」
細いけど、たくさんの線と輝きが交わるように火花が飛び散る。
「でもまあ悪くねーんじゃん」
パチパチと鳴る音と重なるように紡がれた灰谷くんの言葉と、星の代わりに灯るこのちいさな花火が、わたしの夜を明るくさせる。
「…大人になったらいつか今日のことも忘れちゃうのかな」
花火の音がちいさくなっていき、火花もゆっくりとやわらかくなっていく。この夏の終わりを予感させる光景に、寂寞とした感情がじんわりとこころを飲み込んでいく。やがて光は儚く消えていき「あ、わたしの落ちる」と言ったのと同時に地面に火の玉が落ちた。その後、数秒も立たずに灰谷くんの花火も光を失う。やっぱり花火が終わる寂寥感に抗うことは出来なそうだ。後始末をしようと立ち上がろうとした瞬間、力強く腕を掴まれバランスを崩しそうになった。その瞬間、冷たいようなあたたかいようなものが、くちびるに触れる。暗くてよく分からないからではなく、全く予想しない出来事に思考も呼吸さえも止まりそうになった。
「これで忘れねーだろ?」
長く輝き続ける線香花火は、たいせつな誰かと時間を共有するために作られたものなのかもしれない。
消えた花火の代わりに、見えない月の代わりに、目の前に存在する人物が、きっとわたしの光になる。