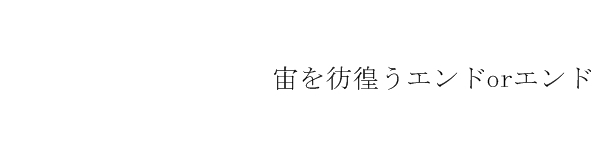濃紺の夜空に輝く派手なネオンに照らされた道を歩いて辿り着いた楽園は果たして眩しい世界なのだろうか。無駄に豪華に飾られたエントランスの花に見守られながら、エレベーターに乗り込む。扉を開けて入った部屋は、大理石のフェイクが散りばめられてはいるが上品さを醸し出している。セックスをするためだけのホテルに品性を求めているわけではないが、やはりキレイな方が良い。
「本当に良いのか?」
「良いけど…」
「煮え切らないな。恋人に対して罪悪感があるならやめるが」
「罪悪感はないけど…赤司くんこそ良いの?」
「そうじゃなければ連れて来ないよ」
PM19時の新宿繁華街。かつての部活の仲間数人が久々に集った。言い出しっぺが誰かすら覚えていない上に意外にも参加率が良いのは驚きを隠せなかった。外見も中身もそこまで変わった人間はいないようだが、注文するお酒の種類でしばらく会っていなかった彼らがどんな人生を送って来たのか、ほんの1ミリくらいではあるが分かるような気がする。
良く言えば自由、悪く言えば勝手な彼らはそれぞれ浴びるようにお酒を飲んだり盛り上がったり、帰ってしまったり。他が騒いでいる間に私は端で黄瀬くんと赤司くんと飲んでいた。こんな組み合わせ、昔だったら絶対にあり得ない。だからこそ久々の再会に面白さも感じるのだが。昔話に花を咲かせるのかと思いきや、何故か話題は各々恋愛の話になった。この面子でこんな話も今となっては出来るのだから時間の流れはおどろきである。黄瀬くんも赤司くんも今はパートナーがいないからか、話の中心は自然と私と私の恋人の話題になった。
「へー、どのくらいヤってんスか?」
飲んでいたカシオレを吐き出しそうになったところ、傍にいた赤司くんがハンカチを差し出してくれた。紳士が持つようなチェック柄のハンカチは、上品な香りさえ感じさせる。酒が入っているからか普段ならアウトゾーンとされる話題にも、別に隠すこともないので淡々と「別に」とだけ答える。更にはアルコールのせいで不意に漏れてしまった「でも、あんま気持ちよくないしイケたことないし、ぶっちゃけしなくても良いかな」という私の言葉に黄瀬くんは面白そうに「ええ!?マジ!?」とだけ言う。絶対楽しんでるな。けれど黄瀬くんはその後、別の席で盛り上がっていた青峰くんに拉致られそれっきり。
「さて…キス、は良いのかな?」
「赤司くんにしては愚問だね」
「…」
「これからキス以上のことするんだから、いちいち聞かなくて良いよ」
「早くイカして欲しいと?」
「そこまでは言ってない、けど」
ふたりになった瞬間、赤司くんがいきなり漏らした言葉。何もかも見透かすような双眸、筋の通った鼻筋、そして人の心を操る言葉が出て来るくちびる。そのくちびるから紡がれた意外な一言。「だったら僕がイカせてあげるよ」まさかあの赤司くんがそんなことを言うなんて。中学生時代の彼からは想像がつかなかった。しかし、冗談を言うようにも見えないし、言ってるようにも見えない。もしかして今は恋人もいないらしいし、あの赤司くんでも溜まってんのかな?くらいにしか思わず、またあの赤司くんがどんなセックスをするのかという好奇心、そしてイカせてくれるという、負の要素がない提案に、恋人がいるというのに乗ってしまった私はこの店のお酒より安い女だろう。
白いベッドに身体が眠るようにゆっくりと沈む。押し倒されながらされたキスだけで既に心地が良い。やわらかいくちづけも、貪るようなくちづけも、私の下唇をやんわりと吸うくちびるも、上唇をゆっくりと舐め上げ歯列を撫でる舌も、舌と舌の感触さえ、まるで銀河を彷徨っているように感じてしまう。ゆっくりと胸の膨らみをひと撫でされ、その感覚に浸っているとあっという間に服をすべて脱がされていた。
「こんなにキレイな身体をしているのにイケないなんて」
「…でも、今日イカしてくれるんでしょ?」
彼はくちびるの端をあげるとそのまま私の耳や首筋を這う。耳にも脳にも心臓にもダイレクトに注がれる水音に思わず声が漏れると「可愛い」と言葉のサービスまでしてくれた。その言葉に柄にもなく照れていると彼の手は胸を這い始めた。彼の手は不思議である。ただ肌の上を滑っているだけなのに、渾沌するほど気持ちが良い。自分でも分かるほどにびしゃびしゃになったショーツを早く脱がして。
「の恋人が少し羨ましいよ」
「…どうして?」
「をいつでも抱けるんだから」
世間一般からしたらおそらく愛を育むであろう行為をしているが、私たちの間に愛はひとかけらもない。長い間、友人関係でいたからきっとお互いそんな風には見れないだろう。けど、セックスは出来た。不道徳だけれども。
剥がされたブラジャーが床に落ちる音が与えられている快楽の中で微かに聞こえた。彼の手だけではなく指でもくちびるでも舌でも、身体にすりこませるように憶えされる快感に、つい太腿を不意に擦り合わせてしまう。その姿をあざとくも見逃さなかった彼は、またもや口角を上げると、ようやく彼の指が海となりかけそうなショーツの中へ侵入して来た。
「…信じられないな」
「何が?」
「こんなに感度が良いのにイケないなんて」
「そんな…ぁっ…っ」
まだ話している最中だというのに彼の指がやさしく陰核に触れると、抑えようとしていた声が漏れる。それを満足げに見下ろす彼の表情が妖艶だなんて思ってしまうのは重症だろうか。ショーツを脱がされると、ようやく彼も服を脱ぎ始めた。あの頃よりきっと遥かに引き締まったその身体だけで、私の下半身を疼かせるのだから全く反則めいている。一本、二本と膣の中に入ってくる指は、これからどんな旅を楽しむのだろう。自分ではハッキリとした輪郭は分からない。けれど間違いなく中で蠢いている彼の指に、つい眉間に皺をよせてしまう。
「ひゃ…!ぁっ、ちょっ…」
「良いね、その顔。普段は絶対見れない顔だ」
「あっ…ゃっ…は、やっ…!」
指だけではなく、腕全体の筋肉を働かせて往復するその動きは速いというより、的確と言ったほうが良いだろうか。今までに味わったことのない感覚が下半身から脳に浸透するように響いてくる。細かい皺を描き、いずれ破けてしまうのではないだろうかというくらいの強さでシーツ握る。このままこの快楽に陶酔していたらどうなるのだろう。私が私じゃなくなってしまうようなそんな感覚。「まっ…まっ…て…!」ようやく絞り出した声と、筋肉が引き締まった彼の腕を何とか出せる力で掴むと、彼の動きが一度静止した。彼の下でただ気持ち良くなっているだけだと言うのにこの息切れと疲労感。
「何だ?」
「こ、こわいの」
「こわい?」
「…自分が変になりそうで」
「それは良かった」
「え?」
「狂って良いんだよ」
−問題ない、その先はが望む答えだ。そう告げた彼は私の言葉も聞かず、またもや指を動かせた。中に入った人差し指と中指が、一体いつ見つけたのか分からないピンポイントを刺激し、彼の片手はたまに陰核や胸の先端を撫でる。しかし、撫でてくるのは指だけではない。彼の赤い舌が小刻みに勢いよくあらゆる先端を刺激する。そして先程の反応だけで私が耳が弱いということを見抜いたのだろうか、這うような舌が耳元にまで再びやってくると本当に何も考えられなくなる。声を出すのは好きじゃない。それなのに厭らしく漏れる自分の声。けれど、そんな音さえも聞こえなくなる。
「ぁんっ…ぁ、あっ、…ぁぁぁぁぁっ…!」
短く切るような自分の下品でふしだらな声がだんだんと絞られ身体が少しだけ反る。そして彼の動きが止むと一気に襲ってくる脱力感。「よく頑張ったね」と汗ばむ私に優しくキスを落とす彼に畏怖すら抱けず、ただ余韻に浸る。あんなにキレイだったシーツはぐちゃぐちゃ。皺がよってしまったシーツはまるでもう今夜は元通りに戻らないことを暗示しているかのよう。
「…お礼にフェラでもしようか?」
「それも良いが…」
「わっ、いきなり足持ち上げないでよ」
「今更嫌なんて言わせないよ」
「…言わないよ。でも、その代わり、」
彼の硬くなった陰茎が私の陰核を撫で回す。そんな穢らわしい所作にさえ美しさを感じた私の下半身は乾くことを止めない。しばらく撫でられているとゆっくりと入り口にフィットしてきた。ゆっくり、ゆっくり。壁を通り中に入ってこようとしているのを全身で感じる。
「…っ、またイカせてくれるんだよね?」
「言うね」
その言葉が合図かのように一気に突き刺さってきた彼の陰茎に、私の膣内が驚いたのか、その感情がくちびるから声となって漏れた。その漏れてしまった音はもちろん、吐息さえ彼は鮮やかに奪っていく。ベッドがギシギシと軋む音、肌と肌が激しく衝突する音、お互いから漏れるすべての音。あらゆる卑猥な音が重なる淫乱が見事な調和を奏でているだなんて言ったら忘我にも程があるだろうか。彼から漏れる吐息は私が奪ってあげる。彼の顔を引き寄せれば自然と重なり合うくちびるは、快感しか知らない。緩急をつけるその腰使いに酔いしれていると、侵略するかのように動く彼の存在が佳境を迎える。「くっ…」と彼から漏れた音を合図にまさか彼の快感に耐える表情が見れるなんて。彼の耽溺するような声をBGMに出来るなんて。先程経験したばかりの絶頂に、些か恐怖心はまだあるものの、彼も一緒だと思うと先程よりの快楽と絶頂を感じることが出来た。
「が望むならいつでも僕がイカせてあげるよ」
「それじゃあセフレじゃん」
彼は丁寧にも後戯までサービスしてくれた。一夜の夢物語とは言え、充分過ぎるほどの世界を体験させてくれた彼の腕枕でぐったりしていると優しく髪を撫でられる。彼は今宵の短い時間で私のすべてを把握してしまったようだ。その事に恐怖を感じたのはきっと、これ以上のセックスをしてくれるのは彼だけかもしれないと思ってしまったからだ。
「そういう関係はあまり好きではないな」
「だから今夜だけってことで」
セフレを作るつもりは私にもない。それが例え私を初めて絶頂させてくれた彼だとしても。そう頭の中では決めているはずなのに、正直な下半身は彼を離そうとしたがらない。彼の脚に絡みつく私の脚に触れる彼の手に、火傷させられてしまったようだ。
「そうだな。まぁ今の男と別れて僕のところに来たくなったらいつでもおいで」
「いかないってば」
「その割にのココは僕を求めているようだが?」
「ぁっ…」
ただ、今宵だけ。眩しくて現実が見えないということにさせて下さい。