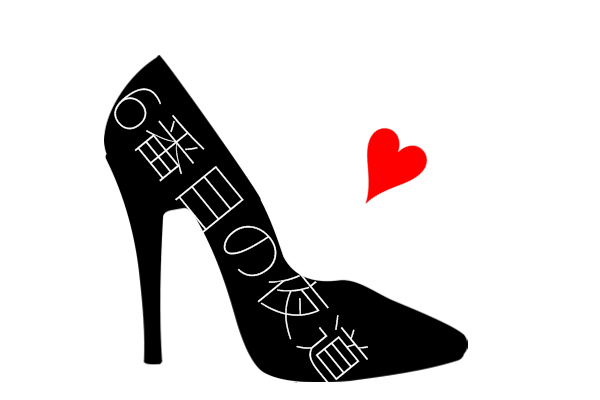けど、金曜日の夜だけは仕事後のメイク直しを欠かさない。オフィスのレストルームでファンデーションのパフを肌に滑らせ、チークで疲れきった顔の血色をよく見せる。マスカラを数回重ねて、ひたすら睫毛が上を向くようにビューラーで持ち上げれば、顔が見違える程度には生き返る。ルージュを軽く塗りなおして、あとは金曜日にしか履かないお気に入りのパンプスで会社を出れば、もうスキップをしたいくらい足が軽やか。電車に乗ってる間も窓ガラスに反射した自分の顔がにやけていて気持ち悪い。いちばん心が高揚するのは、駅に着いて、ICカードを改札にピッとかざす瞬間。ゲートが開いて、そこから彼の姿を探す時間も好きなのに、彼がわたしを見つけてくれることの方が早くて、なんだか少し不満という贅沢な悩みを持っているのは秘密にしておこう。
「、こっちだよ」
「あ、赤司くん!ごめん、お待たせしちゃった?」
「いや、さっき来たところだから気にしなくて良い」
小走りで駆け寄れば、久々に出会えた赤司くんの顔。毎週金曜日は会うことになっていて、そのままどちらかの家に泊まることが多い。けど、先々週の金曜日の夜は赤司くんの仕事の都合で会えなくて、先週の金曜日はわたしの都合で会えなかった。その後も他の日ではなかなかタイミングが合わず、暫く会えない日が続いていた。別に付き合いたてなわけでもないのに、いつまで経っても少女みたいに赤司くんと会えることに喜んでしまう。当たり前のしあわせが、こんなにも嬉しくて楽しいだなんて、赤司くんが初めて教えてくれた。
「赤司くん、夜ご飯食べた?」
「いや、まだだよ」
「じゃあどこかで食べていく?」
「それも良いけど、久しぶりにの手料理が食べたいって言ったら我儘かな?」
「じゃあ駅前のスーパー寄ってこ」
今日はわたしが住んでるマンションの最寄り駅で待ち合わせをした。仕事帰りにわたしがいつも寄る所と言えば、せいぜい近場のスーパーだとかコンビニだとか、あとはドラッグストアだったりレンタルショップだったり。あまりにも日常に浸透しているこれらのお店も、赤司くんと一緒に行くと少しだけ違った景色や気分を堪能出来る気がする。最初は違和感だらけだった赤司くんとスーパーの買い物カゴの組み合わせ。でも、今は慣れた手つきでカゴを持っているし荷物が多い時はカートを使うことも覚えたようだ。冷蔵庫の中は殆どからっぽに近いので、赤司くんが持ってくれてるカゴに次々と食材を入れていく。今日は魚にしようかな、と呟いたら赤司くんが「良いね」と言ってくれたので、迷うことなく決めた。
「赤司くん、明日のは何か食べたい物ある?」
「そうだな…でも朝くらいゆっくりで良いよ」
「そう?」
「は朝に弱いみたいだからね」
「まぁ…いつも赤司くんの方が先に起きてるもんね」
ピッピッとレジを通っていく商品たちを見ながら、ひとりだと余らせてしまうことが多い食材を余らせないで済むということを考えると嬉しかった。スーパーの袋に荷物を詰めると、当たり前のように赤司くんが荷物を持ってくれる。おかずをいっぱい作ろうと色々買い過ぎたせいか、ふたつある荷物のうちひとつを持とうとしたのに赤司くんはそれを許してくれない。勿論その行為は嬉しいし感謝の気持ちでいっぱいだけど、ひとつの袋は軽そうだし何だかいつも申し訳ない気がするからわたしだってたまには荷物くらい持ちたい。
「赤司くん、わたしも持つよ」
「大丈夫だよ」
「えー、だって手持ち無沙汰になっちゃうんだもん」
「…じゃあはこっち」
こどもみたいに駄々をこねるように訴えれば、差し出されたのは赤司くんの大きな手。ふたつの買い物袋を片手で持ってしまった赤司くんのもう片方の手を握ると、指先を伝って全身にしあわせが巡ってくると思えるほどあたたかい。決して広くないわたしの1Kのマンションまであと3分。あともう少し遠くても良いのにな、なんて調子の良いことを考えた。だって、いつもひとりで歩いてる白黒の道が、まるで眩しいくらい輝いて見えるから。