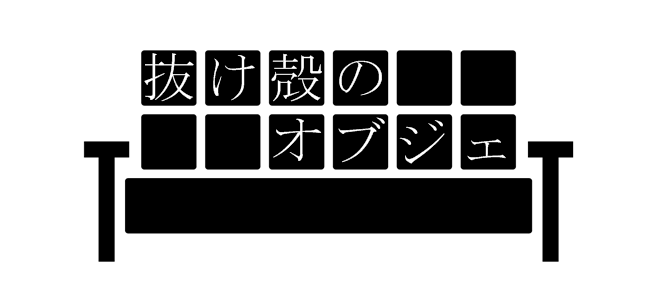▽▲▽
夕方前に美術館で催されていたボッティチェリ展に行き、その芸術性に感化された単純なわたしはイタリアンが食べたいと言うと、赤司くんはすぐにどこかへ電話をかけてお店へとエスコートしてくれた。仕事で使うこともあるという店は、カジュアルながらも品を感じさせ、何より料理が美味しい。カルパッチョとワインが美味しくて、ついついデザートのティラミスも食べてしまうくらいには少し早めのディナーを楽しんだ。家に帰るには時間がまだ早く、赤司くんの家で少しゆっくりしてから帰ることを提案されると、5cmのヒールでステップを踏むみたいに軽やかに歩く。装飾なんてされていないただのグレーのコンクリートの道がレッドカーペットに見えるくらいには浮かれていたと思う。赤司くんの家になんて何回も行ってるのに、少しでも長く一緒にいれることが嬉しくて、今日着ている白のワンピースみたいに純情ぶってみる。
「赤司くんって家具とかのインテリアどこで買ってるの?」
「どうしたんだい、急に」
「だって、シンプルなのにすごい素敵なものばかり」
「そうかな?」
「うん、特にこれ!」
中でも、わたしのお気に入りは今座っているこの黒革のソファーだった。自分の部屋には絶対置けないだろうし、手の届かないような値段な気がしてきっと買えない。溢れんばかりの品を醸し出しているのに、どこか落ち着くこの黒のソファーにゆっくりと埋もれてしまいたいと思うほどだ。その何色にも塗り潰されない真っ直ぐな黒に惹かれる反面、対抗心を燃やしたわけではないけれど、偶然にもわたしは今日生まれて初めて黒とは対の白のワンピースを着ている。普段まったくと言って良いほど白色の洋服を着ないわたしにとっては、荷物も持たずに世界旅行に行くのと同じくらいの冒険だ。ましてや、白のワンピースなんて「ザ・女子」みたいな人にしか似合わないと思ってる。おまけにカレーとかを食べたら汚してしまうんじゃないかと色気の無い事を考えているわたしに白を着る勇気なんて無かった。
「わたしもそろそろ部屋のインテリア変えようかな」
「じゃあ今度一緒に見に行こうか」
「いいね、そうしよ」
そんなわたしが何故いきなり白を身に纏ったか。全身を白に包まれれば、わたしも少しは女性らしくなれるだろうかという単純な好奇心と挑戦だった。結果は見事惨敗。心臓に亀裂が入ってしまったと錯覚する程度には衝撃的だった白いワンピース姿の自分。もちろん悪い意味で。なんだか別人のように感じてしまってひどく落ち着かないのだ。こんな事なら勢いだけでなく試着してから買えば良かったと家を出る直前になって今更後悔したけど、時計の針は赤司くんとの待ち合わせ時間を待ってくれるほどやさしくない。見慣れないせいだと無理矢理な理由をつけて、粉々に割れてしまった心臓の欠片に見ないフリをして家を出た。
「じゃあそろそろ帰るね」
「駅まで送るよ」
「大丈夫だよ、まだ遅くないし赤司くん明日早いんでしょ?」
玄関までの見送りで良いと告げ、上着を持つ。赤司くんの靴の隣に自分の靴が並んでいると、その小ささが愛しく思える。白は似合わないけど、わたしも女なんだと思えるからかもしれない。靴に足をゆっくりと滑らせると、後ろから「」とわたしを呼ぶ穏やかな声が聞こえた。
「すごく似合ってるよ」
本当は、その一言が聞きたかったんだと思う。いつもわたしが髪型を少し変えたり新しい洋服を着ていたりするとすぐに気づいてくれるのに、今日は今まで何も言ってくれなかった。それだけで一抹の不安まで抱いてしまったけど、つまりはそういうことなんだろうと自分を諌めた。無意味な理由を纏わせていたけど、ただいつもとは少し違うわたしを赤司くんに見て欲しかっただけなのかもしれない。だって、赤司くんのたったそれだけの言葉で、わたしのぐしゃぐしゃになった心臓は罅なんて知らないくらい元通りになって、今にも踊り出しそう。
「いつもは会ってすぐ言ってくれるのに、今日は帰り際なんだね」
「恥ずかしくて言えなかったんだ」
「可愛いとか、もっと恥ずかしい言葉はすぐ言ってくれるのに?」
「からかわないで欲しいな。こう見えてもといる時はいつも緊張するよ」
「嘘ばっかり」
「うん」
「うんって、」
「といると落ち着くよ」
上着を着るタイミングを逃してしまった。あれほど早く上着を着て隠したいと思っていた白のワンピース。今はまだこのままでいたい。
「でも、たまにすごく落ち着かなくなる」
「…どうして?」
「ぜんぶのせいだ」
魔法をかけられたみたいに身体が動かなくなって、そのままゆっくりと近づく赤司くんのくちびるを黙って甘受した。火照った身体が熱くて、余計に上着を着ることなんて出来ない。優婉な手つきで髪を耳にかけられ、外気に触れた耳が少しだけひんやりと感じる。けれど、その指で耳を撫でられ囁かれた言葉は、わたしのせっかく元に戻った心臓を再び乱れされた。
「帰したくなくなってしまったよ」
「…朝早いんじゃなかったの?」
「そんなこと、どうにでもなる」
まっしろなワンピースが、色彩を持ち始めるみたいに嬉々としている。似合っていると言ってくれたくせに、どうせいつもみたいにあのソファーでわたしの服を脱がしてしまうのだろう。ベッドにはわたしだけ連れていって、白のワンピースはきっと置いてけぼり。けど、黒革のソファーの上でならあの純白を気取った欲張りなワンピースだってきっと映えるはずだ。