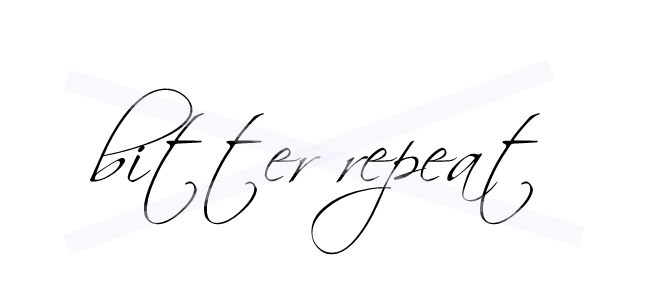あまり慣れないハイヒールを履いたのはひさびさに再会する友人たちとの時間を楽しむため。新調したワンピースは年齢の割に可愛すぎるかもと思っていたけど、実際に着てみると悪くない。こんなにちゃんとした同窓会なんて初めてで緊張したけど、旧友たちの顔を見た途端、びっくりするくらい安心出来た。ホテルのおいしい料理に舌鼓を打ちながら、かつての部活仲間たちの近況なんかを聞いたりして、もう二度と戻れないあの懐かしかった日々に想いを馳せる。
「っち、幹事お疲れ様」
「ありがとう、でもわたしあまり何もやってないから」
「まさかが幹事をやるとは思わなかったのだよ」
「ミドリン、ちゃんはもうじゃないでしょ」
あれからどれくらいの年月が経っただろうか。中学の時にさつきちゃんと一緒にバスケ部のマネージャーをしていたわたしは高校になってからは帰宅部になってしまって、みんなとはほとんどと言っていいほど会っていなかった。さつきちゃんや黄瀬くんらへんとはたまにやり取りしていたけど、実際に会って話すのはひさびさ。それでも、今でもこうして自然に話せるのはやっぱり濃厚な3年間を帝光で過ごしたからだろうか。
「そういえばさっき駐車場で虹村先輩らしき人を見かけました」
「うん、たまたま近くで用があるからついでにって送ってくれて終わる頃にまた迎えに来るって」
「新婚は良いっスね〜!」
「つーかお前、家事とか出来んのかよ」
「青峰くんは相変わらず失礼だね」
こうして談笑して、みんなに祝ってもらうとしあわせな気がする。けど同時に胸の奥底に生まれる罪悪感が身体を蝕んでる気がしてつらい。うまく言葉が出ないときは近くにあった料理を口に流し込むことで誤魔化したけど、味なんてわからなかった。もっと素直に喜べたら、胸を張ってみんなにこの左手薬指の指輪を見せることが出来たらどんなにしあわせだろうか。
「やあ、みんな」
「赤司っち!久しぶりっス」
「申し訳ないがを借りても良いかな。ちょっと打ち合わせしたいことがあって」
「幹事の打ち合わせですか?お二人ともお忙しい中ありがとうございます」
「みんなが楽しんでくれれば何よりだよ」
今回の同窓会は学年全体のなかなか大きい規模のもので、三年時の各クラスから男女各一名それぞれが幹事を務めることになった。普段、飲み会なんかの幹事だってあまりするほうじゃなかったのに、もうひとりの幹事の赤司くんからひさびさに連絡が来ていっしょにやってくれないかと言われた時は本当にびっくりした。でも、もうひとりの幹事が赤司くんなら、とわたしは安心して引き受けることにしてしまったのだ。
目で合図をされたので黙ってついていくと何故かエレベーターに乗り、何も言えない雰囲気のままホテルの部屋に入ってしまった。入ってしまっただなんて、まるで予期せぬ出来事みたいに言ってるけど、本当はエレベーターに乗ったあたりで薄々気づいていた。わたしだってそこまでバカじゃない。ただ、赤司くんは一度も目を合わせてくれなくて、わたしは赤司くんの背中を見ながら黙ってついていくしかなかった、なんて言うのは言い訳になってしまうだろうか。
何階まで上がってきたのだろう。東京タワーやレインボーブリッジ、そして数えきれないほどのちいさく明るい光たち。宝石が足元に散りばめられているのかと錯覚してしまうほどうつくしい夜景が窓に映し出されている。
「今日のワンピース、よく似合ってるね」
「あ、りがとう」
「虹村さんに選んでもらったのかい?」
そう言いながらやさしくワンピースに触れてくる赤司くんの手は、もちろん中学のあの頃なんかよりもずっと骨ばっててずっと男の人の手になってる。この手に触れられてしまうと、もう逃げられないのは身体が嫌というほど分かっているから、わたしはまばたきをすることも出来ずに赤司くんの目をただじっと見つめていた。赤司くんの瞳には、困ったような顔をしているわたしが映っている。
「破いたりなんてしないよ」
「そんなこと、思ってないけど」
「でも早く脱がしたくて仕方ない」
赤司くんとこういうことをするようになってしまったのは、つい最近。同窓会の初めての打ち合わせで久々に会った時からだ。あの頃のわたしはマリッジブルーになっていて、誰にも相談出来る人がいない環境の中、ひさびさに出会った旧友に心を許し、おまけに聞き上手の赤司くんに相談しているうちに…というひどくありがちな明らかに自分がいちばん悪いきっかけからだ。何度もやめようと思ったし何度も「今日で最後」と思いながら一体何回目になるだろう。
「え、今から?」
「大丈夫、あと2時間くらいはあるから」
「みんなが心配するよ。それに、こ、こういうの、もう良くないと思う」
目を見ては言えなかった。だから赤司くんがどんな表情をしたのかは分からないけど、ぎゅっと抱きしめられながら背中のジッパーをゆっくり下げられる。赤司くんはいつだって無理矢理したことはない。多分、突き飛ばして部屋を出て行こうと思えば出れる。なのにそんなこともちろん出来なくて、選択権はわたしにあるはずなのに決定権は存在しないみたいにいつも同じ答えしか出せない。赤司くんを責めることなんて出来ない。決めているのはすべて自分なのだから。
「ま、待って」
「ずっと待たせているのはの方じゃないか」
「待たせてなんて、」
「どうしてオレがずっと独りでいると思う?」
ずるい言葉だと思った。ずるい表情だと思った。そんなさみしそうに微笑まれて、そんなに熱く耳元でささやかれてしまったら、わたしだって赤司くんの背中に腕を回すことしか出来ない。この光輝く夜景を背景に、まるで恋人同士みたいなキスをしてお互いの吐息が熱くなってきたのと同じくらいのタイミングでワンピースが床に落ちる音がした。高そうな赤司くんのジャケットはベッドに投げ捨てられ、肌を隠すものがなくなったわたしの身体がきっと窓ガラスに映っている。
「え、ここで?立ったまま?」
「のせっかくの髪が崩れたらいけないかなと思って」
「で、でもこんな大きな窓の前でなんて恥ずかしいよ」
「ここを何階だと思っているんだい?誰も見てないよ、誰も…ね」
いつも、こういうことをしている時に左手薬指の指輪を外そうという気にはなれず、でもだからこそまるで見られているような気もして罪悪感も生まれる。それなのにこの誰にも言えな関係をやめることが出来ないのは、同じ指輪をしている彼には決して抱けない感情を赤司くんには抱けるからだと思う。それが何かはうまく言えないけど。ただ、彼と離婚して赤司くんと一緒になるなんていう思考は一切ない。赤司くんも多分それは分かってる。
「ぁ…っ、ん…もっ…もう立てっ…な…っ」
「良いよ、そのまま身体ごと預けて」
窓を背にした高級そうなソファーの上で、赤司くんにしがみつきながら快楽に溺れている自分の見苦しい顔とわたしの結婚相手ではない赤司くんの背中が窓に映った。こんなに大きな部屋なのに、いやらしい音が耳を纏わりついて離れなくて苦しいのに気持ちいいなんて本当歪んでる。
「ん…きもち、いい…ぁっ、ぁっ」
「っ…そうだね」
そう言っていつも頭をやさしく撫でてくれるから、わたしはまるで子どもになったみたいになる。子どもだから仕方ない、なんて馬鹿みたいなことを思ってる。
お互いの呼吸が荒くなってしばらくして落ち着くと、赤司くんは動けなくなってるわたしをゆっくりソファーに座らせてくれた。赤司くんがシャワーを浴びてる間のひとりの時間がつらい。このワンピースを買ってくれた男の人とは違う男の人に脱がされてしまったせいで、なかなか着る気になれなくなってしまった。でも、このワンピースをまた着るしかないから、身体だけサっとシャワーを流してまた着直す。メイクも直して、赤司くんのおかげで大して崩れなかった髪型もいちおうすこし手直しする。わたしが洗面台でそんなことをしている間に、赤司くんはカフスをつけながらひとりごとのように話し始めた。
「虹村さんのことは尊敬してる。けど、虹村さんだろうと誰だろうと世界中を敵に回したとしても、君を手に入れたいんだ」
わたしは何も答えなかった。
「今日はすこし強引過ぎたかな」
「…強引だよ。みんなもいるのに連れ出したりなんかして」
「今日の夜、時間あるかなって連絡したのにちっとも返事をしてくれないから」
「さっき聞いてたと思うけど、今日は旦那さんが迎えに来てくれるから…」
まだ言いなれない「旦那」という言葉をこんなところで使うなんて。最低な女だってこと、わたしがいちばんよく分かってる。
鏡を見ながらネックレスをつけてると後ろから赤司くんが抱き着いてきた。さっきまでの男の表情とは全然違う。まるで母親の帰りを待つかのような、さみしそうな子どもみたいな顔。ネックレスの留め具をさっと止めてくれるとまた抱き着かれる。首筋に顔を埋められてあたたかい。
「赤司くん、ずるいよ」
「ずるいのはの方じゃないか。勝手に結婚して勝手に他の男のものになってしまうなんて」
初めて関係を持った日、中学の頃から想っていたと告げられた。でも、そんなこと全然気づかなかったし今更言われたところでどうにもならなかった。それにもし結婚する前に言われたとしても、赤司くんといっしょにはならなかったと思う。ただの勘でしかないけど、多分わたしと赤司くんが祝福されていっしょになることは永遠にない。ふたりだけのこのせまい世界で、限られた時間の中でもいっしょにいられれば良い。それを毎回思ってしまうからこの関係に終止符をうてないでいた。
「オレが唯一手に入れられてないのはだけなんだ」
「…手に入ったら、意外とすぐに要らなくなってしまうかもよ」
「そうかもしれないね、でもそんなこと分からないじゃないか」
頬にキスを落として、腰に回されていた腕が解かれて赤司くんはさっきまでの表情が嘘だったみたいに颯爽と部屋を出る準備し、先に出るよと言ってドアノブに手をかける。同窓会は今日で終わり。幹事として会うこともこれから先は無い。だからと言ってこの関係が途切れるのかどうかは分からない。赤司くんもそんな風に思ったから部屋を出るのを一瞬躊躇ったのではないだろうか。
「赤司くん、かなしくならない?」
その問いに赤司くんが答えることはなく、ひとつのさみしい笑みだけを残して、扉が重く閉まった。