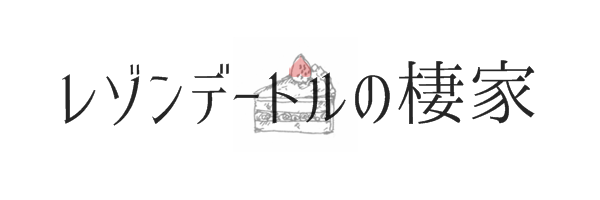「これ銀さんのだから、そんな見たってやんねーから」
「ケチ」
別に強請っているつもりはなかったけど、何も言っていないのにあげないと言われるとなんとなくムッとしたくなったPM3:05。歌舞伎町のファミレスは、若い人たちや仕事をサボってる人たちで賑わっている。
銀さんはわたしが働くファミレスの常連客で、たまに新八くんや神楽ちゃんをよく連れてくる。今日はたまたま仕事が休みでたまたまぶらぶらしていたら、たまたま同じように暇をしていた銀さんとたまたま遭遇した。新八くんはお姉さんと買い物、神楽ちゃんはお友達と遊びに行ったらしく、ぼっちになってしまった銀さんはやけに真剣な顔でファミレスの前をウロウロと変質者みたいに歩いてた。この男でも何か真剣に悩むことがあるのかと声を掛けずにしばらく見ていると、銀さんがわたしの視線に気づいた。やけに明るい顔をされたので反射的に怪訝な表情をしてしまい、無言でその場を立ち去ろうとしたところ捕まった。銀さんはファミレスで開催中のスイーツフェアに興味津々だったしく、その中でも特にイチゴパフェを食べたかったらしい。しかしひとりで入るのを躊躇ったのか、わたしというちょうど良い人間を見つけた途端、あの死んだ魚のような目をしている男が意気揚々とし始めた。何が良くて休日にバイト先に行かなければならないのか。
「銀さんって悩みなさそうで良いね」
「おいおい、こう見えて俺にだって悩みのひとつやふたつくらい…」
「どうせ銀さんの悩みなんてパフェ食べるかどうかとかそういうのでしょ?」
「お前、仮にも俺はここの常連客だぞ?失礼にも程があんだろーが」
「わたしは今日はオフですぅ〜」
わたしが注文したショートケーキがようやくやってきた。持ってきてくれたのはバイト仲間で「デート?」なんて聞かれたので全力で否定をした。ひとつしか乗ってないイチゴにフォークを刺し、ひとくち。イチゴはあっという間に消えてしまった。下のクリームやスポンジと一緒に食べれば良かったのに、イチゴだけ先に食べてしまうと途端にケーキから哀愁が漂って来たような気がして、申し訳ないけど食べる気が少しなくなってしまった。本来のわたしならこんな食べ方しないはずなのに、先にイチゴだけ食べてしまったのはどうしてだろう。
「で、お前はオフの日だって言うのに何くらい顔して歩いてたんだよ」
「え?くらい顔してた?」
「くらいっつーか辛気臭ェ」
「別に何もないけど」
「ちゃんは嘘をつくのが下手ですね〜」
「ちゃん付け気持ち悪い」
「ひどいんだけど。銀さん泣きたいんだけど」
銀さんはちゃらんぽらんに見えて、意外と人を見てるからなんだか悔しい。わたしはもう軽く20年以上生きているというのに未だにわたしのことを理解出来ていない。でも、銀さんは多分わたし以上にわたしのことを分かってる気がする。別にわたしが特別とか言いたいんじゃなくて、銀さんは多分そういう色々な人や事を見てきたんだと思う。
「大したことじゃないし」
「依頼料はこのパフェ代で良いから話してみろって」
「奢るなんて言ってないんですけど!」
「…まあそれはどっちでも良いけどよ、口にしたらスッキリすることもあんじゃねーの」
道で銀さんと会う少し前、公園の前を通ったら不思議な感覚に襲われた。青空に響く伸び伸びとした子どもの笑い声。それを微笑ましく見守っている夫婦。女の子同士がブランコで無邪気に語り合っている光景。老夫婦がベンチに座ってゆっくりと時間の経過を楽しんでいる姿。ハイテクなこのご時世でも公園はまだまだ活気がある。しあわせそうな景色は目の前にたくさん存在しているのに、自分はそのどれにもなれなくて、この世界のピースにもなれないような気がした。特別な夢も希望もない、未来のことを考えた時にただ無性に不安を感じるような生き方をしている自分に、他人からしたら当たり前みたいな公園の光景が眩しく見えた。ここにいる人たちと同じ空気を吸って生きている筈なのに、実際に起きている事実なのに、映画みたいなフィクションの世界に感じられてしまったのだ。
「…何かふと、わたしもしあわせ感じたいなって思って」
「ざっくりしすぎだろ」
「銀さん万事屋でしょ、察して。そしてあわよくば何とかして」
「んな無理言うな」
「ひどい、泣いちゃうぞ」
「…仕方ねーな」
なんとなくすべてを語るのは恥ずかしい気がして、銀さんには結論しか言えなかった。いつまでわたしはファミレスで働いているんだろうとか、わたしもいつかは誰かと一緒になれるんだろうかとか、ひとりで死にたくないとか、そういう漠然とした憂いが年齢と共に重くなってきた気がする。もう大人なのに自分の先が見えないことが嫌で、馬鹿にされたらきっともっと寂しくなると思ったけど、ひとりでは何も出来なくて銀さんに縋るような言葉が零れてしまった。そんな自分に少し嫌悪感を抱いていると、銀さんの「ほら」の声と共に殺風景だった世界が少しだけ鮮やかになった気がした。
「何コレ?」
「俺が大事に取っておいたてっぺんのイチゴだ。味わって食えよ」
さみしくなってしまったショートケーキが、再び色彩を持ち始めたみたいに明るく生まれ変わる。今度は生クリームとスポンジと一緒にちゃんと食べてみた。思わず「おいし」という言葉が漏れると、銀さんは何も言わずに笑っていて、なんだか胸の奥がじんわりとあたたかい。
口の中に入れたイチゴは人生みたいに酸っぱい味がしたけど、少しだけあまい気がした。