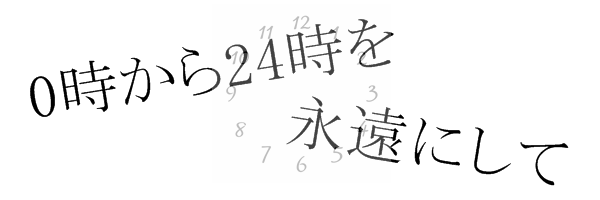「?いい加減顔出してくれないと寂しいよ」
そんな砂糖10杯分の紅茶みたいな言葉を囁かれたって、絶対に顔なんて出してやらない。顔を出したら更に、ガムシロップのようなキスと言葉が雨より優しく、シャワーより激しく降ってくるに違いない。申し訳ないけれど、今はまだそこまで大人で強い心臓は持ち合わせていないのです。真っ白なシーツの上で、白い羽毛入りのふわふわふとんで自分を全身隠せば真っ黒な世界。そんな世界はわたしだって嫌だ。けど、白にも負けない輝くような世界を見るのはまだ躊躇われる。
「はいつもそうなっちゃうな」
そんなところも可愛いから良いけどね、なんてあまったるい台詞をハリウッドスターのようにあっさり言うもんだから、わたしを覆い隠してくれている羽毛に甘さが染み込んできた。これではこの甘さに耐えられなくなって、やがては顔を出さなければいけなくなる。
早く眩しい世界に飛びつきたい、でもそんな想いに潜んでいるこの躊躇い。初めてじゃない。初めてじゃないけど、何回経験しても慣れないそのしあわせ過ぎる時間。贅沢だということは百も承知。けれど、正解の答えに悩むような言葉を、流星群が降って来るみたいにたくさんわたしの肌の上に落としていく彼が悪い。わたしの肌の上を滑るように駆けるその手と唇で、自分が落とした星を拾ってくれたら良いのにそれはしてくれない。それを拾い集める方の気持ちにもなって下さい。ただの羞恥しか残ってくれない。
「だって、恥ずかしいから」
「どうして?」
「色々聞いて来たり…色々恥ずかしいこと言ってくるじゃん」
「例えば?」
「そ、そんなこと言わせないでよ!」
布越しに聞こえる彼の笑いは楽しんでいる以外のなにものでもない。そもそもこういったやり取りも何度目だろうか。何回わたしに「恥ずかしい」という言葉を言わせれば気が済むのかと問いたい。ただでさえ熱が上がって自分では抑えることの出来ない感情と温もりに浸りきってる時に、真っ直ぐ過ぎる言葉や問いを囁かれたって答えられるわけないじゃない。わたしを快楽に溺れさせて答えられないようにしているのはまさに貴方だと言うのに。キャッチボールじゃないんだから、来た言葉を元の場所に返すことなんて出来ない。更に悔しいのは、わたしが何も答えられずに彼の下で熱の温度を上げることしか出来ないということ。何かを発しようと唇を動かしても、漏れるのはスムーズな言葉なんかではとてもない。
いつもは大体、彼が謝る気もないくせに「ごめんごめん」と笑いながら、続くように「でも顔見たいから見せて」だとか「そんなところもオレにとっては可愛くて仕方ないから」だとか「オレだけが知ることの出来るの可愛い一面だろ?」だとかそんな言葉たちと一緒にわたしの壁を少しずつ崩してくる。結局いつもわたしが負けてしまうのだ。だから今日は絶対に負けない。どんなに甘い声を囁かれても、どんなに眩しい言葉を落とされても、どんなに輝くような台詞を渡されても、絶対不可侵を貫いてみせる。
「じゃあひとつだけのお願い何でも聞いてあげるよ」
「…本当?」
「だからもう顔出してくれる?」
この他人からしたら無駄以外の何物でもない戦いが、このような終息を迎えるとは想像していなかった。しかし、これはもうわたしの勝ちである。彼はお願い事を聞くという捧げ物を持ってわたしに降伏したのだ。恥ずかしいから顔を見せないという、当初のわたしの感情はどこへやら。いつの間にか勝ち負けにこだわってしまった為の成れの果てが、あと数分後に襲ってくる後悔だとはまだ気づかない。
「本当に何でも良いの?」
「良いよ」
我が儘な恋人にご機嫌を取るように褒美を与えてあげようとする男。そんな光景をテレビでも映画でも本でも、友人からの話でも日常でも見かけたり聞いたことがあるような気がするが、まさに今がそれに近い。一言だけ言っておきたいのは、あくまでわたしの我が儘で顔を見せていないのではなく、その根源は彼だということ。少しだけ見せてやるか、という非常に上から目線のわたしは鼻から上、つまり目だけを光の下へ曝す。眩しい、ライトではなく彼の微笑みという光が。困っている様子なんてなく、笑みを浮かべている彼の顔は最初からすべての物語を知っている作家のよう。
それにしても、困った。彼は常日頃からわたしのお願いを叶えてくれる魔法使いなのだ。どこかへ行きたいと言えばどこへでも連れて行ってくれるし、何かを食べたいと言えばそこへも連れて行ってくれる。天国に行きたいと言っても地獄へ行きたいと言ってもきっと叶えてしまう。そんな彼に一体どんなお願い事をしようか。
「じゃあ…ぎゅーしてちゅーして」
言葉にした言葉を、自分の耳で聴いた瞬間、時が止まった。いや、止めたのは自分か。何を言っているのだろうと。お願い事ってそんなお願い?そんな当たり前のように叶えてもらえるお願い?自分でも驚くようなそのお願い事は今叶えられなくてもそんなに大変なことにはならないので、どうか夜空へ消えて下さい。そう願いながら光を感じているこの世界を、またもや羽毛のふわふわふとんで覆う。ああ、ようやく先程までと同じ暗さ。やはりわたしにはこの暗さがお似合いなんじゃないだろうか。
「あれ?ふたつもだなんては欲張りだな」
けれど瞬く間に再び光で満ちている眩しい世界。強引に取られた羽毛がきっと中で啼いてるよ。そんなわたしの心情が顔に出てしまったのだろうか。わたしの上には彼が、彼の上には羽毛が覆いかぶさってきた。このまま彼に乗っかられてしまったら重くて無理。わたしも軽い羽毛の方が良い、なんて下らないことを考える余裕はあまりない。先程まで冷たかったシーツと羽毛の間。彼が一緒に入ってきたことで、そこは北極から一気に砂漠の国へと変化を遂げる。その熱さに焦がれてしまう。身体ごと、心ごと。
「ふたつじゃない、1セットです。一連の流れです」
顔の横に彼の腕、という鉄壁を崩すことは出来ない。触れ合っている肌が焦がれて砂漠になる前に早く潤いを下さい。貴方ならそんなこと簡単でしょう。ああ、でもあなたが与える潤沢はわたしにとっては、灼熱と紙一重。どっちに転がるかはわたしでさえ分からない両刃の幸せ。この心臓が鼓動し過ぎて破裂する前に、この心臓の音が夢のような時間に音を止める前に。どうかわたしに愛と幸せを。
「わかったよ、そんな可愛いお願いされたら仕方ないな」
いつの間にか主導権が入れ替わっているこの事態に眉を潜めるどころか、身体の外から心の内にかけて少しずつ加速し始める感情。先程までよりも唇の弧を三日月に近いカーブさせた彼は、この暗い世界を照らして光そのものにしてしまう。頭を撫でるその手つきは、星が虹を滑り落ちるよう。きついくらい抱きしめられるその抱擁は、雲から絞り出される雨という名の涙のよう。優しく重なるふたつのその唇からは輝きが漏れる。
「そんなんじゃ足りない」
珍しくも一瞬驚いた表情を見せた彼はすぐに、それはもう楽しそうに嬉しそうに笑った。その表情でさえ、何て眩しいんだろうと思ってしまうわたしは、もうひとりきりの暗がりの世界には向いていないようだ。これから顔を隠す時は、彼の肌にしがみついて隠してみようか。
何だかんだ言っても、この余韻は嫌いじゃない。