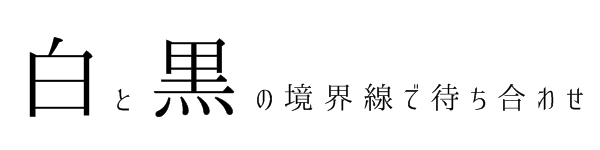「まだ目がとろんってしてる」
「だって、」
「何?」
「言わせないでよ」
そんな幸せなひとときを味わっても尚、私の脳みそは未だどこか広い宇宙を彷徨っているかのよう。ベッドの中で彼の鍛えあげられた身体に寄り添うと、ぎゅっと抱き締められてせっかく冷めてきた熱がまた少し上昇し始める。早く「服」という鎧を着て、彼の思い通りにさせられてしまうこの身体を守らなければ。卑猥な音を生み出し喘ぐことしかしていないのに、疲労感が蓄積されている重い身体をゆっくりと起こし、辺りを見回す。
「あれ、下着が無い」
「え?」
「辰也くん、私の下着どこやったの?」
「夢中であまり覚えてないな…」
「えー、どこ行ったんだろ」
まだ暗い室内の中、手探りと微かに見える物の形を目の端で必死に捉え、少し前まで身につけていたランジェリーたちを探す。ブラもショーツも見当たらない。いつもベッドの下に紛れ込んでいたり、シーツと一緒にぐしゃぐしゃに巻き込まれていたり、椅子にかけられていたり、服の上に置かれていたり。心当たりなんてそれくらい。最後に触ったのは間違いなく脱がした彼だろうけど、彼の下で散々恍惚に悶え動いていた私が足で何処かにやってしまった可能性もなくはない。ベッドの下?枕の下?どこにいるの、私のボディーガードたち。
「電気つける?」
「…ヤダ!」
「は本当明るくするの嫌がるな」
「だって恥ずかしいじゃん」
「恥ずかしがることなんて何もないのに」
彼の気休めであろう言葉を鮮やかにスルーし、ベッドから降りて冷たいフローリングに足をつける。すっぽんぽん、裸体で私は何をウロウロしているのだろう。みっともないというか、色気の欠片もない。彼は辺りを少し探してくれるだけでベッドの中から出る気はあまり無いようだ。私には彼の考えがある程度読めてる。どうせ「あとで良いじゃないか、こっち戻っておいで」とでも言うつもりなのだろう、と思っていたら本当に言った。でも、今夜これ以上愛を注がれてしまったら私の身体は壊れてしまう。彼の素肌に触れるだけで子宮が疼きそうになるこの淫乱な身体に育てられてしまった私の身体に、自分自身同情する。
「お気に入りのブラだったから無いと困る」
「今日のの下着、いつものと雰囲気違ってたね」
「うん、この前つい衝動買いしちゃったやつ」
「似合ってたよ、脱がすのが惜しいと思ったくらい」
サルートで買った漆黒のブラとショーツ。普段はついついピンクだとか水色だとか淡い色に走りがちの私が思い切って買った官能的な黒。バラをモチーフにしたレースが程よくあしらわれていて、可愛くも大人びる事も出来る逸品。少し背伸びをし過ぎたかとも思ったけれど、いつもより少しだけ大胆になれたような気もして、まさに魔法のランジェリーだと錯覚したくなる程なのだ。
「ちょっとだけ明かりつけて」
「はいはい」
「ちょっとだけだよ、全部つけなくて良いからね!」
「分かってるよ」
ダイヤルを回してゆっくり、淡くライトアップ。眩しい、とまではいかないけれど予想以上の明るさに若干躊躇ってしまう。彼に背を向けていたのは幸いだったかもしれない。彼が調整した明かりは私が想定するよりはるかに明るく、私の全てを赤裸々にしてしまう一歩手前だ。
最初から素直に明かりをつけていれば良かったかもしれないと思う程、私の愛しのランジェリーたちは簡単に見つかった。白いシーツに絡まっていたランジェリーを目にした瞬間、少し恥ずかしくなったのはこのランジェリーたちが自分の姿に重なって見えてしまったからだろうか。そんな邪な考えを打ち消さなきゃと、慌ててブラジャーをつけようとしたけどなかなか上手くホックがかかってくれない。
「辰也くん、うしろお願い」
身体を起こした彼が私の背中に触れると、少しだけ反応してしまった正直な身体。自分で頼んだくせに、どうして私の顔も身体も熱を灯ってしまうのだろう。彼はホックを外すのも上手、つけるのも上手。今までにも何回か彼に後ろのホックを止めてもらったことがある。私は何も言っていないのに、毎回どんなブラでもちょうど良い位置でホックを止めてくれるのが彼のすごいところ。私より私の身体を知り過ぎてしまっているようだ。
金具が噛み合った感覚を背中で感じ、お礼を言おうとするとそのまま後ろからぎゅっと抱きしめられる。ちょうど耳の位置で囁くように言葉を紡ぐ彼は、やっぱり形容出来ないほど罪深い。
「うん、やっぱりsexyだし可愛い」
「そう?じゃあ買って良かった」
「本当、眺めてもいたいし脱がしたくもなるよ」
「え、さっき脱がすの惜しいって言ってたじゃん」
「脱がしたいけど脱がしたくない、脱がしたくないけど脱がしたい、ってこと」
「ワケ分かんない」
「男心は複雑ってこと」
髪の毛を全て右側に寄せられ、空気に触れた左側の耳が彼のくちびるで熱くなる。ブラジャーの紐を指で撫でられているだけなのに、背中がほんの数角度沿ってしまった。でも逃げられなくて、彼の大きな手の平が私のブラに覆われた胸を優しく撫でる。揉む程ではなく、触れられている程度の感覚なのに、私をその気にさせるには充分だ。
「ねえ、」
「な、に」
「もう一回、したくなっちゃった」
せっかくかみ合った金具がプチっと外れる音がして、背中がすべて露わになると身体が余計無防備になる。彼の前にさらされた肌の面積は大して変わらない筈なのに、途端に恥じらいが再び襲ってきた。ホックの位置だった部分を彼の指で縦一直線になぞられると、くちびるから漏れてしまった声が彼を余計悦ばせ、愉楽の世界に誘ってしまったらしい。逃げれないことは理解しているし、逃げたいとも思っていない。だからまだ言葉が言葉になるうちに、喋っておかなければ。
「一回で、良いの?」
この大人なランジェリーに少しでも似合うように気取ってみたけど、彼に剥ぎ取られてしまった今では最早関係ない。
「にそんなこと言われて我慢出来る程、オレは大人の男じゃないよ」
―さて、再びこのランジェリーを纏えるのはいつになるだろうか。