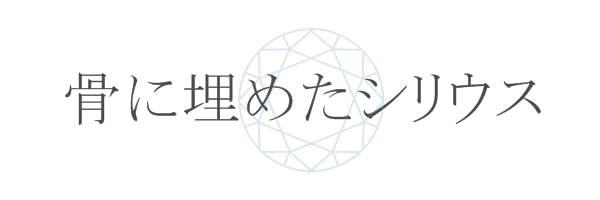「コーヒーの良いニオイがする」
「も飲む?」
「ブラック飲めないの知ってるくせに」
鼻腔をくすぐるコーヒー独特の香りが、どこか落ち着きを与えてくれるように感じるから不思議だ。苦くて飲めないブラックコーヒーでも、意志とは反するようにその香りに恋をしてつい舌の上と喉の道を通らせたくなるような矛盾が、いつもブラックコーヒーを注文する彼といると発生してしまう。決して私の身体に染み込むことは無いはずなのに、香りが漂うこの空気だけで、深みのあるコーヒーブラウンに包まれるような感覚に浸ってしまいそうになる。
頬杖をつきながら彼に問うとふと、親指がひんやりとした自分の首元のチェーンに触れた。先日彼から誕生日プレゼントに貰ったピンクゴールドのネックレス。杜撰に扱ってしまうと壊れてしまいそうな華奢な作りは派手過ぎず、然しひと粒の小さなダイヤモンドが控え目ながらも紛れもない存在感を放っており、その輝きはまるで冬の夜空に煌めく星のようだ。貰った直後はすごく嬉しくて、もちろん今だって嬉しい。ただ、普段から頻繁にネックレスをつけるわけではなく、クリスマスや彼の誕生日など特別なデートの時くらいにしかつけていないネックレスを、いくら貰ったからといって今日のような日常に等しいデートにつけるのはあからさま過ぎるのではないだろうか。しかし、つけないと彼が残念がるかもしれない。そんな葛藤の渦に飲み込まれた私は結局曖昧な海に溺れてしまい、チェーンは鎖骨の上を通り剥き出しになりながらも、主役であるダイヤモンドはトップスの下に隠すという中途半端なことをしてみた。
「にはカプチーノがよく似合うね」
「馬鹿にしてる?」
「まさか。可愛らしいって意味だよ」
わざとらしく、白いクリームたっぷりのカップを両手で包み込むように持っている自分が恥ずかしくなった。ブラックが飲めない私はカフェに行くと大抵カプチーノを注文する。正直、カプチーノとカフェラテの違いも見た目以外明確には知らないけれど、乗っている泡がなんとなく可愛いからという、なんとも自分には似つかわしくない乙女らしい理由でカプチーノを注文している。まさか、彼もカプチーノを可愛いと思っているのだろうか、それ以上は自惚れているような気がして考えることをやめた。
店を出てコートを着ようと吐いた息はもうすっかり白い。夜空に生まれたこの白い息には確か水蒸気が多く含まれていて、人間の温度と外の温度の差が大きいとその水蒸気が急激に冷やされて水滴に変わることから白く見えると彼に教えてもらったことがある気がする。そんなことをぼんやりと考えていると、彼の冷たい指先が私の首の後ろにひやりと触れた。驚いてつい声を上げてしまった自分を恥ずかしがる暇もなく、この冬に似合う彼の笑顔と出会う。
「どうしたの、急に?」
「やっぱり。のことだからつけてきてくれると思った」
後ろからチェーンを辿るように撫でられ、何に戸惑ったのかは分からないけれど私は何も言葉を発せなくなってしまった。内側に秘めていたネックレスが流れるように露わなってトップスの上で目映い光を放つ。こんなことならもっと上質な、この光り輝く星に似合うような服を着てくれば良かった。人肌に馴染むピンクゴールドは当たり前のように肌に浮かぶ鎖骨とも同化する。私の鎖骨はこんなにも美しかったのか。満足そうな表情を浮かべる彼は、やがて私の指を絡めとり歩き出す。
「によく似合ってるよ」
華奢なラインを描くピンクゴールドも、光輝を放つダイヤモンドも、この鎖骨に這うようにこのまま肌に骨に沈んで私の身体の一部になってしまえば良いのに。ふと空を見上げれば、紺青のカンバスに雪の結晶のような星たちが穏やかに輝いていた。