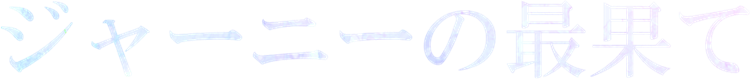「辰也くんはどこか行きたいところある?」
「オレはの行きたいところで良いよ」
「う〜ん…パンフレット見ると余計悩んじゃう」
日曜日の正午過ぎ、彼とランチを終え歩いている時にたまたま通った旅行代理店の前に並べられた数えきれなほどのパンフレット。そういえばここ数年は忙しかったりタイミングを逃して、久しく旅行らしい旅行に行けていない。見惚れるほどの美しい自然や息を飲むほど壮大な遺跡の写真はわたしの歩く足を止めた。きっと子どもみたいに目を輝かせていたのだろう、辰也くんが「今年はどこかに行こうか?」と言ってくれたので、わたしは首を大きく縦に振った。
適当にパンフレットを貰って、色褪せたビンテージの看板が目を引く近くのカフェに入る。アンティーク調のソファーに座ると、予想外に少し硬くて吃驚した。黒に近いチョコレート色のテーブルには似合わない色鮮やかなパンフレットを並べて、ペラペラとページをめくってみる。辰也くんの頼んだコーヒが先に来て、わたしは飲めないけれどブラックコーヒー独特の良い香りに浸っていた。
「国内か海外かは決めた?」
「それすらも決められない…」
「の優柔不断なところが出てるね」
「うっ…おっしゃるとおり」
「どのくらい休みが取れるかで決めても良いんじゃないか?」
「そうだね、一週間くらい取れるなら海外も行けるし」
わたしが頼んだカフェラテには可愛いハートのラテアートが丁寧に描かれていた。ラテアートは見るとすごい癒やされるのに、飲むと崩れてしまうのが勿体無い気がして思いっきり飲むことを躊躇ってしまう。描かれたハートを出来るだけ崩さないようにゆっくりと飲む。白いカップはちょうど良いサイズで、飲み干すまでにはそれなりに時間が掛かるはずなのに、わたしの行きたいところは未だに決まっていなかった。
「…ダメだ、分からなくなってきた」
「気分転換に少し外でも歩こうか?」
「うん、そうしよ」
もうすぐ梅が咲く時期だと言うのに外は変わらず寒くて、それでも手袋をしないのは辰也くんと手を繋ぎりたい乙女心からだ。休日のゆっくりとした時間が流れる住宅街を歩く。普段、殺伐としたオフィスの中でひたすら時間に追われるように過ごし、通勤の朝と夜、それから昼くらいにしか外に出ないわたしにとって、この穏やかな光景はいつ見ても新鮮だった。公園に寄ると、わたしたちみたいに恋人同士が寄り添うように歩いていたり、家族連れがブランコやシーソーで楽しそうに遊んでいたり、老夫婦がベンチでしあわせそうな時間を過ごしている。この世界がなんだかすごく特別なものに見えて「温かい飲み物でも買ってくるよ」と辰也くんが自販機に行ってる間に、ベンチでひとり待ちながら何だか少し泣きそうになった。
「お待たせ」
「ううん、ありがとう」
「そういえば、さっき屋台でクレープ屋さんが出てたよ」
「え、本当?」
「さっきのカフェで何も食べなかったから、あとで行ってみようか?」
「うん行きたい!」
薄いピンクのネイルに気を遣ってくれた辰也くんが開けてくれたプルタブから、あまったるい香りが漂う。暫く温かさを堪能するために缶を両手で持っていると、彼の指がわたしの首とマフラーの間に滑りこむ。ホットの缶を持っていたせいか、いつもよりは冷たくない辰也くんの指に動脈が騒ぐ程度には驚いた。マフラーによって埋もれていたわたしの口元が辰也くんの指によって救出される。それだけなのに、別にキスとかしてるわけじゃないのに、それ以上のことだってもうしてるのに、こんな事で身体が硬直しそうになってしまうなんて恋を知らない乙女のように純情ぶってるみたいで恥ずかしい。そんな気持ちを辰也くんに読み取られないように「ありがと」と小さく呟くとやさしい笑顔をくれた。特別なことなんて何もないのに、この時間がたまらなく愛しい。
ああ、なんだ。改札を抜ける必要なんてない、パスポートなんて要らない。重いカバンを持って無理矢理どこかに行く必要なんてなかった。
だって、ただ青空の下に広がる穏やかな道をふたりで歩いてるだけで、まるでしあわせしか知らない世界へ旅立ったみたいに楽しいんだから。