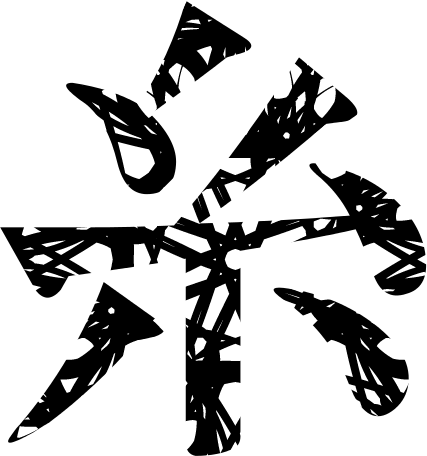案内されたシアター3で上映された映画は、愛と友情が語られるコメディタッチのアクションもののようだった。―ようだった、と客観的に述べてしまうのは観ていた映画の内容が全く頭に入ってこなかったからかもしれない。
たまたま練習がない日曜日の午後、木兎さんから「映画を観に行こう」というメッセージが入った。特に断る理由もなく待ち合わせの映画館まで行くと、木兎さんの隣には彼女のさんがいた。木兎さんが同じクラスの
友人から映画のチケットを3枚もらったらしく、木兎さんとさん、そしてお互い知っているという理由で残りのひとりに俺が選抜されたらしい。Vネックの白いTシャツにデニムというラフな服装なのに大人っぽい。きっと足元の華奢なヒールのせいだ。一年くらい前になるだろうか、木兎さんがさんを彼女だとと初めて俺に紹介した時、「木兎さん、しあわせそうだな」なんて思ったことをよく憶えている。木兎さんがさんに俺の話をよくしてくれているらしく、俺も彼女とは必然的に会話を交わすようになっていた。廊下ですれ違えば挨拶をしたり、練習後に木兎さんと3人で帰ったこともある。
映画を観終わったあと、まだ映像の余韻が残っているのか「あのシーンすごかったな!!」と興奮するように語っていた木兎さんを微笑ましく見るさんの横顔を、俺はずっと見ていた。解散するにはまだ早く、「飯でも食うかー」と言った木兎さんのスマホが光ると木兎さんは子どもみたいに分かりやすく顔を歪めた。どうやら同じクラスでもある部活のマネージャーから借りていたノートを返すのを忘れていたらしく、呼び出しが掛かったそうだ。
「マジでスマン!俺、行かなきゃ殺されるかも…」
「また大げさに言う…」
「赤葦…あいつお前には優しいかもしれないけど俺には超こえーんだって!」
「良いから光太郎早はやく行ってきなよ」
「もスマン…赤葦、悪いけどのこと送ってってやって」
「はいはい」
余程焦りを感じているのか、木兎さんはダッシュでその場を駆けて行った。あっという間に見えなくなった木兎さんの姿を見て、あんなに早く走れるんだとかどうでも良いことを思った。「とりあえずここから移動しましょうか」と声を掛けると、やわらかい声で「うん」という答えが返ってきた。駅に向かう足をすこしだけ遅くさせていることに、彼女は気づくだろうか。
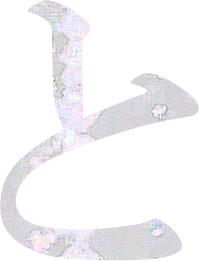
「ねえ赤葦くん」
「何ですか?」
「どうして、あんなことしたの?」
「あんなこと?」
「映画館で手…」
「ああ、繋ぎたくなったからに決まってるじゃないですか」
「光太郎にバレたらどうするの?」
「どうせならバレた方が好都合ですけど」
そうやってすぐ困ったような顔をする―。
関係を持つようになったのは、半年ほど前からだった。いけないことだとは分かっていながらも、先輩の彼女であるさんに恋をしてしまった。ありがちだけど、彼女が木兎さんのことで落ち込んでいる隙を狙って、それまで自分で制御していた感情のブレーキをすべて外した。それからズルズルと木兎さんに内緒でふたりで逢瀬を重ねたり、まるで恋人同士のような時を過ごした。ダメだとは分かっているのに、そう思えば思うほど感情は加速するばかりで醜い情欲は増すばかりだ。
そもそも、俺、さん、木兎さんの横並びで座ってしまったのがいけなかったと思う。上映が始まってから20分くらい経った頃だろうか。暗がりの中でふと、さんの手の上に自分の手を重ねていた。ちいさくて細い指には熱を感じた。アクションシーンに吃驚したかのように一瞬肩を震わせたさんは俺の手をそのまま受け入れ、気づいたらお互いの指の間に隙間なんて存在していなかった。
「俺だって、本当は木兎さんに隠れてこんな事したくありません」
木兎さんを裏切るような真似はしたくない。それは俺もさんも共通の思いだった。けど、だからと言ってこの関係をやめられないのも共通のジレンマだ。困ったような顔を見せたさんはいつもどこかに影を感じさせる。でも、その表情がどうしようもないくらい好きで、もっと俺のことで困ればいいし悩めば良いとさえ思う。俺のことだけ考えてくれればいいのに、なんて子どもじみた思想まで生まれてしまう始末だ。木兎さんと真正面から向き合うことも出来ず、こうして水面下でさんに自分の欲をぶつけることしか出来ない自分がたまにすごく不愉快になる。
「でも、それと同じくらいさんのこと諦められないんです」
「…ずるい」
「その言葉、そっくりそのままお返しします」
ずるいのは貴女だ。どうしてこんなにも惹かれてしまうのか。
こんな街中で、誰がいるかも分からないのに俺はさんの手を取って歩き出していた。人目をおそれてか、手を勢いよく引っ込めようとしたさんだけど、俺は離さなかった。いや、離せなかったと言った方が正しいのかもしれない。繋がったふたりの手はもう共存してしまっているのだから。
アスファルトを踏む足を噛みしめるように歩いていると、突然さんがバランスを崩して俺に体重を預けて来た。急に感じた重みに一瞬驚きはしたけど、それより咄嗟にかけられた全体重の軽さに驚かされた。支えた時に触れた腕はやっぱり細くて、バレーのサーブなんか受けたらあっという間に壊れてしまいそうだ。
「うわっ」
「危ないですよ」
「ご、ごめん」
「…さん、ヒールとか履くんですね」
「え、どうして?」
「いつもより距離近いなって思って」
目線がいつもより近い。木兎さんは気づいてなかったみたいだけど、俺は今日さんと会った時にすぐ分かった。顔が近くなると、いつもよりさんの表情が分かる気がするし、キスだってしやすい。けど、人目も憚らずにキスなんて出来るような関係じゃない。さんが木兎さんの彼女じゃなかったら、さんと出会ってなければ、なんて存在しないもしもの話ばかり考えた。けど、答えは結局いつだって同じ。
「ああ、ヒール8cmくらいあるから」
「似合ってますよ」
「ありがとう」
「でも、靴ずれしてますよね」
映画館を出る時、前を歩く木兎さんとさんの後ろで、さんの踵の部分がうっすら赤くなっているのを見逃さなかった。どこか座れる場所はないかと、近くにある静かな遊歩道のベンチに座らせた。靴を脱がせて膝を地につけた自分の太ももに彼女の片足を乗せると、踵だけではなく親指や小指まで赤くなっていて、ちいさな足が悲鳴を上げているようだった。
「絆創膏貼ります」
「赤葦くん、ごめんね」
「履きなれない靴なんて履くからですよ」
「うっ…本当はいつもの靴で来るつもりだったんだけど…」
「けど?」
「今日はこの前買ったこの靴で行きたくなっちゃって」
俯きながら困ったように笑って話すさんは、理由を言わなかった。けど、隠された理由の奥底に秘められた感情は残念ながらこぼれてしまっている。だから「どうして?」なんてことは聞かない。
「それって、誰のためですか?」
その問いかけに答えなんて望んでるわけじゃない。だから、言葉を紡ぎかけた彼女のくちびるを縫うように、卑怯なキスをした。