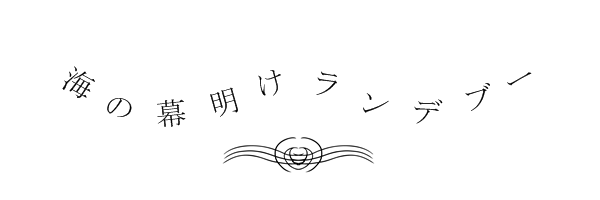
「さん、今日は何買うの?」
「酒」
「こんな時間から?」
「明日休みだし」
夜のコンビニにふらりと行く、という時間に束縛されない自由な感覚が好きなのかもしれない。明日のことは考えなくて良い解放感によって、後先考えずについつい買いすぎてしまうのが自分のダメなところだと思う。ストロング系チューハイを何本か犬飼くんが持ってくれているカゴの中に入れ、新発売のお菓子なんかも混ぜればあっという間に山が出来る。
コンビニを出ると、やっぱり街が眠っているみたいに静かだ。ほとんどわたしの物だと言うのに当たり前のように荷物を持って、当たり前のようにわたしの右手を繋いでくれる犬飼くんの手は今日も無条件にやさしい。コンビニから5分程のところにあるわたしのマンションへ一等星をランプ代わりにしてゆっくりと向かう。ひとりでは決して狭いと感じない1Kの部屋も、高校生の男の子が来ればすこしばかり窮屈に感じる。通販で唯一残っていたミルキーピンクのソファーの上でくつろぐ犬飼くんには違和感の欠片もない。わたしは飲み物やお菓子を適当にローテーブルの上に用意して、毛並が少し長めのベージュのラグに座った。こうして、ふたりでのんびりしながらテレビを観たりボーっとする時間が好きだ。犬飼くんに急な任務が入らなければ、大抵このまま泊まっていくことが多い。
「さんが酒って珍しくない?」
「そう?たまに飲みたくなるんだよね」
「ストレス溜まった時とか?」
「そうそう…って!え!?なんで?!」
「さん、分かりやす過ぎ」
「う、ごめん」
「なんで謝んの?」
残りが少なくなってきた缶をゆるく回しながら、慚愧の念がふつふつと湧いてきた。せっかくふたりで過ごしていると言うのに、仕事のストレスを溜めて挙句の果てに未成年を前にして酒を飲むなんて。少し俯いていると、後ろからわしゃわしゃと頭を撫でられて、わたしよりもしっかりしているふたつ下の男の子に涙が出そうになった。あ、なんか久々に酔ってるかも。最近涙脆くなってしまって困る。小さく「ありがと」と言うしか出来ない愚かな女を許してください。
「っていうか酒ってそんなに良い?」
「うーん、まあ」
「ねえ、俺も一口飲みたい」
「ダ、ダメだよ!未成年なんだから!」
「子ども扱いされるの好きじゃないんだけど」
「子ども扱いも何もまだ未成年のコドモでしょ!」
「そのコドモに慰められてるのはどっちか分かってる?」
「うっ…」
確かに、わたしも未成年の頃はお酒という飲み物に対して興味や憧れといった類の感情を持っていた。大人たちはみんな揃ってお酒は良いものだと言うし、何よりすごく美味しそうに飲む。わたしが初めて飲んだのは甘めのカクテルだったから、最初はジュースと変わらないと思ってゴクゴク飲んでいたけど、やはりアルコールという成分は人を弱くするらしい。味に反して苦い思い出がある。その後もビールや日本酒、焼酎やワイン、ウイスキーなど色々なお酒を試してきたけど、特別お酒に強いわけではないわたしにはカクテルやサワー系が精一杯らしい。けど、問題は味ではなく飲む環境にもある。ひとりで飲む時と誰かと飲む時は、本当に少しだけど味が違う気さえしてしまうのだ。そんな不思議な酒というものに興味が湧く気持ちは痛いほど分かる。けれど犬飼くんはまだ高校生だし、ボーダー隊員でもあるし、健康の事を考えても飲ませるワケにはいかないのだ。
「ダメったらダメ」
「えー」
「よし、アイスでも食べよう!」
意識を酒から離れさせようと、先ほど買ったアイスを最終手段として出すことに決めた。アイスを嫌いな人間はあまりいないだろうという勝手な先入観が先走ってるのは否めない。然し、勢い良く立ち上がると酔いが回ったせいか、若干フラついてしまった。自宅なので然程問題はないけど、犬飼くんに急に腕を思いっきり引っ張られソファーに腰を下ろすことになった。突然の至近距離に脈がドクドクと波うつ音が耳を支配する。けれど、アルコールが体内を循環して心臓が少し慌ただしいだけかもしれない。予想していなかった犬飼くんの行動に目を見開いていると、犬飼くんの手がわたしの頬をふんわりとつつむ。ひんやりと感じるのはわたしの身体が熱いからに違いない。何もかもを見透かすような犬飼くんの目がわたしの心臓を容易く射る。自分の目が熱情に侵されていることくらい分かってる。ふ、と笑った犬飼くんの表情が脳髄を震わせゆっくりと重ねられたくちびるは、アルコールなんかよりわたしの細胞を内側から溶かしていく。
「じゃあ、今はこれで我慢しとく」
アルコールよりもソファーに沈む夜に、朝はきっといつもよりゆっくりと訪れてくれるはずだ。