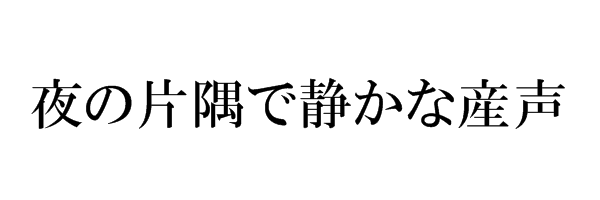「俺はさ、人が書く字にも色々な情報が隠されていると思うんだよね」
後ろから気配もなく現れては、人が書いている紙を取り上げビリビリと2つに破く。私が存在出来る唯一の世界が破られているようで、ひどく不愉快だ。せっかく書いた文字たちの泣き叫ぶ音が聞こえてくる。音をあまり持たないこの部屋で生まれるその不協和音はやたらと響き耳に残っては鬱陶しい。彼には何も聞こえないのだろうか。聞こえていたらあんなに笑顔で破いたりはしないだろう。
「そうですか」
「よく言うだろ、字の特徴が人を表すってさ」
「興味ありません」
「の字ってキレイだよね。でも整い過ぎて隙が無いっていうか、なんだか窮屈そうだ」
「別に臨也さんにどう思われようと構いません」
「でもこんなにキレイな字なんだから勿体無いよ」
彼の言う「窮屈」という表現はあながち間違ってはいない。実際わたしは今、彼によってこの小さな世界に閉じ込められている。狭い箱の中を浮遊して、見えない壁に衝突しては傷だけ負って楽になることは永遠に無い。そんな感覚を何度も何度も繰り返しているようにさえ感じる。それでも、居心地は思ったより悪くないから不思議だ。
「いい加減、遺書なんて書くのやめたら?」
毎日ご丁寧に白い紙と高そうな万年筆を用意してくれているくせに、一体何を言っているのだろう。
この世に別れを告げようと、高層ビルがそびえたつ西新宿の公園で夜中にひとり佇んでいたところを臨也さんに話しかけられたのがすべての始まり。既に「生」に未練も無かったので、特に何の感情も抱かず彼に連れて来られたのはこの部屋。そして、彼は私を此処に住まわすようになった。理由は一切不明。初めて出会った時に人がどうのこうの、周りに誰もいないのにまるで演説でもするかのように自分に酔いしれながら論を語っていたけれど、興味が無いのでただただ聞き流していた。わたしは彼のことを何も知らなかった。けれど、短い時間ながらも生きている時間のほとんどを同じ空間で過ごすという密な時間のおかげで、折原臨也という人間がどういう人間なのかだんだんと理解出来てきた。然し、だからこそ彼が何故わたしに固執するのか分からなかった。胡散臭い笑みの仮面をはりつけてる男のロジカルな思考なんて、理解したくもないけれど。
「臨也さんこそ、いい加減わたしの遺書破るのやめたらどうですか?」
「やめたら君、死んじゃうだろ?」
「でも、わたしが遺書を書かなくなったら面白くないんでしょう?」
「それはどうかな?」
「疑問に疑問で返すのやめてください」
「おかしなこと言うね。から始めたんじゃないか」
それでも、何となく彼のことを理解してしまう自分がいる。きっと彼にとってわたしは玩具か実験のマウスのようなものだろう。わたしが遺書を書くことをやめたら、彼がわたしという存在を殺すかもしれない。そして、わたしが遺書を書く理由が此処に隠されていることをわたしは知っている。最早今となっては生きることをやめるために書いているわけでは無い。勿論、彼に殺されないために書いているわけでも無い。ただひとつ言えることは、遺書を書くことをやめるということに、ひどく恐怖を抱くようになってしまったのだ。世界に別れを告げるための、文字が書かれたただの紙切れが命を繋ぐ。これが「生きる」ということなのだろうか。
「そんなものより、そろそろ俺への恋文くらい書いて欲しいところだよ」
「死んでも書きません」
何が面白いのかケラケラと笑う彼を見て、この笑みは仮面では無く素顔だと分かった。そういえば、私が最後に声を上げて笑ったのはいつだっただろう。結局、思い出せなかった。
紙が無くなってしまったので、特にやるべきことがなくなったわたしは料理を作ることにした。料理を作るのはわたしの役目でもある。住まわせてくれと頼んだつもりはないけれど、何不自由なく生きていることに罪悪感を感じて、せめて人のため誰かのため彼のために何かしたいという気持ちはあった。矛盾している。いっそのこと毒でも盛って彼を殺してわたしもこの世界とさよならすれば良いのではと思ったこともあるが、それは出来なかった。逆に此処でわたしの生涯を無理矢理終えてしまえば良いのではとも思ったが、それも出来なかった。きっと、わたしがあの世へ行ったら彼もあの世まで追いかけてきそうだから。確信は何も無いけれど、予感は心の奥そこで静かに存在していた。
「可愛くないって言われるだろう?」
「そうですね」
「それで良いんだよ」
結局、わたしは今もまだこの世に存在している。果たしてそれがわたしたちふたりにとって正しい結末なのかは分からないけれど、遺書の文字のインクがだんだんと薄くなっていくような気がした。純白を気取る紙と艶やかな黒が繰り広げるモノクロだった世界の中で、色彩を持つ新しい世界が描かれる日も来るのだろうか。
「のことは俺だけが可愛いって思ってればさ」
ああ、胡散臭い。この曖昧な世界が輪郭を持つその日まで、わたしは遺書を書くことをやめないだろう。