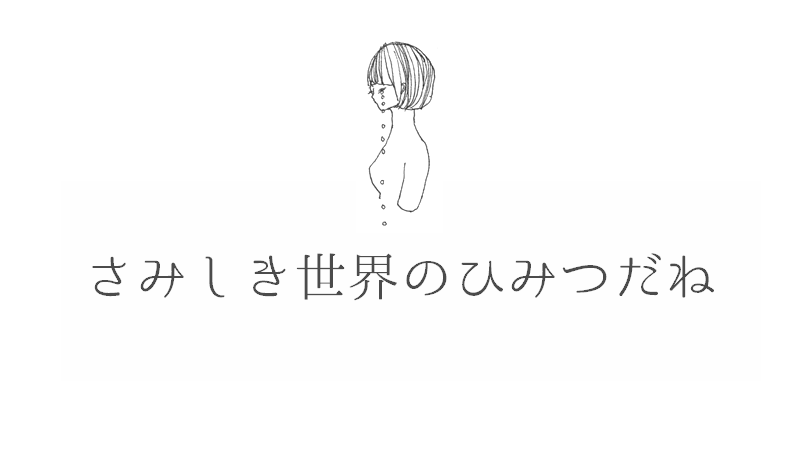雨が池袋の街を濡らしている。サンシャイン前の交差点で信号待ちをしていると、色彩鮮やかな傘が街を埋めるように存在しているのが視界に入った。灰色の雲に覆われているのに、カラフルな傘たちはちっとも憂鬱そうじゃない。そんな光景を見て、嫉妬と羨望が入り交じったよく分からない感情に飲み込まれそうになったのは、きっとひとり白黒の世界に置いてけぼりにされたみたいに寂しいからだ。人々はみんな行き先や目的に向かって歩いていると言うのに、わたしは一体どのくらいここに立ち尽くすつもりだろう。何度も見送った信号は相変わらず無機質で、ただ「止まれ」と「進め」しか教えてくれないなんてちょっと残酷だと思った。
「あれ、珍しいね」
重々しい空とは相反した軽い声は聞き覚えがある。相変わらず何色にも染まらない黒を全身に纏っていて、うっすら浮かぶ仮面みたいな胡散臭い笑顔が相変わらず好きじゃない。むかしはまだすこしまともだった気がするのに、いつからこんな風になってしまったんだろう。来神中学から一緒だったこの男、折原臨也とは同級生でもあり付き合っていたこともあるという因縁だ。付き合っていたと言っても世間みたいなドキドキワクワクな青春を描いたような関係ではなく、恋人同士と言えるのかどうかも怪しいくらい淡々とした付き合いだった。それでも恋人同士がするようなことは一通りやった気がする。あ、手は繋いだことないけど。
「何が?」
「が池袋にいるなんて」
「わたしだってたまにくらい池袋に来るよ」
大学卒業後、メーカーに就職したわたしは実家のある池袋の街を出て代々木に引っ越した。都内、ましてや山手線で5つくらいの近場だ。利便性からか池袋に残っている地元の友人も多く、たまの休みには実家に帰ったり友人と会うために頻繁にこの街を訪れる。その度に、この池袋という街は相変わらず不安定で混沌としながらも刺激に満ち溢れた不思議な場所だと地元ながらに毎回思わされる。そんな雰囲気を作ってるのはこの街にいる人々であり、きっと臨也が過去或いは現在、おそらく水面下で色々動いているであろう影響が色濃く存在しているからだと思う。
「てっきり静ちゃんに会いに来たんだと思った」
自分でも分かるくらい怪訝な表情を浮かべてしまった。正反対とでも言うかのように臨也は満面の笑みだ。わたしが池袋に戻ってくる最大の理由は静雄だった。臨也と別れてしばらくしたあと、静雄と付き合ったわたしは今までの恋愛が嘘みたいに思えるほどしあわせを感じた。臨也の時には一切感じなかったときめきや不安、心配。ぜんぶ静雄が大事だから思うことだ。静雄と付き合って何年経つだろうか。何も言わなくてもお互いがお互いのことを理解出来てるくらいには多分長い。けど、この一週間は連絡が一切取れていない。マメな方ではないけど、電波も通じないみたいでここまで応答がないのは初めてだ。この街では臨也と並ぶくらい静雄も有名で、今までもよく事件に巻き込まれたりしてきた。何か変なことに巻き込まれてなければと、池袋を訪れてみたのだ。
「まあでも会えないと思うけど」
「…何か知ってるの?」
「タダで教えてあげるほど俺がやさしいと思う?君のその甘い考えは相変わらずのようだね」
「じゃあ自分で調べるから良い」
そうは言ったものの、すでに友人知人に聞いてはみたが手がかりは何ひとつ掴めていない。街の裏事情に詳しそうなサイモンさんたちにも聞いてみたけど彼らもここ最近は静雄の姿を見ていないようだ。臨也は多分、というか十中八九なにかを知っている。むしろ臨也自身が多少関係しているのではないだろうかと疑ってしまう。このふたりのバカみたいな犬猿の仲はむかしから何ひとつ変わってないから。
「相変わらず可愛くないなあ」
「臨也にそんなこと言われたくない」
「ここで涙のひとつでも見せてくれれば俺だって何か教えたかもしれないよ?」
「…誰のせいで泣けなくなったと思ってるの?」
「え、まさか俺のせいとか言う?」
「付き合ってた時に臨也が「泣いてる女の思考回路ってあまり理解したくないんだよね」みたいなこと言うから泣けなくなっちゃったんじゃん」
確か高校生の頃に言われた気がする。あの時は確か、臨也との関係に急に不安を感じて生理現象みたいにポロポロと涙が出たんだっけ。そしたら臨也は慌てもせず嘲笑いながらわたしに残酷なセリフを吐き捨てた。呆気に取られて何も言い返すことが出来なかったのを覚えている。わたしが泣いたのはあれが最後。以来、映画を見て感動しても上司に理不尽な怒られ方をしても、ひとりでも泣けなくなってしまった。
「ああ、言ったかもね」
「人にトラウマ作っておいてその程度?」
「っていうか何でいま泣きそうなの?俺が泣かしたみたいじゃないか」
臨也が泣かしたんだよ!とは言えない。わたしが泣きそうな理由のすべてが臨也というわけじゃないからだ。…半分以上はそうだけど。馴染みのある人間と会って、すこし気が緩んでしまったのかもしれない。朝から静雄を探すために歩きまわって少し疲れた。これ以上先どこを探したら良いか分からなくて、進む道が分からなくなってしまったから。
「まだ泣いてない!」
「…ついてくるかい?」
どこに、という疑問符を投げかけると彼はくちびるの両端をゆっくり上げるだけで答えを教えてはくれなかった。
信号が青に変わると人々の波のように動き始める。付き合っていた時は手なんて繋いだことないのに、なんで今になってこの男と手を繋いでいるんだろう。引っ張られていると言ったほうが正しいかもしれないけど。臨也の歩幅が思ったより広いからか、わたしは白線をステップするみたいに急ぎ足でついていく。さっきまでは自分の進むべき道が分からず、靴の裏とアスファルトが接着剤でくっついたみたいに足が動かなかったのに、嘘みたいに軽く動いた。認めたくないけど、この男はわたしが迷っていると道標を作ってくれる。毎回それが正しい道だったのか間違った道だったのかはわからないけど。
赤に変わる前に渡り切ると、臨也はタクシーを呼んで「新宿まで」と言った。車内に乗り込むと、窓ガラスに無数の雫がついていて池袋の街がぼやけて見える。何で新宿なんだろうと思っていると、わたしの心を読んだみたいに臨也が「今、事務所兼自宅が新宿にあるんだ」と言った。新宿まで行くなら、わたしは隣の代々木だからどうせなら代々木まで送ってくれないかな、なんて脳天気なことを言おうとしたら臨也の細くて長い指が伸びてきて、わたしの長い髪を耳にかけた。耳朶から頬、首へ、肌に臨也の温度が広がる。すこしでも動いたらこのまま首を絞められて殺されてしまうんじゃないだろうかという緊張感が身体の全身に走る。
「思う存分、泣けば良いさ」
悪魔が囁くみたいに吐かれたそのセリフがわたしの心臓を揺さぶった。人前で泣かれることを避けたかったのか、それとも泣けなくなったわたしを思ってくれての親切心だろうか。いや、違う。きっと答えはそのどちらでもない。
「後悔しても知らないけどね」
しばらくの間を置いて臨也は「静ちゃんのことだけどさ」と淡々と切り出した。そこにはさっきまでの笑顔はない。胡散臭い笑顔の臨也は好きじゃないけど、今みたいに表情を殺してるような臨也も好きじゃない。だって、そういう時の臨也はたいてい本音を言ってる気がするから。
「知らない方が良いこともあるよ」
「…そうかな。大切な人のことは知りたいよ」
「も知られたくないことが出来たら分かるさ…きっとね」
あ、笑ってる。それと同時にわたしの血液がドクドクと警鐘を鳴らすみたいにうるさくて熱い。
もしかしたらわたしは道を間違えたのかもしれない。本当はもう一本道があったはずなのに、臨也について来てしまった。けど、今はもう引き返したいとも思わない。雨が降るこの街から抜け出して、すこし休もう。
ごめんね、静雄。すこし雨宿りしたら、すぐに戻るから。