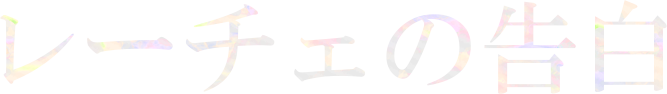
大学のキャンパス内にいくつも連続して立ち並ぶ自販機。これだけ並んでいるとまるでロボットの集団のようにも思えてきた。傍にはカラフルなソファーやローテーブルがあったりと、学生たちの憩いの場になっている。今の時間帯はあちこちの教室で講義中なため、ほとんど人がいない。講義と講義の間が空いてしまい何をしようか考えるけれど、この時間を使って勉強しようと思うほど、今のわたしにやる気はない。とりあえず自販機の前で悩むこと約3分。カップラーメンが作れるほどの時間を要して辿り着いた答えに向かい、一直線にボタンを押す。然し、残念ながら標的はひとつズレてしまったようだ。本当は隣にあるあったかいカフェオレが飲みたかったのに、よりによって「無糖」と目立つように書かれたホットのブラックコーヒー。苦い味が苦手なわたしの今の顔は、きっとこの世の終わりにでも遭遇したかのような表情を浮かべているに違いない。仕方がないので、久々に伸ばした爪で缶のプルタブを開ける。せっかく塗ったミルキーピンクのネイルが惨めに剥がれそう。爪なんて伸ばすんじゃなかった、と思うほど蓋を開けるだけの行為に躊躇する。カッカッと引っ掛かるような音を2回程立てたところで、運良く知り合いが通り掛かった。
「あ!風間くん、ちょうど良いところに」
「なんだ、」
「これ、あけて」
さっきまで同じ講義を受けていた風間くんと偶々目が合ったので挨拶がてらにお願いひとつ。風間くんは嫌な顔ひとつせずにわたしから缶コーヒーを受け取ると、あっさりプルタブを開けてくれた。温かさを表現する白い湯気が上がると同時に、鼻孔をくすぐる大人の香りがほのかに漂う。けど、ブラックコーヒー独特の他を寄せつけないような深い色は少し苦手だった。まるでその深くて重い色に塗り潰されてしまうような、飲み込まれてしまうような、そんな馬鹿げたイメージを良い年して思っている。
「ほら」と無表情で差し出され「ありがとう」と答えると、彼も何か飲みに来たのだろうか。自販機の前で考えるように立ち止まっている。
「今日はもう終わり?」
「ああ」
「良いなー、わたしも早く帰りたい」
「お前は補習だろ」
「よくご存知で」
「目の前の事に集中せずに考え事ばかりしているからそうなるんだ」
誤魔化しようがない程の真実にアイビスで心臓を貫かれたような程の衝撃だ。もう少しオブラートに包んで欲しかった。いや、きっとわたしの為を思って彼は必要最低限の言葉で事実を述べたのだろう。顔が少しばかり歪んでしまったのは、飲みたくもないのに飲んでしまったこの苦いブラックコーヒーのせいだということにして欲しい。
「鋭い」
「お前は分かりやすいからな。普段の様子を見ていれば分かる」
ここ最近の不調。個人ランクの順位も落とし始め、訓練は失敗の連続。集中していないため身にならない特訓を夜遅くまで一人でやり、大学の授業には遅刻する。おまけに講義中は持ってきているバッグを枕代わりに安眠。もちろん試験なんて理解出来るはずもなく、既に単位はひとつ落とした。ネイバーを消滅させずに自分の単位を消滅させてしまうなんて全く馬鹿げている。そんな悪循環の渦の中で溺れて、呼吸が上手く出来ないような感覚になって、なんだか心がいつまで経っても落ち着かない。
「だってさ、不安なんだもん」
21歳。ふつうの女の子だったらキャンパスライフを楽しみつつ、自分の将来を設計したり、その目的に向かって努力し始めたり。留学だったり就職活動だったり、ボランティアだって、なんだってそう。なのに自分は何もすることがなく、何も出来ることがない。だからせめてボーダーとして人のため世のために頑張らなくちゃと思うのに空回り。このまま戦争は終わらないのかな?とかそういう世界の平和に関わる大きなことも勿論そうだけど、単純にしあわせになれるのかな?とか何才までボーダーにいるのかな?とか普通の企業には就職出来るのかな?とか結婚出来るのかな?とか朝ごはんにお味噌汁を作って誰かとゆっくり一緒に飲めるのかな?とかそういう普通なことだって考えてしまう。でも、それがすごい遠い道のよう。特別なしあわせなんて望んでるわけじゃなくて、普通の平凡な、日常のことなのに。
「これから先、将来とか未来の事とかさ」
けど、当然今のわたしなんかが答えを出せるわけもなく、ただただ悩んで悩んで悩んでるだけ。心の中のぐるぐるを紙に書いては、ぐしゃぐしゃに丸めてゴミ箱に投げ込むけど、ことごとく外れて余計泣きたくなるような、そんな感じ。そういえば前に米屋くんに「さん、最近溜息ばっかじゃないっスか」と言われた気がする。出水くんには「負のオーラ出まくってますよ〜」とか笑いながら軽く言われた気がする。菊地原くんには「そういうのうざいんで近寄らないで下さい」とまで言われた。みんなヒドイな。目の前のことに集中出来ないから、未来のことなんてもっと分からないだけなのに。
「考え過ぎて頭パーンなるから何も考えたくない」
「人は考えることをやめると成長が止まるぞ」
「でも周りに迷惑ばかり掛けちゃうし…こんな情けない自分が嫌」
苦いブラックコーヒーの缶を握り締めるけど、凹ませることも出来ない。誰かに「お前に何かを変えることなど出来ない」と言われているような気がして、憤りを覚えるどころか自分自身に呆れが生まれる。なるほど、これが俗に言うネガティブの海か。必死にもがいて泳いで抗うしかない。せめて自分にもう少し自信が持てたら、せめてもう少し自分を好きになれたら少しは好転するだろうか。ああ、太刀川くんなんか自分のことすごい好きそう。どうすれば自分を好きになれるか聞いてみようかな。
「馬鹿だな」
「知ってる」
「だが、俺はそういう馬鹿な人間は嫌いじゃない」
「え、意外。絶対説教されると思ったのに」
まさか、あの自分にも他人にも厳しい風間くんからそんな言葉が出るとは。「それから、」と続くであろう言葉を風間くんは一度飲み込み、は自販機のボタンを押した。ガコン。その音がやたらとわたしの脳に響き渡る。ただ自販機から飲み物が出てくるだけの音なのに、まるで何かが誕生したかのような覚醒を迎えた気がする。風間くんは結局何を買ったのだろう。
「やる」
「え…あ、カフェオレだ」
「間違えて買った」
「良いの?ありがとう!うれしー」
正しくわたしが飲みたかったあたたかいカフェオレ!なんだ、わたしってこんな単純なことですぐ元気になれるんだ。なんだ、わたしってまだ、どうにでもなれる。
おまけに風間くんが譲ってくれたカフェオレは、プルタブがキレイに開けてあった。ジェントルマン。カフェオレのやさしい香りは穏やかさを与えてくれるような気がして、別に何かが変わったわけじゃないのに自分の中の世界が少しだけ明るくなったような気がした。
「ついでだからもうひとつ言っておくが、」
「うん」
「お前が嫌いなお前を、好きだという人間もいることを忘れるな」
そう言って微笑を浮かばせながらわたしのブラックコーヒーを持って去っていった風間くんの後ろ姿は、わたしとあまり変わらない身長のくせにやたらと大きく思えて。今まで見ていた景色がなんだか少しだけ違って見える。
ゴクリ。わたしが飲みたかったカフェオレは、予想以上に甘くてやさしい味がした。