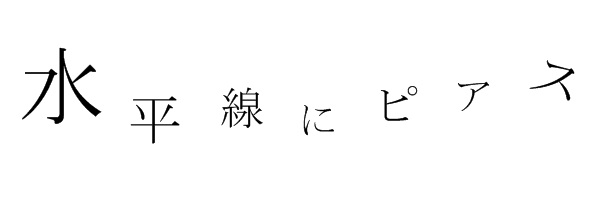海沿いの道はひどく寒い。それでも手袋をせずに肌を海風にさらしているのは、きっと無意識のうちに人肌を欲しているという願望の表れなのだろう。波の音に耳を澄ませると、この世界には他に音が存在しないのではないかと思うくらい静寂を感じる。雲で覆われた灰色の空に白い息が浸透して消えていくのをぼんやり眺めながら、半歩前を歩く彼にゆっくりと着いて行く。
いつからだろう、彼の隣を歩くのに躊躇いを覚えるようになったのは。いつからだろう、自分から手を重ねて指を絡ませることが出来なくなったのは。結局この指先は未だ凍てついたまま、ポケットの中でひっそりと孤独に震える。
「久し振りだね」
「そうじゃのう」
顔は見えず、海と彼の後ろ姿と彼の吐く息だけが今の私に映る唯一の世界。
彼とこうしてゆっくり会うのは約2ヶ月ぶりだろうか。遠距離恋愛などでは無い。会おうと思えば会える程度の距離にお互い在る。けれども2ヶ月という空白の期間が生まれてしまったのは何故か。それは自問自答するまでもなく単純明快。「忙しいから会えない」、街のコンビニみたいにどこにでもありふれている理由だ。そんな真実か嘘か誰にも分からない理由で生じた空白を埋めるには、同じくらいの時が必要だと思ってしまうあたりが少し虚しい。彼が忙しい時もあれば、私の都合が合わない時もある。すれ違いとはこういう事を言うのかと生まれて初めて知った。
「って、恋人同士がする会話じゃないよね」
今までにも会えない日が続くことは幾度もあった。その度に一抹の不安が私を少しずつ蝕む。忙しいなんて言い訳ではないだろうか、なんて猜疑心を始めとした抱きたくない感情を抱いてしまったり、そんな自分が情けなくて自己嫌悪をする日も少なくない。そして、その度に浮かぶ「別れ」の2文字。不意に生まれるその文字に、自分自身が一番怯えた。別れを切りだされる恐怖と、別れを切り出さなければいけない恐怖。もしかしたら、彼自身のくちびるではなく、私のくちびるから「別れ」の言葉を紡がせたいのかもしれない。そんな負の想像ばかりが連鎖して、勝手に悩むという無駄な行為を何回も繰り返した。
彼が寒がりなのは相変わらずのようだ。背中を丸めて両手をポケットに入れている姿に自分の意思とは関係無く涙が零れそうになる。それはきっと、海風のせいだということにしておこう。
−ねぇ仁王くん。私、少しだけ髪切ったんだよ?カラーリングだって季節に合わせてツートーンも落とした。今日だって別れるかもしれないって思っているのに、涙が出るかもしれないって予期しているのに、マスカラだってちゃんと塗っている。前ばかり見てて気づかないのかもしれないけれど。
「…仁王くん、あのさ」
数分の沈黙を遮るように呟いた私の声掛けに、彼は足を止めた。まさか止まると予想していなかった私は、慌てて脳から足へと伝令を送り自身の足を止める。意図しなくとも、ちょうど彼の隣に並ぶことになった。
此方を見る彼の動きがスローモーションのように感じられて、背景の海に溶け込みそうな銀髪を風に靡かせている。思わず息を飲んだのは、形容し難い程の彼の魅力に心を奪われたからか、今日会った時にも見た筈の彼の顔を久々に見たような気がして胸の鼓動が加速したからか。ああ、どちらも意味は同じだ。
「髪、」
「え?」
「に似合っとるの」
伸びてきた彼の大きい手は、私の髪をひと撫でするとやがて頬に触れた。彼の指先も私と同じでひどく冷たい。その冷たさを感じた刹那、閉じていた瞼が開くような、何かが覚醒するような感覚を覚えた。そして見えたのは彼の笑み。口角が少しだけ上がるその笑みは、今まで数え切れないくらい何度も見てきた。瞬きをすることさえも忘れ、思考を巡らせる暇もなく粉雪みたいなキスがくちびるにやさしく降り落ちる。
「…言わんし、言わせんぜよ」
いつの間にか繋がれた指はやはり冷たいが、血が通っている事は分かる程度の感覚を持っている。この世界よりも輪郭が鮮明な彼の笑みは、全てを悟っているようだ。
雪がとけるように何度でもやさしくやってくる春が、私にとって残酷と幸せの表裏一体だということも彼は知っているのだろうか。