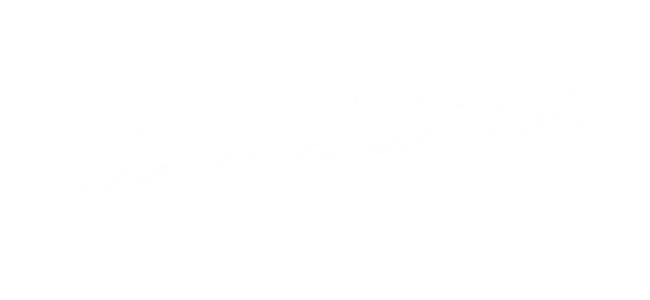オレンジ色の街灯がミッドナイトブルーの空に静かに映える中、財布とスマホだけを持って、冒険にでも行くみたいな気分で家をこっそり出た。Tシャツにデニムのショートパンツという何ともラフな服装で海沿いを歩く。ぺたんこのサンダルでペタペタと歩いて、信号を渡ってコンビニに入ってアイスを買う。特別好きなわけじゃないけど、たまに無性に食べたくなるから不思議だ。コンビニを出て横断歩道を渡った先にある遊歩道のベンチでひと休み。昼は登校中の生徒や出勤のサラリーマン、散歩してるおじいさんやランニングしてる人などたくさんいるのが嘘みたいに静かだ。海は何も映さないくらい真っ暗だけど、国道134号を走る車のテールランプが時々通り過ぎて行くのでそんなに怖くはない。
「そんな格好でこんな時間にうろつくなんて危ないの」
制服のワイシャツが長袖から半袖になり始めた初夏の頃、わたしたちの逢瀬は始まった。初めてキスした海の目の前のこの場所で、気づいたら定期的に会うようになっていた。きっかけなんて覚えてないし、毎回約束した記憶もない。事実、今日だって別に約束したわけじゃない。けれど、初めてここで会ったあの日、わたしはアイスを食べながらボーっとしていて、恋人でもないのに当たり前のようにキスしたことは今でも鮮明に覚えてる。
「襲ってくる物好きなんていないよ」
「ここにおるじゃろ」
頬に触れられた手が冷たくて心地良い。ふっと笑ったあとにわたしのくちびるをいつもみたいに攫っていく。すこし生温かい潮風が肌を撫で波の音が耳に響く。今みたいにキスをしたり指を絡ませて手を繋いだり。まるで恋人みたいな感覚に陥りそうになる。もうひとりの自分が別の世界にいるかのように思うけど、それは今だけ。朝が訪れれば、今起きたことなんてまるで無かったかのように過ごす。
「冷たか」
「アイス食べたばっかだから」
普段、太陽を浴びながら恋人と手を繋いで歩くこの海沿いの道で、月に見つからないように別の人とくちびるを重ねる。まるでどこかの恋愛小説に出て来そうな話だ。いけないことだと頭では理解している。けれど、こうして仁王くんといっしょにいる時間には、他では決して得られない安堵感が確かに存在していて、それを手放せなくなってしまった。それを恋だと言われれば頷くしかない。それでも、仁王くんと結ばれることは一切考えたことがなかった。今の恋人と離れる覚悟は無いからだ。最低な女と言われるなら、別にそれでも良い。
「…前より表情明るくなったの」
「何それ」
「初めてここで見たときは能面みたいな顔しとったのに」
「恥ずかしいから言わないで」
きっと、わたしが何でそんな顔をしていたのかお見通しだったんだと思う。付き合っている恋人が忙し過ぎて、会う時間もあまり取れずにすれ違いが続く日々。どこにでもありふれたよくある話。けど、当人にとってはそうじゃない。虚しさに襲われて海をぼんやり眺めていたところに仁王くんとたまたまここで出会った。当時のことを揶揄うみたいに言うから、少しふてくされていると、手の甲にキスを落とされた。今までそんなことされたことがなくて、びっくりして仁王くんを見ると、その眼に吸い込まれて、瞬きすることも呼吸することも忘れるくらい動けなくなってしまった。時間が止まるってきっとこういうことなのかもしれないって錯覚するほど。寂寞を孕んだ双眸から逃れることが出来ず、くちびるが触れるだけのキスからは虚無感しか生まれなかった。
「部活、引退したぜよ」
「…うん」
「夏も終わる」
「うん…分かってる」
夏の終わりってこんなに明確に分かるものだったっけ、なんて必死で馬鹿みたいなことを思ってはみるものの、胸が苦しい。下を向いてしまったら、出てはいけないものが溢れてしまう気がして、口を開いてしまったら言ってはいけない言葉を言ってしまいそうな気がして、結局真っ直ぐに仁王くんの顔を見て黙ってるだけしか出来ない。さっきの言葉は、部活を引退したからいっしょに過ごす時間が増えるという意味じゃない。きっと真逆の意味だ。
「幸村に、コンビニの帰りに見掛けたって連絡しとくからの」
多分、今後仁王くんと話すことはきっと無い。クラスも違うし、学校でもあまりすれ違ったことは無い。きっとこの夏の出来事なんて無かったみたいにお互い生きていく。アバンチュールと言われてしまえばそれでおしまいだけど、そんな簡単な言葉で終われるほど、わたしは大人じゃない。
「あいつといっしょに帰りんしゃい」
ちいさく頷くと、頭に仁王くんの手が乗せられた。あー、これ好きだったな。仁王くんに頭撫でられるの。なんて、感傷に浸ってみたりするものの、終わりの時間が近づいていると思うと心ここにあらずの状態になってしまう。わたしだけこんな気持ちになってしまうのもまた苦しい。仁王くんにとって、わたしは数多くいる女に過ぎなかったのかもしれないけど、わたしにとっては間違いなく、ひとりの男の人だった。
「もう、さみしくないじゃろ?」
「別にさみしかったわけじゃないもん」
「…俺がそう、思いたいんじゃ」
「それって、」
「をしあわせに出来るのは幸村だけぜよ」
精市との付き合いは比較的安定していて、もちろん病気だとか部活の忙しさとかで心配になったり不安になったりしたことはあるけど、胸が苦しくなるような息さえする時間も煩わしいと思うほどいっしょにいたいと思う事はなかった。わたしは多分、一生、彼との一瞬のこの恋を忘れられずに、他の人と生きていく。
「けど、をかなしませることが出来るのは多分俺だけじゃの」
それで充分ぜよ、と耳元で囁かれたと同時にベンチに濃い染みが出来る。そう、たったそれだけ。去っていく後ろ姿の仁王くんを一瞥もせず、わたしは目の前のぼやけた輪郭の海を眺める。大丈夫、この恋は朝が来たらそっと終わるはずだから。