|
一緒に出掛ける一時間前。彼女の瞳から俺の姿が消えてしまう寂しい時間がやってくる。 休日の午前、朝起きて天気が良ければどこかへランチを食べに行こうと彼女が言う。「こんな晴れた日にテラスの席でランチ食べたら絶対美味しいよ」と彼女がまだ起きたばかりでも目を輝かせて言うものだから、つい微笑ましくなってしまい「そうだね」と頷いてキスをしたくなる。彼女と部屋で過ごすのは楽しい。まるで二人だけの世界に浸っているかのように感じられるからだ。でも、彼女と外に出掛けて過ごすのも楽しい。彼女を隣にして街を歩くだけで、一歩一歩が輝きを纏う。要は彼女と過ごせるならどんな場所でも嬉しいということ。しかし、出掛けるとなると俺を全く相手にしてくれない時間が生まれてしまうのだ。 「え、辰也くんもう準備終わったの?」 「うん、 はゆっくりで良いよ」 外へ出掛けるとなると、彼女は必ず化粧をする。男からすればしなくても良いのではないかと思うことも多いが、どうもそういうわけにはいかないらしい。しっかりと化粧をして華やかな舞台で映えるほど美しい時もあれば、ファンデーションだけ、グロスだけという素朴に近いときもある。どちらにしろ、そういう意識を持つことは女性ならではの素敵な一面だと思う。どちらも美しい、どちらも可愛い。素朴な彼女も華やかに彩られた彼女も、どちらも魅力的で仕方ない。どちらも彼女のありのままの姿と言えるだろう。おまけにその違いを感じられるのは自分だけだと思うと、それもまた嬉しい。優越感に浸れる瞬間でもあるのだ。けれど申し訳ないことに、俺は彼女が化粧をする時間がそんなに好きではなかったりする。 「ねぇ 、今日はどこのお店行こうか?」 「んー」 彼女は鏡に夢中になってしまって、こちらを全く意識してくれない。話し掛けてもいつも相槌を打つだけ。そんなところも可愛いのだが、少し物足りなくもある。もし、俺がその鏡の中に入ることが出来たら彼女は俺を見てくれるだろうか、なんて馬鹿なことを考えてしまった。さて、どうにかこの時間をもっと楽しく過ごせないだろうか、と彼女をじっと見つめてみる。そこであることに気づいた。 そう、彼女が化粧に集中している間は、どんなに彼女を見つめていても怒られないということだ。いつも 彼女が可愛くて無意識のうちに見つめていると、せっかくの可愛らしさを隠してしまうかのように顔を逸らされてしまったり「そんなに見ないで!」と言われてしまう。もちろん、そんなこと照れ隠しだってことくらい分かってはいるけれど、出来ることならやっぱりずっと見ていたいじゃないか。それに今思えばこんな無防備な姿も見せてくれるのは、彼女の素の部分を見れてるようで何だか楽しくて嬉しい。 「睫毛、化粧してないときの方が多く感じる」 「マスカラ塗るとくっつくしボリュームタイプじゃなくてロングタイプだからね」 あまり理解出来ない用語で返されたが、今回は化粧に関連した話だったからだろうか、相槌以外の答えが返ってきただけマシだろう。それに、やっぱり俺が至近距離で見つめていることには気づいていないようだ。睫毛をコーム上のブラシのようなものでせっせとじぐざぐに動かしている姿も、ふわふわとしたブラシで頬を色づけるその仕草も、ひとつひとつが愛らしい。 カメラを持っていたらその様子を写真に収めたいくらいだ。けど、そんなことをしたらまたもや「もう、何!」と彼女を苛立たせる気がしたので、大人しく自分のフィルムに焼き付けるだけにした。こうしてまた、彼女との何気ない日常のアルバムが増えていく。 「出来たー・・・って近!」 「どれどれ、よく見せて?」 今まで散々見てきたくせに、見せてだなんてよく言ったもんだと自分でも思う。しかし、横から彼女の顔を見るのと真正面から見るのでは全然違うのだ。彼女が鏡と化粧道具をしまったのを見計らって、先程までとはまた別の、魅力的なその表情を見ようとする。けれども、彼女はやっぱり「恥ずかしいからあんま見ないで」と言ってなかなかこちらを向いてくれない。しかし、もちろんそんなことは予想通りである。そんな意地悪をする彼女に、少しだけ意地悪をしたくなった。 「あれ、待って。目の下に何かついてる」 「え、何だろ」 「じっとして」 人というものは不思議なことがいくつもある。例えば、顔に何かついてると言われると鏡を見に行くことはせず、まずは教えてくれた人物に何がついているか、どこについているかを聞き返すことが多い。鞄の中やポケットの中に手鏡を持っていたとしても、まずは手探りで顔に触れるという人が多いように思う。おまけに顔についているものを取ってあげようと「じっとして」と言えば硬直したように顔も身体も動かさない人が多いだろう。彼女はその典型的なタイプである。睫毛が上がった瞳に、紅潮した頬、赤い唇、そして体を動かさないその姿は可愛らしくもキレイでもある人形のようにも思えた。 「だーめ、じっとしてて」 「ほ、本当に何かついてる?」 「信用ないな」 「こういう時の辰也くんは信用ない」 そこまでハッキリ言われてしまうと寂しい気もするが、ある意味自分のことをよく理解してくれていると思えば、そんなことでさえ微笑ましい。なんて、惚気も良いところだろうと自分でも思ってしまう。でも、それでも良い。こうして彼女の近くで彼女の柔らかい肌に触れられるのだから。おまけにそのおかげで彼女の顔もよく見れる。目の下、と目の近くだから気になるのだろうか。瞬きを何回か繰り返しす彼女の上目遣いに、仕掛けたこちらの胸の鼓動が激しくなってしまった。 「目閉じて」 彼女がすっと大人しく目を閉じれば、これまた絶好の機会である。完璧に化粧を纏った彼女の睫毛は頬に影を作り、瞼にはキレイなグラデーション。頬には自然な赤ピンクが色づいており、唇は何とも可愛らしくぷっくりとつやつやしている。こんな可愛らしい顔を目の前にして、何もしない男がいるなら是非ともお目にかかりたいくらいだ。いや、可愛い過ぎて何も出来ないのなら賛同するが。 「ほ、本当についてる?」 目を閉じているせいか、少し恐怖心を感じているようだ。睫毛が少し震えているのが見ていて微笑ましい。忠実に俺の言うことを聞いて、目を開けないのは純粋な彼女らしいと言えば彼女らしいと言えるだろう。もう少し楽しんでいたいところではあるが、これ以上やっていると流石に不信に思われそうなので仕方ない。 「はい、睫毛」 「え・・・あ、本当だ」 「嘘だと思った?」 「え!?」 「何かされると思ったって顔してる」 「う、うそ!そ・・・そんなこと」 偶然彼女の目の下に潜んだ睫毛に感謝しなければ。女は誤魔化すのが下手というか、すぐ表情に出る。自分とは違うそんな素直な部分も彼女に惹かれた理由のひとつかもしれない。それにとてもからかい甲斐がある。図星なことを指摘されて慌てているところも可愛いし、時にはムキになって否定しようとしているけれど、それが逆効果だと自分で分かってだんだんと口をもごもごと噤んでしまうところも愛しい。 「もしかしてキス、されると思った?」 彼女の髪を耳にかけて耳元で囁くと、それはもうすごい勢いで顔が紅潮していった。顔だけじゃなくて耳まで真っ赤だ。本当に分かりやすい。どうせ俺が「顔赤いよ」と言えば「これ、化粧だもん」とでも 言うつもりだろう。そんなこと言わせない。化粧で誤魔化せるほど、彼女の熱は穏やかじゃないはずだ。そんな絶対の自信を持てる、そして彼女をここまで動揺させることが出来るのは自分だからだと図々しくも自負しているからだ。そんなある意味素直な彼女を見れることが、また幸せでもある。 「じゃあ、期待に応えてあげないとな」 そのまま彼女の耳に指を滑らせれば身をよじり逃げるようにするので、とっさに腰を引き寄せる。細い腕を俺へ伸ばし、小さい手で俺の服をきゅと握るのを見て何となく優越感を覚えた。彼女は今、俺の腕の中にいるんだと改めて実感出来るからだ。掴まれているこの指が、手が、彼女から俺への信頼の証でもあるように感じられて嬉しくもなった。しかし、彼女の両手は何故か俺の唇を覆い隠してしまう 。 「ちゅーしちゃダメ!」 「・・・どうして?」 「辰也くんの唇にグロスついちゃうよ?」 彼女に対して「邪魔」とは言いたくないが、これではキスが出来ない。彼女の手首を掴むと「グロスってついたら結構ベトベトして大変なんだよ!」なんて言ってきた。どうしても化粧をし終えたばかりの今はキスをしたくないらしい。しかし、申し訳ないことに俺は今、彼女のその唇にキスをしたくて仕方ないのだ。グロスなんて気にしない。別に今だけに限ったことではないが、彼女のことになるとどうも我慢出来ないようだ。 「良いよ、そしたらにまたキスするから」 そのまま彼女の手の甲にちゅっと音を立てて唇を落とすと、腕をすごい勢いで引っ込めようとするので、逆にこちらに思い切り引き寄せた。そして彼女が「そういう問題じゃない」と言い切る前に唇を塞いでしまう。ああ、確かに朝キスした時とは違う感触だ。彼女はグロスが俺についてしまうのと同時に、自分の唇から落ちてしまうことも心配なのだろう。グロスだけじゃない、頬に塗られた胸をときめかせるようなピンクや、彼女の肌をさらに引き立てるファンデーション。俺が触れる度にそれら全てが気になって仕方ないようだ。だったらいっそのこと、そんなこと気にならなくなるくらい俺に夢中にさせてしまおうか。でも、彼女がきっと自分のためだけでなく俺のためにも頑張ってキレイになろうとしてくれている努力を無下にするわけにもいかない。そんなこと気にしなくても、その存在自体が愛おしくて仕方ないのに。けれども、素朴なままの彼女も美しくなろうと努力している彼女も、どちらも決して無理をしているわけではなく、彼女のありのままの姿なのだろう。 「好きだよ、 」 せめて愛を伝えることで分かってもらえるだろうか、その溢れ出る彼女自身の純粋な魅力を。 こうした何気ない日常でさえ楽しくて幸せを感じることが出来るのは彼女のおかげである。彼女がありのままの姿を見せてくれるので、俺もそのままの姿を見せられる。唯一、彼女の前でだけは本当の自分でいることが出来る気がする。だから、今日もこうして一緒に過ごせることに感謝の気持ちを込めて、再び彼女の唇に自分の唇を重ねた。 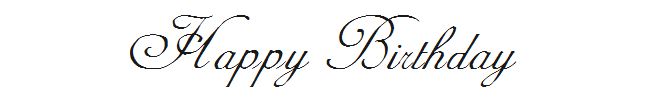 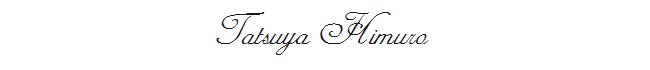 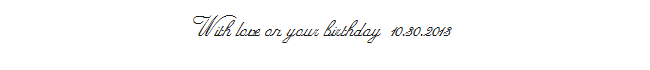 |