|
廊下側の一番前の席と窓際の一番後ろの席。対角線、教室の中で一番遠い距離。後ろを向いて彼を見ることが出来ないこの位置がもどかしくて仕方ない。きっとこの教室の中では誰よりも彼に一番近い存在なはずなのに。せめて逆だったら、私が後ろだったら彼を人知れずこっそり見つめることが出きるのに。例えば今日は少し疲れてそうだな、とか普段あまり見ることがないあくびをしようとしてるところだとか。忙しい彼だからせめて見つめていたいのに。 「た…氷室くん。隣のクラスの女の子が呼んでるよ」 「ありがとう」 彼と私が「恋人」という繋がりを持っていることは一部の人間しか知らない。恥ずかしいとか、そういうんじゃない。人気がある彼のファンに因縁をつけられるのがこわいわけでもない。けど、私からあまり広めたくない、広めないでほしいと申し出た。 それなのに、彼が女の子に告白されようとしている場面を見て少し不安になったり心配になってしまう自分はとてもワガママだと思う。この座席関係が何より悪い。廊下側の一番前にいる私は必然的に呼び出し係に任命される。もちろん呼び出しを頼まれるのは彼だけではない。けれど、このクラスで呼び出しが一番多いのは紛れもなく彼。しかもその8割が告白。どうして彼女の私が彼に告白をしようとする女の子の手助けをしなければいけないのか、なんて思ってしまうあたり本当に性格が悪い。そしてそれを誰にも言わずに心に秘めているだけの意気地なしなのだ。  そんなことがあった週の土曜日。私は選択の授業で午前中の土曜日だけ学校へ来た。この日はたまたまバスケ部も午前中のみの練習ということを聞いていたので、思い切って彼にどこか遊びに行きたいと告げてみた。バスケ部のみんなで練習が終わったあとにご飯を食べに行ったりするのかもしれない。彼が友人と過ごす時間を奪ってしまうのを分かっていながら、私は自分の欲望のままに願望を彼に告げた。彼はいつも通りの笑顔で良いよと言ってくれた。 学校から少し離れたところで待ち合わせをする。制服の私に合わせてわざわざ部活のジャージから制服に着替えてきてくれたのだろう。休日でも彼の制服姿を見ることが出来たことがちょっとだけ嬉しくて、でもそんなこと言える気分でもなくて、ただ黙って彼の隣を歩く。自分から一緒に帰りたいと言ったのに、だんまり。もう慣れてるつもりだったのに、この前彼が告白されたのを私は勝手に引きずっている。 「あ、」 「え?」 「ちょっとこっち来てごらん」 自分で勝手に作った気まずい沈黙を遮ってくれたのは、何かを発見したらしい彼だった。何気なく歩いていたショッピングモールの一階で大規模な大道芸をやっていたらしい。人も多く集まっており、3階にいた私たちはそれを吹き抜けから覗く。上からでもよく分かるほどのその華麗な技たちは、私を少しだけ夢中にさせてくれた。 彼はひとり分しかない前のスペースに私を優先させてくれると、そのまま私を囲うように手すりを掴んだ。今日一気に近くになった距離に少しだけ心臓が飛び跳ねる。まるで人前で抱きしめられてるみたい。 ディアボロのコマがこの3階まで飛んで来ると一気に盛り上がり、私もつい感嘆の声を漏らしてしまったり拍手をしてしまう。 「…少しは気分晴れた?」 「え?」 「元気ないみたいだったから」 「そんなこと、」 「まぁオレがそうさせちゃったのかもしれないけど」 困ったように笑う彼に胸が締めつけられそうになった。つい抱きつきたくなったくらい。けど、こんな人前でなんて抱きつけるわけがない。そんな葛藤に私が必死に我慢してると言うのに、彼はそれを気にもせず踏み込んでくる。彼の手が手すりから私の腰回りに移動してくるとぎゅっと抱きしめられた。おまけに彼のくちびるが本当に微かにだけど頬に触れた気がした。 「も、もう、またこんなところで」 「大丈夫だよ、みんなステージに夢中で誰も見てない」 私は一体何に迷って何を勝手に落ち込んでいたのだろう。彼はいつだって私のことを考えてくれる。それなのに、ひとりで落ち込んで、自分の駄目さを責めて不安になって。彼は一度も私を不安にさせたことなんてない。私が勝手に不安になってるだけなのに。 「が暗い顔になってる時に、いつもの可愛い笑顔に戻すことくらいさせてくれたって良いじゃないか」 そんな私にもこうやって優しさだとか、嬉しさをくれる。今までだって、私を叱ることはあっても怒ったことはない。私を責めるようなことはしないのだ。甘やかされていると、思う。彼は私より大人だから、甘やかせてくれる。そして、彼のそんな大人なところに甘えて自己嫌悪するのが私。でも、そんな私を否定せずに受け入れてくれるから、私は今こうして幸せでいられるのだろう。 「は、普段頑張り屋であまり文句だとか愚痴とかを言わないよね」 「え、そうかな?」 「優しいし、オレだけじゃなくて他の人たちにも気を遣える」 多分、彼が言う「他の人たち」には、彼に恋心を抱いている人が含まれている。彼に恋心を抱いている、彼に告白をしに来る人たちに、少なからず私が遠慮していることを理解してくれているのだろう。だって、こんな私が彼女だなんて彼にも、彼のことが好きな人たちにも何だか申し訳ない。だから彼には告白された際、「彼女がいる」とは言わないで欲しいとお願いしていた。今思えば、全く無駄で余計な感情だったのかもしれない。彼だってあまり納得してくれず「がそこまで言うなら分かったよ」としぶしぶ了解してくれていた。 本当は、彼の、氷室辰也の彼女だって胸を張りたいのに−。 「でも、オレにくらい甘えても良いんじゃないかな」 「…充分甘えてるよ」 「それでものことだからオレに甘えすぎてるとか色々考えてるんだろう」 「うっ…だって、いつも私が悪いのに辰也くん私を絶対責めないし」 「そうかな?」 「そうだよ…私のこと、甘やかしすぎだよ」 自分でも可愛くないことを言ったと思う。おまけに彼のせっかくの優しさだとか気遣いを否定しているみたい。 「違うよ。を甘やかしてるんじゃなくて、が甘えてるわけでもない」 彼は私を責めないだけじゃない。一緒に歩いている時だって必ず車道側を歩いてくれるし、重い荷物は持ってくれようとする。見たい洋服や買い物があれば嫌な顔ひとつせずに付き合ってくれる。公園で休む時だって、さりげなく飲み物を買ってきてくれたり。家までだってどんな時でも送ってくれる。私がイライラして彼に八つ当たりをしても、彼は怒らない。声が聞きたいと言えば電話をくれるし、会いたいと言えば会いに来てくれる。これで甘えてないなんて言えるわけない。 「オレがを甘やかせたいだけなんだ」  ある日、またしてもやってきた彼への呼び出し。今日の子は多分一年生。私にも緊張した面持ちと敬語で話しかけてくる。「氷室先輩いますか?」って。その緊張がこっちにもうつってしまいそうなくらい。 「た…氷室くん。一年生の女の子が呼んでるよ」 「ありがとう」 先週と同じ光景。ここから彼は女の子と一緒にどこかへ行く。大体校舎裏とか体育館裏とか人が少ないところ。ほら、今日も「つ、伝えたいことがあるので、ちょっと来てもらっても良いですか?」って、声が裏返りそうになりながらも頑張る一年生の子を見て複雑な気持ちになった。だって、彼に恋をする気持ちは痛いくらい分かるから。同じ想いを抱く者として応援したい気持ちもある。相手が彼じゃなかったら。 「ごめん、次の授業の準備とかもあるしここでも良いかな?」 え!?と、誰もが驚くだろう。一年生の子だって驚いてる。私だって驚いている。だって、誰もが「告白」と分かる雰囲気なのに。彼だって、彼だからこそ、これから告白されるということに気づいているに違いないはず。なのにそれを、告白をここでさせるのかという、誰もが抱く驚き。また告白か〜と見守っていたクラスのみんなだって驚いている。今までおしゃべりに夢中になっていたクラスの女子も男子も、みんなが注目した。 「じゃ、じゃあここで言います!」 「うん」 「氷室先輩、す、好きです!私と付き合ってくれませんか!?」 教室が静まりかえる。きっとあの一年生の子も今言わなきゃと思ったのだろう。せっかく勇気を振り絞ってきたのだから、今言わなきゃと。けど、こんなクラス中が注目してる中で言えるなんて、すごく頑張ったんだと思う。それでも彼は断る、断ってくれるのだろう。バスケに集中したいとか言うのだろうか。 「ありがとう。でもオレ、愛しくてたまらない大好きな彼女がいるんだ」 静まりかえった教室が今度は一気にざわついた。周りからは「氷室って彼女いたのかよ!?」だとか「氷室くんの彼女ってどんな子〜!?」だとか。急にそんなことを、しかもこんなところで言うもんだから私が固まってしまう。けど、固まってる私とは正反対に一年生の女の子は冷静だった。 「もしかして、その彼女っていうのが好きな人ですか」 「え?」 「この前、氷室先輩に告白した友達が言ってました。「好きな子がいるから付き合えない」って言われたって」 そういえば、彼はいつもどうやって告白を断わっていたのだろう。私が「彼女がいるとは言わないで」なんて下らないお願いをしたから、てっきり告白してくれた人たちの傷が少しでも浅くなるであろう「バスケ」を理由にしてるのだと思っていた。今は誰とも付き合う気はない、とかそういう感じ。なのに、好きな子って 「うん、この子」 急に腕を掴まれたかと思えば、そのまま引っ張られる。彼の隣に並ぶ私は今、この場にいる全員の誰もから彼の彼女として見られているに違いない。 「オレにはがいるから、悪いけど君の想いには答えられない」 |
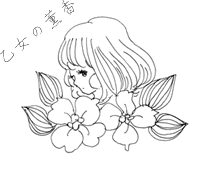
|
−の「彼女がいるって言わないで欲しい」っていうお願いは、やっぱり聞いてあげられないみたいだ。 甘やかしてあげられなくて、ごめん− |