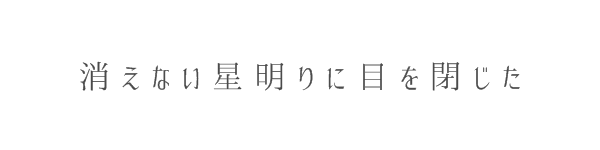チカチカ、チカチカ。目黒のこじんまりとしたお店で買ったアンティーク調のランプ。天井だけでなく部屋の空間すべてが一気にレトロで、でも華やかになるこのランプの小さい電球がサインを送ってきた。「限界だ」とでも言うかのように暗くなったり明るくなったりの繰り返し。サスペンス映画を見ていたら、きっとホラー映画に早変わりしてしまうだろう。テレビを見ていても内容は全然頭に入って来ない。本を読んでいても、せっかくの活字たちがなかなか読み取れない。まるで私のプライベートを邪魔しているかのようで、煩わしくて仕方ない。いっそのこと暗くなるならなれば良いのにと何度も思った。もちろん、電球を変えれば良いだけの話。けれど今までの人生、恥ずかしながら自分で電球を変えた経験の無い私は、まず何をして、どんな電球を買って、どう取り外して、どう取り付けるのかが分からない。そんな中、ひとりの救世主がやって来た。
「電球変えた方が良いんじゃないか?」
「だってよく分からないんだもん」
「じゃあ一緒に買いに行こうか」
誰もが気づくであろう前兆。部屋に入るなり彼もすぐにチカチカと小さい呻き声をあげながら早く取り替えろとアピールしてくる電球に反応した。やはりこういうのはメンズの得意分野なのだろうか。まずはコンビニに行ってみようと左手に財布、右手に彼の手を握り締め、電球を買いに行く。
ポツポツと灯る外灯に照らされた、明るいとも暗いとも言えない道。不思議なことに、いつもひとりで歩いているこの道も、彼とこうして歩いていると全然違った景色に見える。電球なんて色気の欠片も何もない庶民的な目的なのに、微かに濃紺が残る夜空になりかけの空が眩しい。
「電球ってこれ?」
「それじゃあサイズ合わないからこっち」
今時のコンビニには電球も売っているのかと無知な頭を隠しながらたどり着いたコンビニで、ついお菓子を買いたくなる衝動も一緒に隠す。適当に電球を手に取ってみるが、どうやら違うらしい。彼はいつの間に電球のサイズなんて調べたのだろう。そんなありふれた日常のひとかけらの「今」にやたらと胸の奥が熱くなる。たくさん並んでいる電球の中から私の家の可愛いランプに合う電球をピンポイントで見つけ出すなんてヒーローみたい。そんな風に言うと大袈裟に聞こえるかもしれないけど、とっても頼りになる存在ということを言いたいだけ。おまけに私が食べたいと言っていた新発売のチョコレートまで、何も言わずにレジに持っていく姿を見て思わず抱きつきたくなる衝動を必死に抑えた。彼の右手には電球が入ったビニール袋。左手には私の右手。こうして歩いているだけなのに、なんだか一緒に住んでいるような感覚になってしまってひとり胸がドキドキ。帰り道の途中、商店街のお店の人が本日最後の呼び込みをしている声も、自転車のチリンチリンと鳴るベルの音も、車がゆっくりと通る音も、耳を澄ませたくなるほど心地良いハーモニー。彼と一緒に歩いているだけでそんな楽しい気分になれてしまうなんて、ある意味贅沢な幸せ者だ。家までの道があっという間に感じられて少し物足りない。
「じゃあ早速電球変えちゃおうか」
「やってくれるの?」
「もちろん。にやらせたら危なっかしくて見てられないよ」
「私、そんな女の子らしくないと思うけど」
「こういうのは男に任せてってこと」
踏み台も無しにランプへ手を伸ばした彼。身長が高いとこういう時、便利だなぁなんてありふれたことを思うと同時に、その背中に手を伸ばしたくなった。彼の腕の筋肉だとか、広い背中だとか、集中してる横顔だとか、すべてが私をときめかせるのに充分な要素を孕んでいる。キュッキュッと電球を回す音が私の心臓の音に相槌をうつかのよう。彼から古くなった電球を受け取り、先ほど買った新しい電球を渡す。こうしてみると違いは明らかで、古くなった電球にお疲れ様と言いたくなった。
「きっと明るくなるよ」
真っ暗闇の中、彼に電球を渡すために微かに触れた私の指たちがざわめいている。彼の指に手を触れるなんて、お互いの指を絡めて手を繋ぐようになった今となっては当たり前のこと。なのに今時中学生でも抱かないような初を咲かしてしまった。月と星しか輝いてない暗闇の情景が、私の胸の高鳴りを荒々しくさせるのに充分なエッセンスである。
「よし、ついた」
「わー、ありがとう!本当、明るい」
途端に明るくなる室内。一瞬、その眩しさに目を伏せたくなった。部屋の中も、表情も、心の中も明るくするようなちいさい光が目映い。
「の顔もよく見えるよ」
ランプの電球が照れるように光っている。その光の下で、彼のくちびるが私のくちびるに灯火をつけ、私の頬を赤く点灯させた。