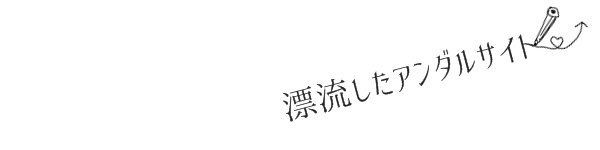|
お気に入りの場所がある。人が多過ぎず少な過ぎず、うるさ過ぎず静か過ぎないキャンパス内のラウンジ。周りの学生たちの様々な個性を表すかのように、可愛らしくもありオシャレでカラフルで形がひとつひとつ違うソファーたちは背もたれがないのが少し不満である。けれど私がもっぱら住み着いているのは、木目調のテーブルがあるゾーン。不規則にカーブした長めのテーブルたちは用途も様々らしく、サークルの集団が話し合いをしていたり、個人で課題をしている人間なんかもいる。今の私は後者。講義が入っていない時間を利用して、硬いチェアに腰掛け冷めたインスタントのコーヒーを一口、苦い。 「ああ、やっぱりここにいた」 「氷室くん、どうしたの?」 「が課題に埋もれてるって聞いて」 「もしかして助けに来てくれたとか?」 「まぁね」 「さすが氷室くん」 同じバスケサークルに所属している彼はどうやら私のヒーローになりに来てくれたみたいだ。そういえば英語系の課題もあったはず。基本どのジャンルの課題も完璧に手伝ってくれそうではあるけど、まずは英語系のものをお願いしてしまおう。 前に座った彼に課題を渡すと、彼は早速ペンを走らせた。足を組みながらサラサラとペンを動かす姿が様になっている上にペンがなかなか止まらない。社会に出ても通用する男を既に醸し出している。 「そういえば昨日の飲み会、大変だったみたいだね」 「ああ、小太郎くんでしょ?彼女と別れたのを宥めるのにみんなで話聞いてたから」 「それは…大変そうだな」 「今回は彼女に「私が悩んでることにも気づかない彼氏なんて要らない」って言われたらしいよ」 同じサークルに所属している人間の恋愛事情を語りながら課題に取り掛かれるほど器用ではない私はペンを止めてすっかり休憩モードになってしまっていた。きっと彼が私が根を詰めているのを察して話し掛けてくれたのだろう。会話を交わしながらもペンは止まらない彼を尊敬する。おかげでこの場所の滞在予定時間も短縮出来そうだ。あれだけ眩しいくらい日が差していたこの場所も、少しだけオレンジ色に染まり始める時間になってきた。 「男は鈍感だよね。氷室くんがどうかは知らないけど」 女が気づいて欲しいことに気づかないのが男。例えば髪を切っただとかメイクを少し変えただとかビジュアルな面はもちろん、会いたいだとか寂しいだとか、そういう心情が絡む面だってそう。男はなかなか気づいてくれないから、気づいて欲しい女は気づかない男に虚しさや怒りを感じてしまう。何度もそういう恋人たちを見てきたけど、気づいてあげてと男たちに言ってもきっと難しいのだろう。けど、稀に女心を理解してくれる男も存在する。目の前に座っている彼なんてきっとそう。 「オレが鈍感かどうか気になる?」 「うーん、別に。でも、氷室くんも鈍感な時あるよね?」 「そうかな?」 口元に笑みを浮かべている時点で確信犯。「"鈍感"ではなくわざと"鈍感を装ってる"時があるよね」と問いたいくらいだ。構内を賑わせる人気者であるが故の、仕方がないことなのかもしれないけれど。サークル内にもサークル外にも、彼が通り過ぎるだけで乙女の吐息がたちまちピンク色に変わる。男女問わず人気者で、周囲をよく見て誰にだって気を配れる彼がそんな事実に気づかないわけないのに。彼は謙虚の中に感情を隠す時がある。 「…じゃあさ、鈍感なオレに教えてくれないかな」 そして、鈍感なんじゃないくせに鈍感なフリをして油断を誘うのが彼のタクティックスとでも言うのだろうか。彼の片目をとらえた私の双眸はきっと揺れている。何もされていないのに逃げ道を完全に塞がれてしまったような感覚に襲われて、それを理解する時間もないまま私は彼に鈍感でいて欲しかったという我儘と、もっと早く気づいて欲しかったという矛盾が生まれてしまった。彼の口元に描かれた美しく緩やかなカーブは、きっと答えを全て知っているのに。 「オレがのこと、どうして放っておけないのか」 オレンジ色の夕陽が私の頬の紅潮を誤魔化す。けれどそれを阻む彼との距離が近くなって、落ち着くために飲んだコーヒーは少しだけ甘い。 直接言葉にする勇気がなくて、芯の無いシャーペンでルーズリーフに綴った「好きだから?」の解答は彼を笑顔にさせた。
|