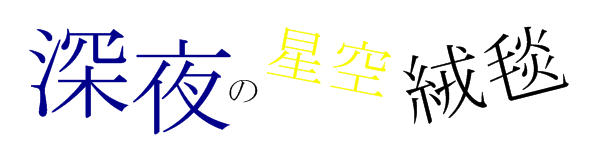|
PM11:25。ぼんやりと黄色く灯る月と目映い星が映える今宵、氷室がいるこの空間はとても穏やかで静かだ。部屋の中でリラックスタイムを満喫中の彼は、コーヒーを飲みながら本の中で様々な物語が繰り広げられる活字を追う。イタリアの革を使用したブックカバーが、経年変化により程良い艶を生み氷室の手に馴染んでいるようだ。そんなひとつの光景から聞こえる音はページをめくる音くらい。少し休憩しようと本に栞を挟むと、タイミング良くスマホが振動しテーブルが僅かに震える。こんな時間に一体誰が?という疑問が浮かんだが、見慣れた名前がディスプレイに表示された。 「あ、室ち〜ん?」 「アツシ、こんな時間にどうしたんだ?」 「迎えに来て〜」 男から、しかも2mを超える自分よりも大きい男に「迎えに来て」と言われたところで、当然躊躇いが生じるのはごく自然なこと。すぐに頷くことが出来ず喉を詰まらせていた氷室だが、電話の相手である紫原からその後すぐに「ちんを」という言葉を聞いた途端、思考が180度変わった。そういえば彼女は今夜アツシや中学時代の旧友たちと飲みに行くと言っていたな、とぼんやり思い出す。 紫原からのヘルプコールを受けるとすぐに着替える。もう夜になるとすっかり肌寒くなってきたこの頃。薄手の黒のジャケットを羽織り目的地まで向かう。氷室の家から割と近い場所だったのは幸いだったようだ。電話から約30分程で氷室は紫原の元へ辿り着いた。明るすぎない照明のせいか、店内は落ち着いた雰囲気を出しており、カウンターに並んだワインやビール、他にも漆黒のソファーや木目のローテーブルなどがこの空間とオトナな時間を醸し出している。馬鹿騒ぎするというよりは、ゆっくりと酒を飲みながら深い話をするのに適していそうだ。既に飲み会は終了、メンバーは解散していたらしく、その場には紫原とチークにしては濃いような赤を頬に火照らせ、紫原に寄り掛かりながら目を閉じているしかいなかった。 「早かったね」 「思ったより近かったからな」 「電話でも言ったけどちん、こんななっちゃったから」 「にしては珍しいな」 「ね〜。あ、言っておくけどオレ達が無理矢理飲ましたわけじゃないよ」 「分かってるよ」 氷室も紫原に向かい合うように座り、ついでにビールを一杯注文する。時刻は既に日付けを跨いではいるが、店内はまだ活気に満ち溢れているようだ。ついでに、と言うように紫原もカルーアミルクを一杯注文した。 「オレがおんぶして室ちんとこまで持ってても良かったんだけどさ〜室に迎えに来て貰った方が色々良いかなって思って」 「アツシにしては気が利いていたよ」 彼ら二人は高校を卒業してから今でも割と会う機会が多いため、今更話し込むようなことも特に無かった。典型的な、他愛もない話を少し繰り広げたところで氷室のグラスが空になる。それが合図かのように氷室は立ち上がり、うとうとしているに声を掛けた。寝ているわけではないようだが、おそらく雲の上を歩いているような感覚に浸っているのだろう。たまに小さく動きはするものの、なかなか瞼は開いてくれない。 「、帰ろう」 「んー…」 何故氷室が此処にいるのか?といった疑問は、彼女の今の思考回路ではショートカットされたようだ。目をうっすらと開けて氷室の存在を認識はしたものの、またゆっくりと瞼を閉じて紫原の腕にしがみついてしまった。本人に悪気は無いとはいえ、この行動に二人の男はそれぞれ別の意味で戦慄する。くちびるは緩やかな弧を描いている氷室ではあるが、内心は表情通りではないということを紫原は長年の付き合いにより悟っていた。 「ほら、おいで」 「んー…やーだー」 拒絶の言葉を吐いたに今度は男たち二人、戸惑いと疑問を生まざるを得なかった。そもそもと氷室は特に喧嘩をしているわけでも、仲が悪いわけでもない。ごく普通の、仲の良い恋人同士である。昨日だっていつも通り一緒に夜ご飯を食べていた。それがたった一夜でこのような急展開。お酒の影響だということは誰もが理解しているものの、の酔いが覚めるのを待っていたら朝になってしまいそうだ。 「、どうかした?」 「やーだー…」 「それじゃあ分からないよ」 「だって…」 まるで子どものように拗ねているは、紫原から頑なに離れようとしない。氷室以上に困っているのは紫原だ。無関係であるにも関わらず、恋人同士のいざこざに巻き込まれ、離れようと思ってもに腕をしがみつかれているため見動きが取れない。無理矢理引きはがすのも躊躇われる。解決するまで黙って静観しているしかないのだ。 「アツシ、今日のの様子どうだった?」 「いつも通りじゃないの〜?あ、でも急にペース早くなってひとりで潰れてった」 「まぁ…そんな感じだろうな」 「ってゆーか、いつものアレじゃない?」 誰と比較しているのか分からないが芽生えてしまう劣等感。何に怯えているのか分からないが拭えない憂慮と不安。の中には氷室との恋愛に対して抱いてしまう負の感情がいつでも存在していた。こればかりはいくら氷室が愛を注いでも、いくら周りがフォローをしても、本人の生まれ育った価値観や性分なのだろうか。なかなか排除されないらしい。氷室という人間の隣に自分はいても良いのか、という不安が酒のせいで溢れ出てしまったようだ。紫原や氷室にとって、が抱くこの無駄に等しい感情を肌で感じるのは慣れているが、氷室は些か責任を感じている。 「ちんは相変わらず鈍いよねー」 「まぁでも、そんなところも可愛いだろ?」 「うわ…つーかそれ、オレがどう答えても室ちん納得しないでしょ」 「どうかな?さて、でもそろそろ帰らなきゃな」 の小さいようで大きい悩みをいじらしいとでも思っているのだろうか。氷室はのこの負の感情を無理矢理排除させるつもりなかった。ゆっくり、ゆっくりで良いから、自信持ってくれればという見守るような立ち位置にいる。 紫原にしがみついているの頭をひと撫でし、視線をに合わせるようにしゃがみ込みながら会話を試みる。 「ほら、無理矢理連れて帰るよ」 「…」 「そのままがアツシにしがみついていたら、オレが寂しいよ」 ゆっくりと紫原から離れたは人目も憚らず、氷室の首に腕を回し抱きついた。幸い周りは其々の世界に入り込みお酒を嗜んでいるため、誰も彼女たちのことは見ていない。のその行動に満足したのか、氷室もようやく安堵したような表情を浮かべた。「じゃあ先に失礼するよ」とと指を絡ませながら店内をあとにする二人を見送った紫原の腕に、温もりはもう無い。 冷たい夜風に当たったおかげで酔いが覚めてきたは肩を少し震えさせ、寄り添っていた氷室の肩も僅かに振動させた。氷室は彼女のためにと持ってきていたグレーのカシミヤのカーディガンをの肩に羽織らせ、再び月と星に見守られた道を歩く。 「ご、めんなさい。迷惑かけて」 「良いよ。でもアツシにもお礼を言っておかないとな」 「うん」 「じゃあ、早く帰ろうか」 二人が歩いている道だけ、スポットライトが当たっているかのようにあたたかい。今宵の陶酔はきっとまだ終わらないのだろう。
|