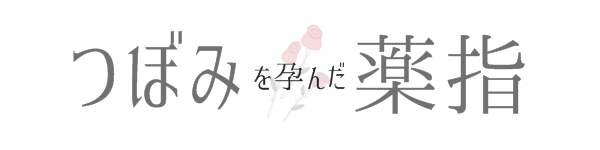|
白いウエディングドレスに映えるような青空はまさに結婚式日和。今日は高校時代の先輩である福井先輩の結婚式に、恋人である辰也くんと共に出席する。彼も私もお世話になっていた先輩の結婚式ということもあり、喜びの報せを受けた時は二人で喜んだものだ。 既に準備を終えて迎えに来てくれた彼を部屋に招き入れ、ソファーの上で待たせる。申し訳ないとは思いつつも買い置きしてあった安っぽいインスタントコーヒーを差し出し、時間を埋めてもらう。主役である花嫁さんを引き立たせるために纏ういつもより華やかなドレスやヘアメイク。時間をかけて丁寧に作りあげていかなければ。ただ、彼のフォーマル用のスーツ姿に見惚れてしまった時間が少し惜しかったかもしれない。彼が着るスーツはきっと世界中で売れる。そんな風に思ってしまうあたり盲目だ。 「まだ時間もあるしゆっくりで良いよ」 「ありがと。でもあと着替えて髪セットするだけだから」 新しく新調したドレスを着て、全身を映すミラーの前で360度回転。昨日ネイルサロンで施してもらった肌馴染の良い薄いピンクのネイルでストッキングを破かないように、ゆっくりと脚を通していく。ストッキングのおかげで私にも辛うじて脚線美が生まれる気さえしてしまうのは図々しいだろうか。そのまま軽やかな足取りで彼の元へお披露目、そしてひとつのお願いを聞いてもらう。 「辰也くん、辰也くん」 「によく似合ってるね。可愛い」 「ありがとう。ね、ファスナーあげて」 彼の言葉は魔法のように私の頬を紅潮させる。けれど動揺ばかりしていたら身が持たないため、ときめく感情を必死に心の奥底へ沈める。新しく買ったばかりでまだ慣れないドレスのファスナーをあげるには、体の硬い私では時間が掛かりそう。昨日入念にトリートメントしたおかげでサラサラに蘇った髪を持ち上げて彼に背中を見せる。後ろからくすりと笑う声が小さく聞こえて、別の意味で恥じらいが生まれた恥じらいは私だけの秘密。故意にやっているのか否かは分からないけれど、彼の指が背中に直に触れると少しだけくすぐったい。ファスナーが上まで上がったのを感覚で感じ取ろうと集中しすぎた背中は、より敏感になってしまっている。 「あ、ありがとう」 「どういたしまして」 電源を入れておいたコテよりも早く私の心が温まってしまったようだ。逃げるように今度は小さいドレッサーの前に座りながらヘアセットの準備。髪を適当にブロッキングして、一般的な32mmのコテを使い、リバース巻きフォワード巻きを交互にしていく。日頃からMIX巻きをしているので、程よいカールを誕生させることも困難ではない。しかし、慣れとは恐ろしいもので、油断を招く要因の最たるもののひとつだろう。あとたったひとつの工程。最後の工程ですべてが完成。ようやくいつもより華やかな自分を演出出来ると思っていたのに。 「熱っ!」 前髪をワンカールさせようとしたところで気を抜いてしまったのだ。おかげで額が一気に熱を持ち、おそるおそる前髪を上げてみると、じんわり赤い。バタバタと急いで冷凍庫に入っている保冷剤を額に当てる。ちょっとした騒音に違和感を感じた彼が心配して様子を見に来てくれた。 「大丈夫?どうかした?」 「おでこ火傷した…」 「どれどれ…あ、本当だ」 彼がそっと前髪を上げてくれたその距離にジクジクとするのは額の火傷のせい、だということにしておこう。心配そうに額を見てくれる彼の顔を下からこっそりのぞき見してちょっとした優越感を抱くなんて、馬鹿な女だ。ただの愚かな動作から生まれた自己責任の火傷でさえ、彼は心底心配してくれる。痛いのは頑張れば我慢出来る。幸いにも前髪で隠れる場所を火傷したので、街中で恥ずかしい思いをすることもなさそうだ。けれど、ひとつだけ心配することがある。 「痕に残ったらどうしよう…」 「すぐ冷やしたし、きっと大丈夫だよ」 「でも…痕残るかも」 「は心配性だな」 「だって痕になんてなったら余計お嫁に行けなくなっちゃうかも…!」 「え?それは心配しなくて良いんじゃないか」 「え?」 「オレは気にしないよ」 頭にたくさんのハテナを浮かべていると、頬に触れるだけのキスを落とされた。ちゃんとメイクが崩れない程度の本当に一瞬触れるだけのキス。そしてやっぱりほんのり紅く染まる頬。「少しでも火傷が目立たないように、ね」なんて、キスをされるだけで私の頬が簡単に色づくことを彼はお見通しなのだ。けれど「違う、これはチークだ」なんて言い訳を言う程の余裕が今は無い。どういうこと?と聞くのも今はまだ怖くて、火傷した額より熱くなった心を保冷剤で冷やしたいくらいだ。誤魔化すようにドレッサーに戻り、髪をアップスタイルにする。そしてパールのピアスとネックレスをつければようやく拙いながらも魔法の完成。待たせていた彼に一声掛け、戸締りを終えて玄関へ向かう。胸中穏やかではないけれど、少しでも心を落ち着かせようと無理矢理話題を生み出す。 「け、結婚式楽しみだね」 「そうだね」 「どんな結婚式なんだろう。福井先輩派手なの好きじゃなさそうだけど…」 「はどんな結婚式を挙げたい?」 玄関に向かうまでのたった少しの距離で一体どれだけの動揺と戸惑いとときめきが私を襲っただろうか。廊下のフローリングが未来への赤い絨毯に思えてきて、そんなことを思ってしまう自分に眩暈さえした。小さいパーティーバッグを持つ手に自然と力が入る。 「ど、うしてそんなこと聞くの?」 せっかく塗ったルージュが彼のくちびるにうっすら移る。目を凝らしても、そんなことくちづけした当人同士しか分からないくらいの色づきではあるけれど、それが余計に艶気を際立たせる。彼の指に触れられたパールのピアスに映っているのはきっと夢なんかじゃない。私が今見ている光景と同じはず。少し無邪気に笑う彼の顔。 「ひみつ」 そして、首元に光るパールが嬉し涙になるまでのカウントダウンがゆっくりと鳴り響き始めた。
|