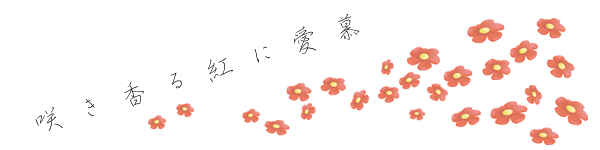月に照らされる檜で作られた箱。それは身体に良い成分たちが散りばめられた小さな露天風呂。少し肌寒くなってきたものの、外気の冷たい空気と温泉のお湯が心地の良い時間を作り上げる。きっとひとりでぼんやりと湯船に浸かるより、誰かと楽しんだ方が甘美な時間を過ごせるだろう。そんな贅沢な時間を身の程知らずにも放下した私は罪な女なのかもしれない。
初めて彼と二人きりで思い出を作る温泉旅行。前日は浮かれ過ぎてあまり寝れなかったの、なんて私の子どもみたいな感情に微笑んでくれる彼。たくさんの観光箇所を訪れ、悠然な時間を二人で過ごしたりと日常では決して味わえないひとときが楽しい。彼がチョイスした雰囲気の良い旅館に胸を弾ませていると、仲居さんに「素敵なカップルですね」なんて言われてそれに照れている私に構わず「はい」とすぐに答えてしまう彼に、またしても私の頬が紅潮する。
しかし、そんな私の火照った感情は急速に冷えていく。そういえばそうだ、この宿は全室露天風呂つきが売りだった。旅行までの間、もしかして明るい場所でこの怠んだ裸体を彼に見せることになるかもしれないという憂惧、いやそれよりも初めて彼にすっぴんを見せなければいけないという憂苦に悩んでいたというのに、旅行という期待に胸を弾ませ過ぎていつの間にか忘れてしまっていたのだ。
私は普段の情事から光の下で裸を曝すことを苦手としている。明るい場所で自分の決してキレイとは言えない裸を彼の目に入れることにひどく躊躇いを感じるからだ。彼はもうすっかり私のそんな愚昧な感情を理解しているので、露天風呂に一緒に入ることは厳しいということも言わなくても分かってくれているようだった。それに何より一緒にお風呂になんて入ってしまったら、嫌でも素顔を見せなければいけなくなる。もちろん、今宵それが避けられないことは理解してはいるけれど、まだ心の準備が出来ていない。じゃあ先に入ってくるね、とだけ言ってくれた彼を見送り、もうひとつの絶対に避けられない問題に改めて直面する。
彼と交代で入るように旅館の慣れないバスルームでシャワーを浴び、身体が充分に温まったら蛇口を捻って一度止める。アメニティで用意されている日本の王道ブランドのシャンプーたちをぼんやり眺めて、鏡の前に映った自分が本当の自分なのか自問自答してみた。答えをハッキリと述べることも出来ないのに。
持ってきた愛用のクレンジングオイルを乾いた手におそるおそる乗せる。このクレンジングオイルというものは不思議なもので、みるみるうちに肌に直接張りついている仮面をするすると落としてしまう。睫毛専用のクレンジングを使ったあと、顔全体にオイルを広げていく。くるくるとマッサージをしながら少し冷たい水で流し、再び鏡を見る。そしてその鏡にシャワーをかけて視界でとらえたこの世界を歪ませた。
バスルームを出て、ふわふわの白いタオルで、髪や体についた水滴を吸い取る。浴衣を羽織り、適当にタオルドライをしてドライヤーで髪を乾かせばカウントダウンの始まり。既に乾いた髪をなびかせ、座布団の上でくつろいでいる彼の元へダッシュで飛び込む。
「わ…びっくりした」
勢い良く彼の胸元へダイブし、そのまま顔を彼の胸に押しつける。漂うシャンプーの香りは彼からか、私からか。同じ香りで分からない。私の心情を理解しているのだろう。くす、と笑みをこぼした声音が頭上に振り、私の髪を彼の手がさらりと撫でた。
「今日のはずいぶん積極的だね」
「は、初めてふたりだけでの旅行だし」
「それだけ?」
「は、離れたくないの」
「どうして?」
「それは、その、た、辰也くんのことが好きだからに決まってるじゃん」
嬉しいこと言ってくれるね、と言いつつもその台詞に込められているのは、私の必死の抵抗を見破っている笑い声。彼の長い指が私の耳に触れ、髪をゆっくりとかけられる。耳と肌がほんの少し露わになって、それだけで恥ずかしいのに、顔面ぜんぶなんてとてもじゃないけど無理。なのに「顔見せて」と剥き出しになった私の耳を貫いて心臓を破壊するような囁きをするのだから憎らしい。けど、どんなに必死に抵抗しても、いつか覚悟しなければいけない瞬間が来る。彼にすっぴんを見せられない関係で終わるのもまた辛い。意を決し、彼と目を合わせずにゆっくり顔を上げる。きっと寝てしまっている睫毛は私の小さな瞳を隠すほどの長さも無く、砂漠より乾燥地帯の肌には誰も寄りつかない。
「可愛いよ」
「いーよ、別に」
「まつげ触らせて」
「わ…」
本当に私の睫毛を触る彼の指に怯えて目を瞑った。まるでマスカラを塗るみたいに睫毛が上下に動かされている感覚と、ふわりと肌にファンデーションを乗せるような軽い彼のキス。私の心情は頬の沸騰が物語っている。口から心臓が飛び出る程の熱い抱擁と「かわいい」という言葉。彼なりの優しい嘘だと思っても胸がざわいて、それなのに心はなかなか素直になんてなれない。
「オレとまだ出会ってない頃の昔のに会ってるみたいで嬉しくなる」
幼くなったと言いたいのだろう。それが嫌なのに、それを「嬉しい」と言うのだから理解出来ない。すっぴんを見せるくらいなら裸を見せた方がまだ良い、は言い過ぎかもしれないけれど、素顔に自信が持てない女の子にとって、すべてを曝け出すというのは勇気がいることであり、信用のおける人間にしか見せることが出来ない。もしかしたら嫌われてしまうかもしれないという恐怖と戦わなければいけないのだ。
「なんでそんなにすっぴん見たがるの?」
「自分にとって特別な人の、いつもと違う素の部分も全部見たいと思うのが男の性だよ」
「わかんない」
「オレだけが知ってる、っていうのがまた良いんだよね」
「もっとわかんない」
「男はみんな独占欲を隠す子供だから」
毛穴だって開いてるし、眉毛だって少ししかないし、目だって小さくなるし、くちびるだって色が悪い。けれど、彼のくちびるに撫でられた頬はチークのようにみるみるうちにほんのり紅く染まり、くちびるだってほんのり色づく錯覚さえ生まれる。あらゆる効果を持つ魔法のような彼のくちびる。頬から首筋と徐々に降下していく彼のくちびるが熱いのか、私の身体が熱いのか、両方熱いのか。
「の全部が欲しい」
せっかく着た浴衣が肌けて、素肌の上に彼のくちびるが艶美に舞う。私が輝けるのはファンデーションやグロスたちによって必死に飾り立てた結果だけじゃない。彼がいるから、私は私なりに輝ける。
「ねえ、あとで一緒に露天風呂入ろうか?」
「う、ん」
色づいたのは表情だけでなく、何ひとつ隠すところが無くなり露になったわたしのすべてだ。もう彼と過ごす時間に憂心なんてひとつも抱いてない。