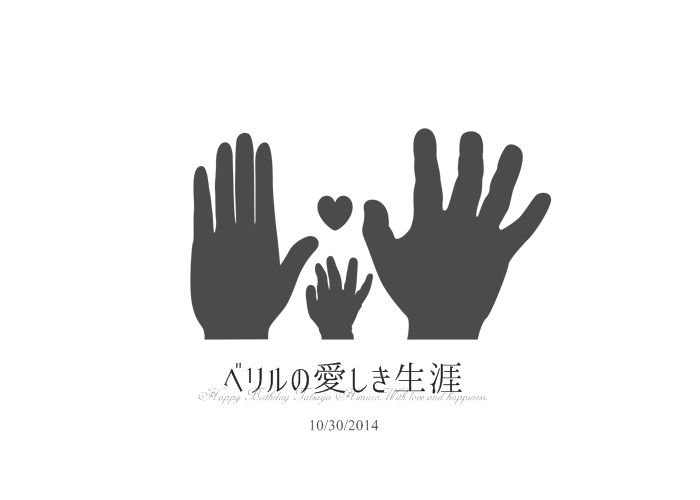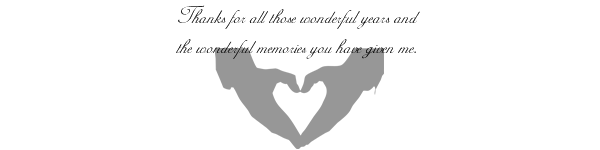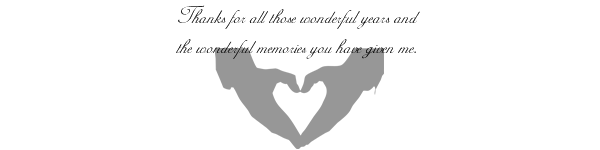ひとつの宝箱が見つかった。
部屋の掃除をしようとクローゼットの奥を整理していると、たくさんの懐かしいものたちに遭遇する。そんな中、ひとつの箱を見つけた。真っ白いその箱は奥に存在していたにも関わらず、微塵も色褪せていない。中身が気になり開けてみると、昔の記憶が蘇るような思い出の数々。旅行に行った時に購入したご当地ものの置物土産だとか思い出が詰まったアルバムだとか写真だとか。何れもオレたちふたりに関連した物ばかり。思い出を形として残しておくことが好きなが、年月をかけて積み重ねていったものだろう。ひとつひとつ眺めながらノスタルジックな感覚を味わっていると、その中に紛れて心当たりの無い白い厚紙が2枚。両方共裏返してみると少し退色してはいるものの、今もなお存在感ある眩しさを放っている押し花。どうやら栞のようだ。それぞれ違うその花たちを眺めていると、すぐにその栞に纏わる情景を思い出すことが出来た。
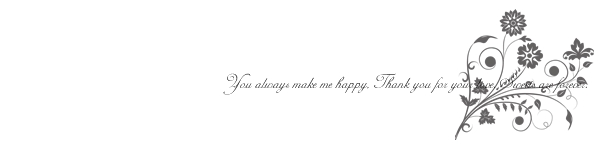
ひとつは以前、と喧嘩した時に関係する。あまり喧嘩などはしないふたりであると認識しているが、長い付き合いがあれば言い合いくらいは稀に発生する。喧嘩の原因となると覚えてはいないが、下らないことだったのかもしれない。けれど、オレも珍しく感情的になってしまい由々しい事態へ発展してしまったことは鮮明に覚えている。の潤んでいた両目から透き通るような涙が頬をゆっくりと流れた瞬間、それが限界のサインだったのだろう。急に部屋から飛び出してどこかへ行ってしまったあの夜のことを思い出した。あの頃はオレもまだまだ子どもだったな、なんて思いながら当時公園のブランコで項垂れるように座っていたを見つけた瞬間にひどく安堵したことも思い出した。
「!?」「た、辰也くん」「ほら、家に戻るよ」「や、やだ!辰也くん怒ってるもん」「…怒ってないよ」「怒ってるよ!」「っていうか、こんな深夜の遅い時間にひとりで財布も携帯も持たずに飛び出したことの方が叱りたくなるよ」「う…」「まぁ、そうさせちゃったのはオレなんだけど…まずは家に戻ってからだ」「で、でも」「…。お願いだから、帰ろう?」「…はい」
もう世間はきっとこの穏やかな夜空の下で眠りについている。辺りも真っ暗で人工的な明かりは外灯くらい。あとは月と星の光くらいしか見えない時間だったかな。あんなにシリアスなムードだったのに、公園から帰る時には当たり前のように手を繋いでいた自分たちが少し可笑しかった。半歩後ろを歩いているの手は少し冷たくなっていて、でも玄関の扉にたどり着いた時にはお互いの手のひらは温もりで満ち溢れていて、同じ体温を共有していた。
「すごく心配したよ」「ごめんなさい」「に何かあったらどうしようって心臓飛び出るかと思ったくらいだ」「辰也くんがあんなに焦ってるとこ初めて見た。なんか新鮮だった!」「誰のせいか分かってる?」「うっ、ごめんなさい…」
自分が原因のひとつであることは重々承知していたが、消沈しながら謝るが可愛くて、少し意地悪したくなったのを今でも覚えている。本当に子どもみたいだ。翌日、オレは詫びと改めてこれからもよろしくと言う意味を込めて帰りに駅前の花屋で買ったマーガレットの小さなブーケをにプレゼントした。渡した瞬間、まるで映画のワンシーンみたいに細い指を並べて口を覆ったその姿が愛くるしかった。この栞の押し花は、紛れもなくその時の花だ。
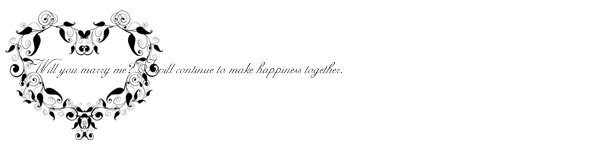
そしてもうひとつの栞。これは先ほどの一枚に比べるとまだ記憶に新しい。そうだ、これはオレが人生で一番緊張したと言っても過言ではないあの時。と一緒に生きていきたいという表明を本人に伝えた日だ。プロポーズした時に贈った大きなバラの花束が今もこうして押し花となって存在しており、当時のシーンが鮮明に思い出される。
「を一生幸せにするよ」「…やだ」「え?」「しあわせにしてもらうだけなんて嫌。私も、辰也くんのことしあわせにする。したいんだから」
高層階のレストランで流れる心地の好いピアノの旋律が穏やかで優雅な時間を奏でる中で、いつもより少しだけドレスアップしたの美しさは、この宝石が散りばめられた眩しいくらいの夜景を遥かに凌駕していた。瞬きをした瞬間に見える瞼のグラデーションだとか、頬に影が出来そうなほど長い上向きの睫毛、それからやわらかく透き通るような肌に血色の良い頬、夜景に映えるルージュはいつだってオレを誘っていて、爪に塗られたコーラルピンクは彼女の指をより美しく見せる。その左手の薬指に早くオレが贈るエンゲージリングをはめて欲しいと思ったものだ。そんな美しい彼女から出た可愛いらしい言葉。ああ、やっぱりオレが選んだ女性だと、に惹かれた自分を自画自賛したくなる程、今の幸せとこれからの未来に笑顔が零れた。その愛らしい双眸が朧気に潤んでいるように見えるのに、強い意志を持ってそんな嬉しいこと言ってくれるが愛しくて。オレがプロポーズしたはずなのに、オレの方が幸せになっちゃったんだっけ。
「辰也くんも一緒にしあわせになってくれなきゃ、私しあわせになれない」
敵わないな、と思った。今までの緊張が一気に吹き飛んで思わず声を出して笑った。そのせいか、自分で言った言葉を恥ずかしく感じたのかもしれないが頬を紅潮させながらあたふたしていた光景が今でも脳裏に思い出される。
「オレはと一緒にいれるだけで幸せだよ」
結婚して下さい、と改めて伝えた言葉に涙をポロポロと零しながらその雫がプレゼントした花束に落ちる。バラの丸みを帯びた花びらを滑り流れる透明な雫は、きっとオレの嬉々たる表情を映していたのだろう。言葉が上手く出せずに首を何度も縦に降ったを、一生大事にしたいと思ったんだ。

「辰也くん、片付け終わったー…って!」
「懐かしいものが出てきたんだ」
「…あ!それ!」
「がこんなに色々とっておいてたなんて知らなかったよ」
「恥ずかしいから返して!」
感情がすぐ表情に反映してしまうところは今でも変わっていない。の分かりやす過ぎるところは羨ましくもあり、微笑ましくもなる。付き合い始めたあの頃といつまで経っても変わらない無垢な。いや、あの頃よりキレイになったかな。少なくともオレが何度か焦るくらいに美しく可愛く素敵な女性になっていくを一番近くで感じることが出来て、複雑な思いを抱いたこともあるけれどやっぱり嬉しくもある。
「って、。またそんな重いの持って」
「重いのって、本5冊くらいじゃん」
「だーめ。はこっち」
「相変わらず過保護だなぁ」
両手に些か分厚い本を抱えてやってきたに、宝箱と言えそうな思い出の白いボックスを渡し、彼女が持っていた5冊の本を本棚に置いていく。ちゃんと作者順に本を重ねて持ってきてくれたおかげで、特に思考を働かせることもなく、仕舞うことが出来た。その後ろで彼女が箱の中を探る音が聞こえて、きっともオレみたいに昔を思い出すんだろうなと思った。長い年月をかけてこの箱の中身を思い出で埋めてきたの方が、懐かしさをひとしお感じることだろう。
「生まれてくる子が女の子だったら大変そう」
「性別、まだ聞いてないんだっけ」
「ふっふっふー」
「え?」
「まだ秘密ー!」
無邪気に笑うの愛らしさに、今でも胸がやさしい気持ちでじんわりと熱くなる。平日、普段賑やかなオフィスであっという間に駆け巡る時間とは正反対で、と過ごす時間は悠然で欠けがえのないひとときだ。あれから結婚して、同じ苗字になって、夫婦になって、一緒に住むようになって、ふたりの新しい生命も芽生えて、誰かのために誰かと一緒に「生きる」ということが、未来と希望のピースのひとつでもある。
「気になるな」
「男の子でも女の子でも辰也くんに似て欲しいな」
「オレはに似て欲しいけど…あ、でも…うーん」
「どうしたの?」
「そうなったらきっと可愛過ぎるからどうしようかと思って」
「もう…」
「楽しみだね、オレたちの子」
今、この何気ない時間だってと過ごしているのなら、形はなくてもきっと数年後、数十年後。お互いの心に鮮やかに宿る宝物になる。
のおかげで生まれる幸せという名の宝物に、これから先もきっとたくさん巡り合えるのだろう。