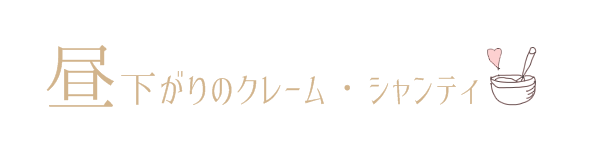|
クローゼットの中からお気に入りの洋服を出しては着てみる。そしてスタンドミラーの前で360度ターン。残念ながら無いに等しい脚線美を少しでも表現してくれるスカートやパンツを確かめたり、もちろん後ろのシルエットにだって気を配る。そんなことを何回も繰り返していたら、部屋の中はあっという間に服の海になってしまった。今は片付けている時間よりも、準備のために少しでも時間を割く方がきっと有意義だ。着ては脱ぐを散々繰り返し、ようやく決めた洋服たちに身をつつむ。それが済んだら今度はガラス製のローテーブルの上に小さなミラーを置いて自分の顔と向き合う。人並にファンデーションやリップくらいは纏って、少しでも自信をつけたい。ほんのり色づくグロスを丁寧に塗っていると、時計の針は思っていた時刻より10分も進んでいた。つけていたテレビ番組はいつの間にか違う番組に切り替わっていて、慌てて玄関に用意しておいたパンプスに足を滑らせる。玄関の扉を開けると清々しい外の空気。きっと、程良く漂っている雲と、眩しいくらいに輝く太陽のおかげだろう。スキップしたくなるほどの軽い足取りで待ち合わせ場所へと向かった。 「ごめん、俊くん…!待った?!」 「全然。っていうかまだ待ち合わせの5分前だし」 「そっか、良かった」 「…」 「え、何?何かついてる?」 「いや、に久々に会えて嬉しいなって思っただけ」 きっと、今の私の頬はチークなんて意味が無かったかもしれないくらいには、紅潮していることだろう。普段外出する時より少なくとも30分以上は準備に時間が掛かっている。だって今日は久々に彼とのデート。何日も前から楽しみにしていて、当日は何を着て行こうかな、なんてシミュレーションを何度もしていたはずなのに、当日になってやっぱり悩んでしまう優柔不断。彼の隣に並んで街を一緒に歩けるのなら、気持ちが高揚してしまうのはどうしようもない。 ここ最近、彼も私も忙しく過ごしていたため、ようやく都合が合った日曜日の午後。久しぶり過ぎてなんだか手に触れるのも躊躇ってしまうほど、初めてのデートみたいな感覚を味わう。けど、歩くのと当たり前のように自然に触れられて繋がれたふたつの手を見て、やっぱり付き合ってるんだ、なんて今更だけど人の温度が直に伝わり浸透してくることによって、心もじんわりと温かくなった。 「晴れてるし公園にでも行こうか」 「うん」 休日の公園というのは、こんなにも活気に満ち溢れていながらどこか落ち着いた雰囲気を醸し出しているものなのだろう。人がたくさんいるのにも関わらず、穏やかな時間が流れているミステリー。いや、きっと多くの人が日常の忙しさや迫り来る時間に怯えることなく、優雅な時を過ごしているからだろう。ひとりで読書している人や犬の散歩をしている人、それから家族連れや付き合いたてらしい恋人同士、老夫婦の仲睦まじい様子など、たくさんの平穏な時間が垣間見える。そんな平和な光景を双眸に焼きつけながら彼に寄り添うように歩いていると、ふと手が離された。温もりがどこかへ行ってしまい、代わりに風に覆われた手がどことなく冷たくて寂しい。 「ベンチ座っててちょっと待ってて」 そう言い残して彼がどこかへ行ってしまったので、近くにあった木のベンチに座って広い公園の芝生をぼんやりと眺める。芝生には先程とは少し違う人たちで溢れている。シートを敷いて座っている人や寝転がっている人、フリスビーやサッカー、バドミントンをしている人たちから凧揚げなんかをしている人もいる。子どもから大人までの多彩な笑い声をBGMにしながら、なんだかこの緩やかな空気と時間に同化して寝てしまいそう。単純に瞼が閉じきってしまうのを恐れたからか、それともこの情景を脳の中のアルバムに刻んでおきたいと思ったからか、きっと両方だろう。シャッターを切るように瞬きを何度か繰り返していると、頬に缶ジュースが当てられた。 「わ…ビックリした」 「ボーっとしてるみたいだったから」 「飲み物買ってきてくれたの?」 「うん。あとコレ」 「あ、クレープだ!」 「さっき移動販売車が見えたから買ってきた」 「ありがとう!一緒に食べよう」 ホカホカのクレープ生地に包まれたチョコレートがちょうど良い感じに溶けて、甘さが徐々に舌の上に広がる。彼にも差し出して食べさせてあげると、この甘さを共有出来たようで、彼の笑顔にわたしの口元も自然と弧を描いてしまう。 別になんの変哲もない時間。会話が多いわけでもない。周りからしたら面白みの欠片もない時間なのかもしれない。それでも、こうして太陽の下で、青空に包まれながら二人で並んで、肩と肩が触れ合う距離にいられる。それだけでも、私にとってはかけがえのない大切な時間。罰当たりにもそれをしばらく忘れていたような気がする。いつからか、この関係に慣れ過ぎてふたりで過ごす時間に特別胸を高鳴らせたりはしなくなっていたのだ。けど今日、久々に彼と会うために費やした時間だとか、こうして隣で過ごす時間だとか、彼に関わるあらゆるひとときがこんなにも楽しくて幸せで穏やかだったのかということを思い出すことが出来た。このただのありふれた日常が、とてつもなく平穏で幸せで、永遠にこのままでいたいと思ってしまうほどなのだ。 静かにこの時間を共有していると、不意に隣の彼から小さな笑い声が漏れた。 「どうしたの?」 「いや、不思議だなって思って」 「何が?」 「なんかさ、といると普通のことでも楽しいっていうか、幸せに感じるなって」 −それ、私が言おうと思ったのに。 彼に台詞を取られてしまった私の言葉は宙を漂っている。まさか彼も同じことを思っていてくれていたなんて、驚きと同時にたまらなく嬉しくて、言葉が出ずにただ彼の顔を見つめているだけ。愛しい人がいれば当たり前の日常が幸せで彩られる。私の双眸がゆらゆらと揺れて、きっと彼の表情を反射していることだろう。 「何?」 その優しい声音が穏やかに注がれると、私も見つめているだけでなく、ちゃんと伝えたくなった。昨晩ミスティローズに彩った爪を見て一呼吸置いたあと、彼の腕に手を伸ばし距離を更に縮める。なんだかより温かく感じるのは気のせいだろうか。彼の耳元で風が囁くように「私も」と答えた。
|