|
カクテルに入ったマドラーが響かせる音はひどく脳に響く。お酒のみならず、人の心を混ぜることも掻き消すことも誤魔化すことも出来る気さえするのは既に酔っているからだろうか。マドラーを回して氷がカラカラと鳴るこの音に耳を澄ませると、まるでこれからの宵を物語るBGMのよう。 今日は大学の友人同士、私の女友達と彼女の男友達がノリで開催したという、何とも単純な飲み会である。そして人数合わせに連れて来られたのが私、彼女の男友達に連れて来られたのが今ここにいる高尾くんである。彼はどうやら般教の授業で私の存在を知ってくれていたらしい。私はというと、申し訳ないことに何となく見かけたことはあるものの、彼の名前までは知らなかった。それでも男性陣ふたりが飲んで盛り上げてくれたおかげで、初対面でもスムーズに打ち解け、楽しい時間を過ごせている。 そして今、そんなほぼ初対面だった人間が二人きり。残りの二人はどこへ行ったのかと言うと、それぞれバイトがあるだの明日早いだので帰宅してしまったのだ。今思えばそこで解散しても良かっただろうに、こうして二人でも飲み続けているのは、お互いまだ何となく帰りたくなかったからだろうか。既に薄くなってしまった私のカクテルが、アルコール濃度を欲しているようにも見える。 「高尾くん、大丈夫?っていうか眠そう…」 「んーだいじょうぶ」 「たくさん飲んでたもんね」 「そーだっけ?ちゃんはお酒強いの?」 「うーん、普通じゃないかな。高尾くんは?強そうに見えたけど…」 「オレ?オレは…っつーかさ、」 アルコール慣れ、と言ってしまうと可笑しいかもしれないが、多分彼は普段あまり酔わないのだと思う。今日も潰れるという感じではなく、ほろ酔いで少し心地良さそうでもある。そういえば、最近気持ちよく酔った記憶が私にはあまりないかもしれない。自分自身を無意識にセーブしてしまっているからだろうか。いつからか、醉うことに怯えてしまった。アルコールにも、恋にも。今だって、そうだ。テーブルの上に突っ伏してしまった彼の頭を不意に撫でてあげたくなって、慌てて手をマドラーに移動させる。どうしてそんなことをしたくなったのだろう。自分を冷静に見つめ直すために、氷をカラカラと鳴らしてみたけれど、無意味だった。 「男ってさー、好きな人と飲むとすぐ酔っちゃうんだよね」 音を裂くように、彼の言葉だけが世界の中心に存在しているかのように響いてくる。目だけ覗かせた上目遣いは私の動きを止めるのに充分だった。マドラーを動かせていた手が止まり、カラカラと鳴っていた音が止むと、店内に流れていたBGMさえも一瞬止まったように感じるほど、頭の中にアルコールが回ったような感覚だ。聞こえるのは自分の心臓の音だけ。目の前にあるグラスの中身を一気に飲み干して空にした。溶けかかっている氷だけが残る。 「高尾くん…酔ってるね」 「ちょ…!そんな冷たい目で見んなって!」 ケラケラと笑う彼はやっぱり酔っているのだろう。先程は私の心臓を射抜くような目で見つめてきたというのに、随分な変わりようである。けれど、私が追加のお酒をオーダーする前に彼が私の分と自分の分をオーダーしていたところを見ると、やはり酔っていても本来持っている性分がちゃんと働くのは流石だと思った。 それから何杯か飲んだあと、時計の針はいつの間にかに驚くほど進んでいた。お互い適度に酔いがまわり、大学生活のことを中心に恋愛の話なんかもしたりした。 「帰んの?」 腕時計をちらりと見ると、脳に直接響くように入ってきた声音。腕時計を見ているから彼の表情は見えないはず。それなのに、高まっていくこの感情は時計の針と同じで止まることを知らない。「そりゃあ…帰るよ」と静かに返すとしばらくの沈黙。僅か数秒なのに、何時間にも感じてしまいそうなほど長く感じて少し不安になった。 「帰っちゃヤダっつったら?」 でも、そうやってまた人の顔を覗きこむように顔が自然と近づいてくるから、不安はどこかへ飛んで行った。不安なんかよりも、私と彼の酔いどこかに消えてくれたら良かったのに。嫌だ、と言われて何と答えるのが正解なのかが分からない。何も言えずにいると、手を引かれ彼がいつの間にかに支払い済ませてそのままお店の外に出た。再び手を取られて街灯に照らされる道をふたりで歩く。街灯なんかより、きれいな真ん丸の月明かりかまるでスポットライトのように私たちを照らすから、これでは何だか恋人同士みたいだ。 レンタルショップに行き、彼は黙々とタイトルを選びそのまま何本かのDVDを借りた。先程飲んでいる時に話題に出た「観に行きたかったけど、観に行けなかった映画」のタイトルがいくつか目に入る。そのまま再び夜道を歩くと、どうやら彼のマンションに着いたようだ。彼に掴まれた手を振りほどくことも出来ずにここまで来てしまったことはもちろん反省するが、複雑な思いが渦を巻く。 「あ、あの…高尾くん!?」 「ちゃん、もう終電ないっしょ?」 「そ、そうだけど」 「こんな時間まで付き合わせちゃったのオレのせいだし、せめて責任取らせてくんない?」 非常に頭の良い言い回しである。そんなことを言われてしまえば拒否しづらいと言うことを彼は理解しているのだろう。分かった、とこくりと頷くとそのままマンションのエントランスを抜け、彼の部屋に初めてお邪魔した。思っていたよりもキレイに片付けされており、それでも男の部屋もいうことを感じさせられて少し緊張してきた。同時に軽率だったかもしれないと少し後悔している。今更純情ぶるつもりなんて僅かも無いけれ「異性の部屋にのこのことやって来た」ということはやはりそれなりの覚悟を持たなければならない。けれど、どこかでそれを受け入れても良いと思っている自分がいるから、きっと私は今この場にいるのだろう。 途中のコンビニで買ってきたビールを飲みながら、レンタルしてきた映画を一緒に見る。まだ飲むのかと少し驚きはしたが、宅飲みだと思いっきり飲めるから良いんだよねと楽しそうに笑う彼につられて私も缶チューハイを買っていた。 「ねぇ」 「何?」 映画も中盤に差し掛かってきた。まさに青春、純愛。こういう映画を見ていると、もし今ここで彼と一線を超えてしまったら何だか自分がダメな女に思えてしまうかもしれないと思った。けれど、よくよく考えたらそれは自惚れかもしれないわけで、彼と関係を持つとは限らない。そんなことを考えながら予想外に面白くない映画をただ眺めていると、不意に声を掛けられた。 「襲ってもいー?」 「…え!?…そういうこと聞く!?」 「え、聞かなくて良いの?」 「高尾くん…酔ってるでしょ?」 「どっちでも良いからちゃんとちゅーしたい」 予想された展開ではあるものの、やはり少しは驚いてしまう。酔っているとはいえ、私に欲情してくれたのだろうか。言葉を濁していると、その時間も待てないかのように、彼の手がすっと滑らかに伸びてくる。後頭部を力強く引き寄せられ、気づいた時には口に少し苦い味が広がっていた。人生で初めてのキスではない。けれど初めてのキス以上にドキドキするのは、舌の上で踊る苦さのせいだと思いたい。 「やべー、ちゅーしただけでめっちゃ興奮してきた」 いつの間にかテレビ画面で繰り広げられていた青春、純愛ものの映画は画面から消されていて、代わりに彼に押し倒されている自分が黒い画面に反射して映っていた。なんて愚かな物語。でもその愚かささえも享受してしまうこの現実は不愉快ではなかった。 「ちょ、ちょ、せめてシャワーとか…!」 「そんなん良いって。つーかオレが我慢出来ないから無理」 「で、でも」 「じゃあ後で一緒に入ろーぜ」 彼を押し戻そうとするけれど、ビクともしないあたり流石男の人だと感じさせられる。おまけに彼はバスケをやっていたらしく、トップスを脱いだ彼の上半身は美しいほど締まっていた。女の私には無いオトコの部分に、余計心臓が激しく荒く鼓動する。 「責任、取ってくれる?」 くちづけを受け入れ彼を甘受したことが私の答えだったことは、言うまでもない。 朝目覚めると気怠さが一気に襲ってきた。爽やかな朝とは言えない。朝日が眩しい。おそるおそる横を見ると既に起きていた彼と目が合う。「おはよ」と違和感無く会話を交わした。床にぐちゃぐちゃに散らばった服を拾い集め、昨夜と同じ服を仕方なく着る。その間、彼はコーヒーを用意してくれるらしい。 「ちゃんはさ、良いの?」 彼とは反対側を向いて着替えていると、ふと後ろから声が聞こえてきた。反応して振り向くと、彼はコーヒーをいれながら喋っていたようで表情は全く分からない。インスタントコーヒーの香りが昨日のアルコールをかき消してくれるんじゃないかと淡い期待を抱いたけれど、どうやら違うらしい。 「オレと一夜だけの関係で」 薄くなってしまったアルコールは、混ざることによって濃くなるようだ。 |
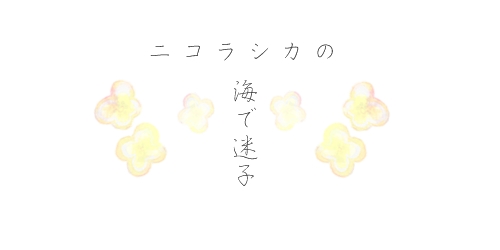
|
|