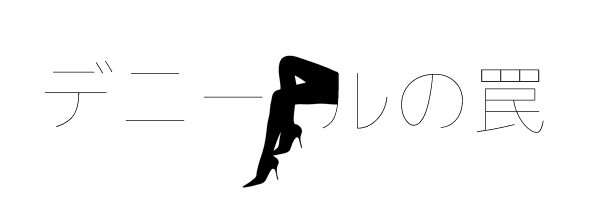「う〜ん…ないなあ」
「そんな前の映画観てどうすんだ?」
「ただ観たいの」
ジャンル別に50音順で整頓された棚にはひとつの美しささえ感じる。はひとつひとつゆっくりと目で追いながら目的のDVDを探す。太刀川はぼんやりと店内に流れている有線を聞きながら、DVDを探すを見ていた。暫くすると、ちいさな声で「あった」と言ったは首を45度ほど上へ傾け、視線は手の届かない上の方を向いている。欲しかった物を見つけ、やたらと輝きに満ちた視線をすぐさま太刀川の方に向け、目で訴えた。の心情を当たり前のように察した太刀川は何も言わずに棚へと手を伸ばし、が観たいと言っていたDVDを取り出した。
「ほら」
「ありがとー慶くん」
ご機嫌な様子でレジへと向かったは精算を済ませ、再びふたりで寒い夜空の下に出る。「さむーい」と言ったは太刀川の大きい手に自分のちいさな手を重ねると、太刀川は迷うことなく自然に重なったふたつの手を自分の上着のポケットの中に仕舞いこんだ。ひんやりとした冷たい風邪からは守られているため、外気にさらされているよりは充分に暖かい。けれど、そんな肌で感じるリアルな温度よりも限られた空間の中で繋がっているという事実のほうが何よりもこころを安心させてくれる気がした。
夜道をふたりで歩き、太刀川の住んでいる部屋へと向かう。この辺りはかなり静かで外灯も多くなく、夜に女ひとりで歩くのには躊躇いが生じるほどだろう。故に、は暗くなった夜にひとりでこの道を歩いたことはない。必ず太刀川が一緒に歩く。そのせいかはこの道をこわいと思ったことは一度もなかった。今日も、観たかった映画と恋人というふたつの存在に安定した嬉々を潜ませ、太刀川の住んでいる部屋に入る。
「やべ、ココア切れてるの忘れてた」
「えー!あ、でも牛乳ある?カフェオレなら飲めるよ」
「は相変わらずお子様舌だな」
「あまい方が好きだと言ってクダサイ」
この部屋にはしか飲まないココアの粉が存在していた。普段はコーヒーの瓶の隣に、太刀川には似つかわしくないココアが寄り添うように置かれている。ふたり並ぶと少し狭くなるほどのキッチンで、がお湯を沸かす。自分の家ではないけれど、太刀川の家に行くと殆どと言って良いほどがコーヒーなどの飲み物を準備するが、自身それを面倒だと思ったことはないし、太刀川自身も楽な上、の淹れたコーヒーの方が美味だと感じるのでいつからかそのようなスタイルに落ち着いていた。太刀川は待っている間のこの短い時間が密かに好きだった。けれど、ソファーで待ってる間が焦れったいのも事実で、太刀川はふたつの相反する感情に挟まれ複雑な心境に陥ることもある。その分、湯気がのぼっているカップをふたつ持って「お待たせー」とやわらかい笑顔でこちらへやってくるに、太刀川本人は一切自覚をしていないが、こころの奥底で何ものにも変えられないほどの安堵を覚えていた。
「あれ、このリモコンどうやって再生するんだっけ?」
「どうやってって…再生ボタンがあるだろ」
「ないよ」
「ないことないだろ」
「ほら、見て!」
どうやらカバーをスライドさせる仕組みだったらしく、持ち主である太刀川自身も暫く電源を入れる、チャンネル、音量を変える程度の機能しか使っていなかった為、再生までには些か時間を要した。映画が再生されると、はすぐに画面の中で繰り広げられるストーリーに夢中になった。現実ではありえないような物語はを虜にし、なかなか離さない。一方の太刀川はと言うと、最初から特に興味があったわけではないので大して集中していない。それよりも、ある一点が気になっていた。それはスカートの下から伸びているの脚である。防寒のため、黒のタイツを履いているの脚は無造作に太刀川の脚と触れ合っている。太刀川は思った。最後にの生脚を見たのはいつだったかと。季節のせいか、最近は今日みたいなタイツだったりパンツ姿だったりと脚の生肌の部分を見た記憶がない。そういえば、少し前まではお互い課題やバイトや任務にと時間に追われるように忙しく、会うことはあっても外食するくらいが圧倒的に多かったしが部屋に来ることはあっても数時間しか滞在しないという事態に陥りがちだった。はおそらく今日はこのまま太刀川の部屋に泊まることになるが、それは数ヶ月ぶりの事だった。
「」
「んー?」
映画に夢中のは生返事をするだけだ。然し、その間にも太刀川の中では黒いタイツに隠されたの脚が気になって仕方ない。肌が焦げるような紫外線を振りまく夏でさえ、その華奢な脚は確か白かった記憶がある。冬である今なら、雪とは比べ物にならないほど透き通るように白いのだろうとひとり勝手に脳内で理解を進めていく。何より、久々にゆっくりとした時間を持つことが出来たふたりきりの世界で、黒の布地によって隠されたすらりと伸びたうつくしい脚は、奥底に秘めていた感情を呼び起こすには充分なほどだった。そういえば、そのような行為も久しくしていない。
「タイツ脱がして良いか?」
またもや生返事で「んー…」と答えたが「えっ」と驚きの声を漏らし、画面に集中していた双眸を太刀川の方へと移動させた。太刀川はいつもと変わらない、普通の表情だった。そこにはきっと、タイツの下の脚を見たいという中学生みたいな下らない願望とを今すぐ抱きたいという男の衝動しかない。然し、女という存在は時に男より残酷で冷酷で非道でもある。顔を歪ませ怪訝そうな表情で「変態」と罵ったが、映画を停止させたはにこりと笑った。その笑みは少女みたいに無邪気なのにやたらと艶っぽく、太刀川の手を自然に脚へと誘導させるほどだった。
映画みたいにロマンティックなシチュエーションなんて欠片も存在していない。それでも、ふたりはフィクションの物語なんかよりずっとしあわせのようだ。