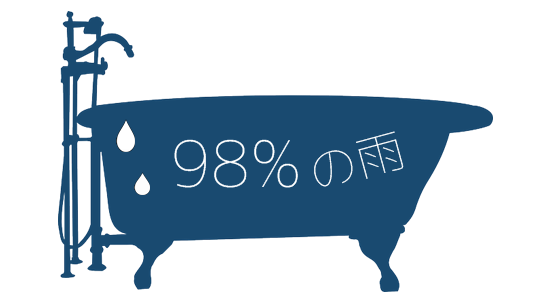オレンジとバニラのあまい香りがするボディソープがお気に入りで、一見相容れないように感じながらもお互いを上手く尊重しているこの香りをバスルームに充満させるのが好きだった。泡を肌にすべらせるだけで、さみしく汚れた身体だけでなくこころだってキレイにしてくれるような気がする。勿論、それはただの気休めだけど彼だってこの香りが好きだと言ってくれたし、わたしによく似合ってるとも言ってくれた。なのに、彼は一度だってわたしのボディソープを使ってくれたことがない。わたしの住んでるマンションに来て、セックスして、シャワーを浴びる。けど、いつもなんの香りもついていないシャワーで身体を軽く流しておしまい。わたしの香りなんて最初から存在していないかのように、わたしと過ごした時間なんて排水口に流すようにあっさりと消してしまう。
「太刀川くん」
「んー?」
「次はいつ来れそう?」
「そーだなー…とりあえず、また連絡する」
ベッドの上で未だ情事の余韻を引きずったままのわたしは、彼がシャワーから出てきて着替えているところをぼんやり見ていた。日頃怠そうにしていながらも、引き締まった上半身は流石だ。けど、今日この部屋に来た時となんら変わらない、服も髪も一切の乱れなく整える姿の彼を見るのがつらくて顔をシーツに埋めた。タオルケットにくるまってるわたしの頭を撫でて「」って名前を呼ばれて「風邪引かないうちに早く風呂入って寝ろよ」なんて、中途半端なやさしさがわたしの醜いこころを孤月より鋭い刃で抉る。「うん」とちいさく呟いた言葉はシーツに染みて滲んだ。そうして、いつも日付が変わらないうちに彼は帰る。泊まることは絶対に無い。情事後、彼が携帯を確認していたのを見てしまった。きっとこれから愛しい愛しい恋人のところへ行くのだろう。
怠い身体を無理矢理起こしてバスルームへ向かう。まだ彼が入って間もない為か、バスルームはあたたかかった。でも、やっぱり香りは一切存在してない。なかなか減ってくれないボディソープがなんだか惨めで、目元がじんわりと熱くなってきた。わたしもシャワーで誤魔化すようにすべてを流す。彼が、身体だけで生んだわたしとの愛を消してしまうように、わたしが彼へ抱く想いも消えてしまえば良いのに。
▼△▼△▼△▼△▼△
「さんさぁ、いつまで続けんの?」
「何が?」
「太刀川さんとの関係」
「よくこういう時に他の男の話出来るね」
「だって気になんだから仕方ねーじゃん」
適当に入った安いホテルのベッドの上で、後輩でもある出水くんは躊躇うことなく核心を突いてくる。よくもまぁセックスを終えたばかりの中、そんな事を軽く言えるものだ。後ろからわたしを抱きかかえるように座っている彼の髪が、耳に当たってくすぐったい。肌と肌が直に触れ合っている部分はあたたかいのに、いつだってこころは穴だらけで隙間から風がピューピュー吹いてる。あのボディソープを彼が使ってくれるまで、と言ったらわたしは馬鹿な女だろうか。本当は、いつも彼が帰る時に後ろから抱きついて引き止めたい。けど、そんなこと出来る度胸も勇気も自信も、かなしいことに欠片も存在しない。恋人以外の女と関係を持ってるくせに、恋人から連絡が来たら面倒くさそうにしながらも、任務の時よりも早いんじゃないかというくらいのスピードで恋人のところへ向かう最低でバカな彼がやっぱり好きで仕方ないのだ。その対象がわたしだったら、と何度思っただろう。そんな蟠りを埋めるために、わたしもまた別のところでぬくもりを探す。彼の後輩でもある出水くんを利用しているのだから、わたしはやっぱり悲しい女でしかないのだと思う。けど、出水くんを家に入れたことは一度も無い。今更な悪足掻きだということは理解してるし無意味だということも分かっているけど、それでも譲れない想いくらいわたしにだってある。
「ってか話全然変わるけど、」
「何?」
「やっぱさんの肌ってすげー触り心地良い」
「ありがと」
「さんって、」
首筋にくちびるが這い、肩をやさしく緩慢と撫でられる。出水くんは、わたしの肌が好きだといつも言う。すべすべで白くてやわらかいって、いつもやさしく撫でてくれる。この肌はね、お気に入りのボディソープで出来てるの。なかなか減らないから、たくさん使うの。
纏うものがいっさいないわたしの身体は、再び翻弄されていく。手の位置が下へ進むに連れてくすぐったくなってきたわたしは堪らず身体を回転させて、出水くんに正面から抱きついた。背中をやさしく撫でてくれる手も、こどもをあやすみたいに頭をふわふわと撫でてくれる手も、彼とは全然違うし、勿論体型も温度も何もかもが違う。けど、それで良い。
「ボディソープ何使ってんの?」
―秘密。くちもとに一度だけ三日月のような弧を浮かべて耳元でそう囁いたら、それが何かの合図のようにそのまま力強く押し倒されて、ベッドのスプリングがぎしりと軋む音がした。
この話はこれでおしまい。だって、わたしのお気に入りのボディソープを使ってほしいのは、たったひとり。太刀川慶だけだから。