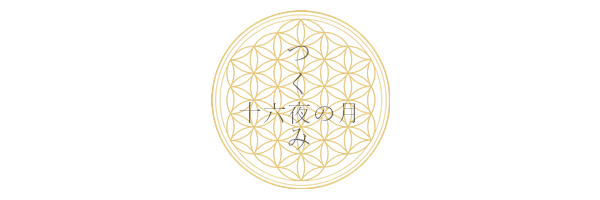
澄んだ静寂を浮かべる夜の中で、彼女を照らす頼りない街灯がスポットライトのように見えてしまった。遠目からでも分かるほど凛とした姿勢は、それだけで彼女自身を表しているかのように感じる。どこを見ているのか分からないその双眸には星が散りばめられているようにまばゆい輝きが灯っていて、けど同時にその虹彩に映るのは自分では無いのだと思うと、この夜の奥底に埋もれたくなってしまう。
「さん、お待たせしました」
「ううん、赤葦くんも部活お疲れ様」
澱みの無い空気を心地よく揺らすような声音の持ち主は、こちらに気づくとちいさな手をふわりと上げた。もし彼女と恋人同士であれば、その華奢な五指に自分の指を絡めて体温を共有出来るのに、なんて馬鹿みたいなことを考えてしまうほど、今日は疲れているのかもしれない。
木兎さんの幼馴染で恋人のさんに、こういう感情を抱くようになってしまったのはいつからだっただろう。さんはよく部活の練習を見に来ていて、その流れである日突然木兎さんに紹介されたような気がする。そうだ、アスファルトに一度散った桜の花びらが風で浅く舞う、春の終わりかけだった。廊下ですれ違えば挨拶をするような関係になっていて、いつだったか校内の各運動部主将やキャプテンが集まる部長会で帰りが遅くなる自分の代わりにさんを送って欲しいと木兎さんに頼まれた。「もちろん良いですけど、どうして俺なんですか?」「うーん……勘!」と答えがなんとなく分かっていた無駄な質問をしてしまったことまで覚えている。
「…さん」
「ん?どうしたの?」
初めてさんの名前を呼んだとき、自分の心臓音が鼓膜を揺らしたときのあの感覚は忘れもしない。「あ、スミマセン。木兎さんがそう呼んでいるのでつい」「…ううん、名前で呼んで貰えた方が嬉しい」そう言ったときのさんの笑顔が、単純な言葉になってしまうけど本当にかわいらしくて愛しいと思った。もう春はとっくに終わっていたと言うのに、うららかな木漏れ日を浴びて微睡みから穏やかに目覚めるような心地良さに、一瞬戸惑いさえ覚えた。
それから月に一度、部長会に出席する木兎さんの代わりにさんを送るようになった。その日が待ち遠しくなるのと同時に、絶対に報われない絶望さと共存していかなければいけない事実から逃げられなくなった。
「いえ、木兎さんってさんのこと大事にしてるんだなって思って」
「えー、そうかなあ」
「自分の帰りが遅いときは誰かにさんを送るように頼むとか、ちょっと意外でした」
「あー…それは多分昔のことを引きずってるんだよね」
「昔って…小さい時とかですか?」
「うん、前に光太郎と遊んでた時にわたしがちょっと大きい怪我しちゃって。それから大げさに心配するようになった気がする」
当然だけど、俺の知らないさんを知ってる木兎さんがひどく羨ましくなった。幼馴染なんだから、恋人なんだから、きっとそんなのたくさん在るって理解している筈なのに、醜い感情が湧いてくるのが誤魔化せない。さんのちいさい歩幅に合わせながら歩くことで長くいっしょにいれると思っているこの時間は、同時にいつも泣きたくなるような感情に襲われる。この矛盾の残酷さに溺れないように必死になってる自分が、時に滑稽にさえ感じた。
「そう、だったんですね」
「でもたまにこっちが心配になるんだよね」
「何がですか?」
「そんなにわたしのことばっか気にしてたら彼女とか出来ないんじゃないかって」
「…え?」
都合の良い幻聴が聴こえた気がする。あまりにも憐れな自分の鼓膜が、きっと音を間違って脳に伝達したのだろう。せまくなった脳内で必死に正しい処理をしようとするけど、さんの先程の言葉がずっと頭の中を揺蕩う。いや、淡い期待なんて抱いてはいけないというのは分かってる。けど、脳裏に一瞬でも浮かんでしまった希望みたいなものを簡単に消せるほど人間がまだ出来ていない。今することは期待が外れて直面するであろう現実から、自分を守る準備をすることだ。
「さんと木兎さんって、付き合ってるんですよね?」
「え、わたし?光太郎と?まさか!付き合ってないよ」
じんわりとした熱さが身体に宿る。現実に理解が追いついていないというのはこういう状態を言うのか。夢の中を彷徨っているような、不思議な感覚。けど、少し冷気を孕むようになってきた風がさんの髪をやわらかく揺らしているし、暗がりの中でも相変わらずまぶしく笑うさんは間違いなく現実だ。今まで手を伸ばすことさえ躊躇っていたけど、それが許されると解釈しても良いのだろうか。もちろん伸ばしたからと言って触れられるとは限らない。ただ、困らせてしまうだけなのかもしれない。それでも、永遠に宵闇から抜け出せないと思っていた感情がせめて星屑にはなってくれるかもしれない。
「あの、じゃあ言っても良いですか…というかもう言います」
「え、急にどうしたの赤葦くん?」
今まで勘違いしていた時間が無駄だったとは、決して思わない。面倒な思考なんてすべて無視して、しじまの隙間を縫うように自分の胸懐がこの夜にゆっくりと響いた気がする。
「好きです、誰よりもさんのことを好きな自信があります」
街灯の代わりに玲瓏たる月がふたりをスポットライトのように照らしてくれている気がする。そんなまぶしい光の下で、一瞬だけ見せてくれた頬の紅潮を見逃すわけがない。自然と触れ合えた手が今までの距離を無くすようにぎこちなく、それでも温度を共有するようにしっかりと繋がった。
