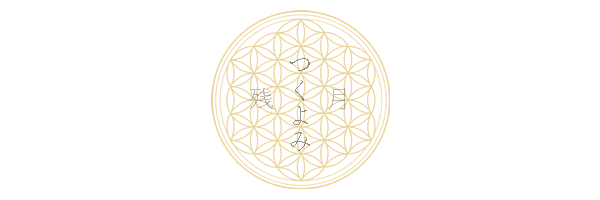
破れた夜を縫うように縋りつきたくなったのは、これが初めてではない。
付き合っていた彼氏に振られて、その度に連絡しては仕事終わりのやけ酒に付き合わせるわたしを、彼はどう思っているのだろう。軽い女、面倒くさい女、馬鹿な女。どんなに頑張っても自分を侮蔑するような言葉しか出てこない。自己嫌悪して、枯渇しかけているこころを潤すようにお酒を身体に入れるけど、まったく何も埋まらない。お酒なんてもので誤魔化せないこと、自分がいちばん分かってるくせにね。
「はい、ストップー。強くないんだからもうやめとけって」
「イヤ、飲んで何もかも忘れたい」
「忘れんのはいーけど、飲み過ぎは身体に悪いからダーメ」
社会人になってもう何度目か分からないこの非生産的なわたしの嘆きを、鉄朗はいつもただ聞いてくれる。けど、慰めてくれたことは一度も無い。なんだかんだやさしいくせにどうして慰めてくれないの?と聞けばいつも「今回も本気じゃなかったくせに」なんて酷いことを言う。わたしが一生懸命育もうとした純粋な恋をそんな冷たくて簡単な言葉で終わらせないで、と言いたいところではあるけど、自分でも決して否定できない気持ちがこころの奥底に眠ってるのは分かってる。
「…じゃあ鉄朗が忘れさせてよ」
「酔っ払いの言うことは聞きません〜」
「酔っぱらってないもん」
本気じゃないから本気になれないに決まってる。だって、わたしがいつだって傍にいたいって思うのは他の誰でもなく鉄朗だから。でもむかしから研磨と同い年のわたしは多分妹みたいにしか見てもらえてない。何度も諦めようと思っては他の男の人に縋りついてみたりしたけど、結局かりそめでしかなくて無理に繕った感情は相手も自分も誤魔化すことは出来なかった。研磨には何度も「はほんとにバカで不器用だね」と言われる。
酔いがゆっくりと全身を這って脳がうっすらと揺らめく。赤提灯系の大衆居酒屋を出ると、すぐに大通りだった。無意識に年上の男性を選んで付き合っていたからか、オシャレなビストロ系のお店だとかワインバーとかに行くことが多かったけど、ほんとは居酒屋で出されるビールだとか焼き鳥だって大好き。わたしがありのままの自分を出せるのは鉄朗くらい。自分をいちばん理解してくれてる人が自分を見てくれないだけでこんなに泣きたくなるなんて、今日のわたしはやっぱり酔っているのかもしれない。大通りを通る車のテールランプや信号がやたらと眩しくて、目を閉じたくなる。
「ほら、タクシー呼ぶから。自分の住所くらい言えんだろ」
「今日はひとりになりたくない」
「はいはい、そうやってオトナの男を誘惑しちゃダメですヨ」
「ひとつしか変わらないじゃん」
「…お前さ、俺のことまだお兄ちゃんみたいに思ってんの?」
「思ってない、思ったことない」
暗いコンクリートのアスファルトを見つめながら、鉄朗のスーツの袖をきゅっと掴む。どうせいつもこういうこと他の男の人にやってきたんだろうとか思われているのかもしれない。そろそろいつもみたいに説教タイムに入るだろうなと思いながらも、掴んでる手は離したくない。今日はなんとなく、そんな気分。背の高い鉄朗に、わたしが地面に吐露した言葉が聞こえているのかは分からないけど、暫くの間に沈黙が訪れる。賑やかな飲み屋街を彩る明るい笑い声だとか大通りを走る車のエンジン音やクラクションが聞こえる筈なのに、自分の心臓の音がいちばんクリアに聞こえるような気がして、静かな世界に放り込まれたような錯覚を起こしてしまう。
「どういうことになるか分かって言ってる?」
「うん」
「俺、多分チャンが思ってるほどやさしくも善良でもないんですケド」
「ちゃん呼びヤダ、知ってる」
「…後悔すんなよ」
袖を掴んでいた手が離されたかと思うと、いきなり指を絡め取られたので吃驚した。手をつながれたことの衝撃もそうだけど、それより子どもの頃以来に触れる鉄朗の手の大きさと安堵感に驚きを隠せなかった。その体躯に見合った骨ばった手は、想像していた通り大きくて、触れるだけで溶け合うみたいな心地よささえ感じてしまう。まるで恋人同士みたいに手がつながったままふたりでタクシーに乗り込み、そのまま流れるようにホテルへ向かった。わたしは鉄朗と一夜を過ごせるなら、場所なんてもうどこでも良いけどラブホでもビジネスホテルでもない、普通のホテルに連れて行ってくれたのは鉄朗なりのやさしさなんだと思う。きっと彼は、妹的存在でもある幼馴染の我儘なお願いを叶えるために、慈善的な感情でこれからわたしを抱いてくれるのだろう。愛が虚無だとしても、これから訪れるのが寂寞だらけの時間だったとしても、わたしはそれ以上求めたりしないから。
「どうした?もっとこっち来いって」
「う、うん」
ホテルの部屋に入り扉が閉まると、後ろにも前にも進めなくなってしまった。あんなに望んでいた展開だったのに、今更怖気づいてしまう。だってきっと、もう今まで通りの関係でいられることは出来なくなるから。今思えば、現在の関係性を失うのがこわくて素直になれなかったのかもしれない。絨毯に埋まるヒールを履いた脚が、ゆっくりと鉄朗の元へと向かう。スーツの上着を脱いでネクタイをベッドの上で緩める鉄朗が、なんだか別の人みたいに見えてしまった。隣に腰掛けると、シーツの皺が余計に波を打つ。
「今更やめてって言われても止めらんねーから」
「うん、言わない」
頬を撫でる手があまりにやさしくて眩暈がしそうになった。勘違いしてしまいそうになるから、そんな繊細な手つきで触らないで欲しい。そんな傲慢なこころとは反対で、ゆっくりと重ねられたくちびるは何もかもを享受してしまう。離れたかと思えばさみしいと思う暇もなく、すぐにまたくちびるが重ねられてほのかにお酒の味が舌の上に広がる。火傷しそうになるほど熱いのは舌なのかこころなのか、どちらか分からないけどこんなに心臓がときめくのなら今日が最初で最後の夜になって良いとさえ思えた。失うものが大きい行為になるかもしれないけど、まがいものみたいな夜かもしれないけど、わたしにとっては今この瞬間が最高にしあわせでうつくしい想い出になる。朝なんて来なくて良い、今この瞬間を永遠にしたい。そう思いながら、長らく続いたわたしの片想いは、今宵おしまいを迎える。
▲▽▲
目が覚めると、寝返りを打ったシーツは冷たくて、そこには誰もいないことを感じさせられた。予想はしていたので寂寥感のようなものは皆無に等しい。怠い身体を起こすと、まだ明るくなりきれていない空がカーテンの隙間からうっすらと見える。くちづけを交わしただけで満たされて、そこから先の記憶はあまり無い。着衣の乱れはほとんど無くて、きっと鉄朗が着せてくれたのだろうと思った。まるで、何事もなかったかのように巻き戻したかったのかもしれない。わたしにとっては夢みたいな時間も、きっと彼にとってはなんでも無い時間だったのだろう。
「お、起きた?早起きじゃん」
「…え?!な、なんでいるの?」
「いたらダメー?」
「帰ったかと思ってた…」
「俺そこまでひどいヤツに思われてんの?」
シャワーから出てきた鉄朗はいつもの笑顔で、ある意味何事もなかったかのような顔をしてベッドに腰掛けて髪をバスタオルで拭いている。わたしが思わずまばたきを繰り返していると、鼻をつままれて「アホ面」と意地悪な笑顔で言われた。予想していなかった光景に戸惑いを隠せずにいると、立ち上がった鉄朗がカーテンを思いっきり開ける。
「外、散歩でもすっか」
「え?っていうか今何時…って朝の5時?!」
「ほら、用意しろ」
顔を洗って歯を磨いて、簡単に身支度を済ませて外に出ると当然人はほとんど歩いてなくて、まだ明るくなりきれてない空がやたらと幻想的に感じた。朝特有の空気が、朧気だったわたしの頭をゆっくりと鮮明にさせる。前を歩いている鉄朗に着いていくと何処かの公園のようで、ふたり並んでベンチに腰掛けた。公園のベンチに座るなんて何年ぶりだろう。むかしは足をプラプラと浮かせて楽しんでいたのに、今はもう当然地に足が着く。自分の感情を誤魔化すためにフラフラと彷徨わないで、いい加減落ち着かないといけないのだと、改めて思わされた。
「あー…あのさ、」
「ごめん、昨日のことだよね」
「ウン、まあ」
「色々ごめんなさい…しかも着替えさせたりまでしてくれて」
「いや、あの後爆睡されたからあれ以上は何もしてないけど」
「え?」
慈しむようなくちづけに恍惚として、そのまま酔いしれるように無我夢中になって記憶を落としたかと思っていたけど、どうやらあれ以上の行為はなかったらしい。複雑な感情が生まれてしまう。だって、中途半端にこうなってしまった以上、きっと鉄朗とこうして普通におしゃべりするなんてこと、もう出来なくなる。どうせ今までみたいな関係でいられなくなるのなら、せめて嘘でもいいから愛の真似っこをする時間を持ちたかった。色々な感情が交錯して、すこしだけ目が潤みそうになる。我慢するように両手を太腿の上で丸めていると、包み込むように鉄朗の手が上から重ねられた。
「まあ曖昧なままとああいうことしたくなかったし」
「曖昧なまま?」
「我慢できなくてキスはしちゃったけど、俺も多分お前とおんなじ」
いつもの余裕綽々な感じでもなく、揶揄うような雰囲気も一切ない、まっすぐな鋭い目がわたしを射抜く。「お前が素直になれないこと、俺が一番分かってる筈なのにな。にあんなこと言わせた俺がダメだわ。いい歳して情けねーな」なんて自身を嘲笑しながらこの空にひとりごとを零すように言っているけど、思考回路が追いつけていないわたしはその言葉に対してなんて返せば良いのか正解が分からなかった。
「昨日のお願い聞いたから俺もいっこ良い?」
「え…な、なに?」
「もう本気になれない男なんかと付き合うな」
「…でも誰でも良いから誰か傍にいてくれないと、つらくなる」
「あー…うん、ごめん。やっぱちゃんと言うわ」
もう話しかけないで欲しいとか関わんなとか、そういう切り離されるようなお願いだったらどうしようと、数秒の間に自分のせまい脳内で必死に考えてた。今までもやけ酒に付きあってもらってる時に「もうそんな男と付き合わなきゃいーじゃん」と言われることはあったけど、こんなに強い意志を孕みながら言われたことはない。そもそも鉄朗がこういう風に何かを制限するようなことを言うのを、初めて聞いた気がした。
次は何を言われるのだろうと、不安と緊張で心臓がうるさくなる。ほんとは、もうこういうのに付き合わされるの面倒だから誰彼構わず付き合うなと言いたかったのを、遠回りの言葉で言ってくれたのかもしれない。今まで自分の感情を誤魔化して、他人も好きな人も巻き込んできた罰を受ける覚悟は出来てる。傷つくなんて図々しい。それなのに、告げられるであろう言葉がこわくて、ふたつの目はじんわりと熱くなっていく。
「俺、お前のこと好き。むかしからずっと好き。俺と付き合って」
明確に紡がれた言葉は、霞みがかっていた暗い世界をゆっくりと眩しく鮮明にさせていくような気がした。響いた言葉を疑ってしまうほど、予想していなかった言葉が降り注ぐ。けど、お酒も抜けている筈なのにほんの少しだけ頬を赤くしている鉄朗に、初めて愛しさのような感情を抱いて、からっぽになりかけていたこころが温かさで満たされていくような感覚が、間違いなく現実だと教えてくれる。
「わたしも好き。鉄朗以外、本気になれない」
A.M6:00前、まだ暗いけどどこか明るい空に残る月をスポットライトにして交わした静かなくちづけが、恋人のはじまりを告げる。綻んでいた夜の向こう側に、澄んだ朝が待っていた。
