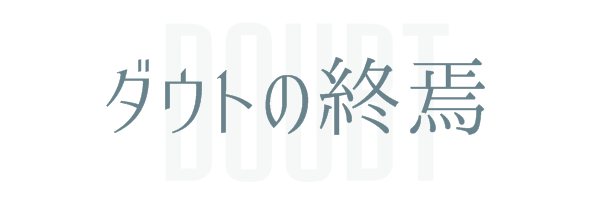高校生になってからすぐ始めたスーパーのバイトも、もうじき2年になる。最初は単純にお小遣い稼ぎのつもりだけでやっていたけど、レジで常連さんとお話したり逆に「ありがとう」と言ってもらえる事もあったりと接客業と言うのは難しい分、楽しいとも感じるようになっていた。
「お疲れ様です、さん」
「あ、烏丸くんお疲れー」
ひとつ年下のバイト仲間である烏丸くんは、年齢の割にとても落ち着いていて礼儀も正しく、おまけにその見た目の良さからファンがいるという噂もあるほどだ。他を寄せつけないようなキレイな黒髪とその凛とした雰囲気に最初は勝手に気圧されてしまってそんなに会話を交わせなかったけど、彼とはシフトが重なることも多く、気づいたらよく話す間柄になっていた。今日の烏丸くんはわたしより15分ほど遅いシフトだったらしい。バイトを終えて既にいつもの学ランに着替えていた。大人っぽくみえるけど、こうして制服姿を見ると本当に高校生なんだなぁと思って少しだけ安心する。
「さん、もう上がりすか?」
「うん、そろそろ帰ろうかなって」
「じゃあ途中まで送ります」
「ありがとー」
社員専用の裏口から出ると、空はもう真っ暗で夜を告げていた。烏丸くんと帰るのは別に今日が初めてというワケではない。家の方向が途中まで同じであるため、シフトが重なったり上がりが近い時間帯になると一緒に帰ることがよくある。落ち着いている佇まいのせいか、あまり喋らない人なのかと思いきや、無口というワケではなくむしろ穏やかな時間を過ごせる気がする。加えて、さり気なく道路側を歩いてくれたりと、この年齢にして既に紳士的な部分も持っているようだ。人気があるという理由がよく分かる気がする。烏丸くんと一緒に帰るのは楽しい。
「さん、知ってますか?」
「何を?」
「俺たちがバイトしてるあのスーパー、来月で閉店するらしいすよ」
「え…うそ!じゃあわたしたちも働けなくなるってこと?!…どうしよ、烏丸くんどうするの?!」
「まあ嘘ですけど」
まるで風が吹くらい当たり前に、さらりと嘘をつく。よくもまあそんなに思いつくなと言うほど烏丸くんは嘘をつくのだ。人を傷つけるような嘘は言わないけど、その嘘の真意はポーカフェイスから何ひとつ読み取れない。ただ「嘘つき!」とついムキになって言ってしまうと、いつも小さく笑ってる気がする。その表情にやたらと心臓がドキドキさせられて、その後の言葉は結局いつも続かない。
「さん、知ってますか?」
「知らないよ!何?!」
「俺がさんのこと好きってこと」
先程騙されたら警戒心と悔しさから、つい口調が強くなってしまう。軽く聞いて、今度はわたしがその嘘をさらりと流そうと秘かにリベンジを企んでいたのに、暗い夜の帰り道で周りの音はすべてシャットダウンされて、烏丸くんの言葉だけがやたらと澄んで聞こえてしまった。三門市の夜はこんなに静かだったのかと疑ってしまうくらい、烏丸くんの言葉がわたしの心臓に響いてくる。予想外の言葉にわたしの頭と心臓はオーバーヒートして、さらっと流すどころではなくなってしまった。けど、いつもみたいに信じるわけにはいかない。信じていつもみたいに「嘘ですけど」って言われたら、きっとわたしの心はしくしくと泣いてしまうだろう。
「嘘はよくない!」
「嘘じゃないです」
「もう騙されません」
「っていうかさん、なんで泣きそうな顔してるんすか」
両方の目頭が熱を持っていて、自分でも泣きそうな顔をしているということはよく分かる。だからと言ってそれを指摘しないで欲しい。烏丸くんは、きっとわたしがどうして泣きそうな顔をしているのか知っているはずだ。わたしも、どうして自分が泣きそうな顔をしているのか本当は分かっているはず。先程の言葉は「嘘」だと言われたら傷つくなんて、そんなの小学生でも分かる簡単な答えだ。
「だって、誰だって騙されたら嫌に決まってるじゃん…」
「そうすか?」
「え、嫌じゃないの?」
「俺、さんになら騙されてもいいと思ってますけど」
まあ今回は嘘じゃないですけど― そう言うと急に手を握られて、烏丸くんの手が思っていたよりも男の人の手だったことに動揺した。そのまま導かれるように烏丸くんの胸に手を当てさせられると、心臓のドクドクがうるさい。おまけに、わたしの手のひらを伝ってわたしの心臓にまで伝染してしまったじゃないか。この静かな街で、ふたつの心臓の鼓動が魔法みたいに重なって小さな演奏会みたいになってる。
「嘘じゃないの、分かりました?」
首を縦に振って頷くと、相変わらずのポーカフェイスなのに少年みたいな表情を見せられたような気がして、心臓が震えるほど熱い。そのまま重なった手は、離れることを知らないように繋がったままだ。まるで星が月に寄り添うみたいに、わたしたちの距離も静かに輝いてる。