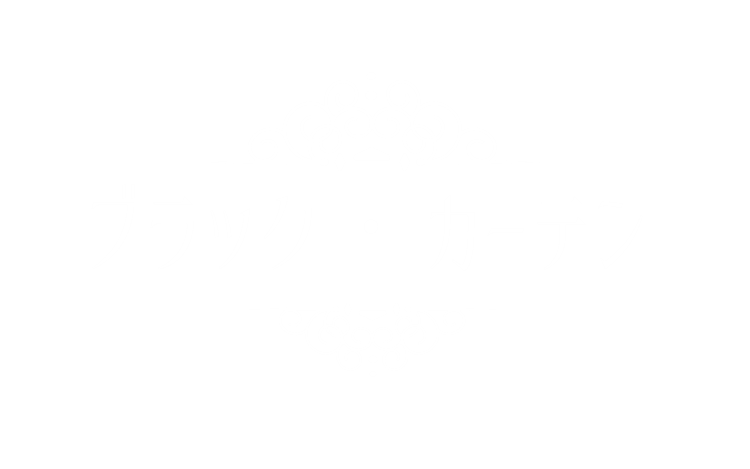重たい雲が浮かぶ空から、雨が降りそうに思えたのは彼女の表情のせいだろうか。委員会の仕事で校内のいくつかの花壇を見回っていると、何かを我慢するように華奢な肩を震えさせ、なかなかその場から動こうとしない彼女の後ろ姿を見つけた。彼女の先には遠ざかる仁王の後ろ姿も見える。仁王に何かを言われたのだろうか、おそらくではあるが男女の修羅場的な光景に偶然にも遭遇してしまった居心地の悪さから、早くこの場を離れたくて仕方がない。それなのに動くことが出来ないのは、彼女のそのさみしい後ろ姿が息を飲むくらい苦しくて美しくて、呼吸を忘れそうになるくらい今のこの瞬間を壊しくないと思ってしまったからだ。
彼女の足元にだけ、雨が降ったみたいに地面が滲んでいた気がした。
▽▲▽△
制服はブレザーからワイシャツへと移り変わり、校庭の花壇にある紫陽花たちは、鮮やかに彩り始めた。肌にまとわりつくような少し湿った空気と雨のニオイが季節を感じさせる。終礼が終わって、委員会の仕事でもある清掃の見回りがてら花壇を見に行く。春に植えた種のいくつかが、うつくしく咲き始めている。ジニアの花がカラフルに咲いている花壇の前で、ひとり座って花を見ている人間がいた。
「あれ、確か仁王の…」
「あ、幸村先輩。こんにちは、です」
「こんにちは。こんなところでどうかした?」
「キレイに咲いてたんで思わず魅入っちゃいました」
まばたきもせず、ただ真っ直ぐジニアの花を見つめていたひとつ年下の仁王の恋人は、俺が声を掛けると微睡みの中から覚めるみたいに勢い良く立ち上がり、礼儀正しくお辞儀をした。「よく俺の名前を知ってたね」と聞けば「この学校で幸村先輩の名前を知らない人はなかなかいないと思いますよ」とやわらかい笑顔で返された。彼女のこの笑顔を見るのは2度目である。1度目は美化委員が年に1回主催している雑草取りや種まきのボランティアに、彼女がたまたま参加していた時だ。誰よりも楽しそうに手伝ってくれていたのが印象深くてよく覚えている。だからテニス部の練習を見に来たときはすごく驚いた。同時に仁王の彼女だということにも驚いたし、少し違和感を感じた。こんな事を言っては2人に失礼かもしれないが、たまに練習を見に来てる彼女はあまりしあわせそうに見えなかったし、この前の光景だってかなしそうな彼女の表情しか見ていない。
「これから新しい種を植えようと思ってるんだけど良かったらどう?」
「え、良いんですか?」
「うん、前もボランティアで来てくれたことあるよね?」
「よく覚えてますね。でも本当に良いんですか?」
「むしろこっちとしては手伝ってもらえたらありがたいよ」
「嬉しいです。ぜひお手伝いさせて下さい」
俺と仁王の身長はほぼ同じ。仁王と話す時も今と同じくらいの角度でその双眸を下から向けているのだろうか。そんなよく分からないどうでも良いことを一瞬思ったけど、こころの中がぐちゃぐちゃになって決して気分が良いものではなかったのですぐに思考を停止させた。そのせいか分からないけど、種を渡す時に彼女の手に直接触れるのを躊躇ってしまって、袋のまま彼女の手にちいさな種をひと粒ずつ落とした。汚れてしまうことなんて構わず土に触れる彼女の手は、とても純粋で美しく見える。
「テニス部の部長、大変ですか?」
「そんなことないよ、と言いたいところだけど癖のある人間ばかりだからね」
「ふふ、確かに」
「そういえばさんは赤也と同じクラスだっけ?」
「はい、クラスでもよく部活のこと話してますよ」
外見からは何か目立つような「特別」を持っているようには見えないけど、彼女の話し方や纏っている雰囲気は不思議と心地好い。ちいさく笑う表情とかやわらかい声だとか、彼女と過ごしている今のひとつひとつの場面が、額縁に飾られた絵画のようにうつくしく穏やかに感じる。けど、もうひとりの冷静な自分が彼女に対してそんな感情を抱いてはいけないと警鐘を鳴らしているのも事実だ。だから、故意に仁王の名前を出すことでこの感情を枯らさなければならない。
「最近は試合が近くて練習もいつもより多いから、さんには申し訳ないと思ってるよ」
「どうしてわたしに申し訳ないんですか?」
「仁王とあまり会えないと思って」
「…いえ」
「ごめん、余計なお世話だったかな」
「あの…わたし、仁王…先輩の」
ほんの少し眉をさげてこちらを向いた彼女の頬には土がついていた。土がついているよ、とひとこと言えば良いのになかなか言えない。彼女も言葉が詰まってしまったのか、それとも言葉を自ら潰したのか分からないけど、その先は何も言えない様子で、しばらくの静寂がふたりに訪れている。無音の世界のように思えて彼女の頬に手を伸ばそうとしたけど、後ろからやたらと鮮明に聞こえた足音がそれを阻んだ。枝を踏んだだけのちいさな音が、何もかもを壊すような、そんな音に聞こえた。
「」
「…っ、仁王、先輩…こんにちは」
「何じゃ、ずいぶん他人行儀じゃの」
「…幸村先輩の前なので」
「不思議な組み合わせじゃの」
「美化委員の仕事をたまたま通りがかったさんに手伝ってもらっててね」
「部活前に委員の仕事とか幸村も大変じゃな」
相変わらず背中を丸めた猫背でポケットに手を入れて何も考えていなさそうな雰囲気を出しているのに、その何もかもを見透かしてるような仁王の笑みは味方だと心強いけど、そうじゃないと警戒する以外の何ものでもない。この男だけは本当に厄介だ。そして仁王が現れたと言うのに、仁王の傍へ行かずひたすらその場でアスファルトを見つめている彼女にも違和感を感じた。居心地の悪い空気が肌に刺さる。気を利かせて何か言うべきかと必死に思考を巡らせているけど、何が正解なのか分からない。
「、ちょっとこっち来んしゃい」
「え?」
呼ばれた彼女は俺の横を通り過ぎ、まるで子猫みたいに仁王の元へ小走りで駆け寄る。仁王は躊躇うことなく、彼女の髪を耳にかけ、頬にやさしく触れた。テニスをしている時の仁王しか知らないせいか、そんなにやわらかい所作をするなんて知らなかった。ほんの一瞬ではあるけど目を奪われたような感覚になってしまい、けど同時にすぐに目を逸らしたくなった。きっと、醜い羨望のようなものが心に芽生えてしまっているのかもしれない。仁王の顔と彼女の後ろ姿しか見えないけど、きっと彼女の頬は赤く薄づいているのだろう。ようやく仲睦まじい2人の姿を見れたという安堵感と、口には出したくない情けない虚しさの2つが渦を巻いて、よく分からない感情に埋もれそうになる。
「ほっぺに土ついとった」
「え!?うそ!?恥ずかしい…」
「幸村」
仁王は彼女の肩を掴んでくるりと反転させ、急に俺の名前を呼んだ。やはり彼女の頬は紅潮しており、それが恥じらいくら来るものなのか仁王に触れられたからかは分からないが、そんなことを考える時間さえ奪われるように仁王は彼女の腰に手を回して距離を縮めた。急に仁王に後ろから抱き着かれた彼女がちいさく「わ…」と言ったけれど、そんなことお構いなしに仁王の口元は三日月よりも妖艶な弧を描いている。俺と仁王との付き合いも数年経つ。仁王がそういう笑みを浮かべている時がどんな
時かはもう分かってるつもりだ。
「かわいいじゃろ、俺の“彼女”」
その台詞には、迷いがひとつも存在していなかった。苦しくなるから「仁王の彼女」と言いたくなかった俺と、自信がなくて「仁王の彼女」と言えなかった彼女を置いてけぼりにして、堂々と容易く「彼女」と言えてしまう仁王にきっと俺たち2人には同じ感情が生まれていたと思う。けど、だからと言って2人とも何かを変えることなんて出来ない。寂寥感に苛まれた雨なんかじゃ、花はうつくしく咲けないのに。