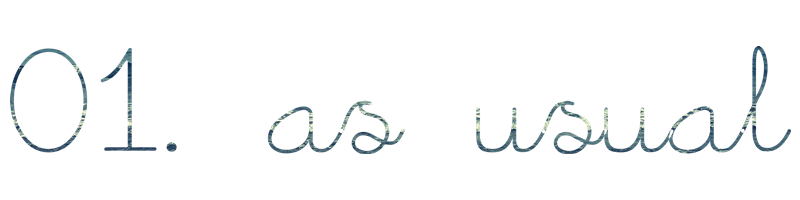
カーテンの細いすき間からこぼれた光で起きる朝は嫌いじゃない。目覚まし時計が鳴り響く前に身体を起こしたはいつものようにひとり身支度を済ませ、隣の家のチャイムを鳴らす。
隣の家の朝はいつもにぎやかであたたかい。祖母と両親、そしてちいさな弟ふたりに幼馴染である丸井ブン太が作り出す明るくてやわらかい雰囲気がは好きで、朝はほぼ毎日と言っていいくらいお邪魔し、いっしょに朝食を食べている。幼馴染である丸井が部活の朝練でいない時もあるが、そんなこと関係なくはこの家の明るさが好きだった。自分の家が暗いと思っているわけではないが、両親は仕事で忙しく不在がちなため、には隣の丸井家が眩しく映っていたのだ。そんなをちいさい頃からよく知っているからこそ、丸井家の人々もをいつでもやさしく迎える。がまだちいさい頃は両親の帰りが遅く、丸井家で夕飯を一緒に食べることもよくあった。
「え、宿題なんかあったっけ?」
「あったよ、英語のプリント」
「…げ!!俺やってねぇ!」
「やっぱり…でも今から急いでやれば多分間に合うと思うよ」
「今日はゆっくりと朝飯食えると思ったのに…」
「そのオレンジはわたしが食べといてあげるから宿題頑張って!」
「どさくさに紛れて俺の取んなって!」
そんなふたりのやり取りを大人たちはやさしく見守り、ちいさな子どもたちはおいしそうに朝食を食べている。丸井が無事に宿題を終えた頃、は食後の紅茶を飲み終わり「行ってきます」とふたり声を揃えて家を出た。
▲▽▲▽▲
学校に行くまでの途中に微かに聞こえる波の音や、凛とした音で鳴く鳥の声、通り過ぎる人々の会話をBGMにして今日もいつも通りの道を歩く。ほんのりとした海の香りが鼻をかすめると、学校まであともう少しだ。ふたりと同じ立海の制服を着た学生たちがたくさん歩いていて、丸井に「おはよう」と声を掛ける人間が増えてくる。丸井は全国ナンバー1と呼び声高い立海のテニス部に所属しており、おまけに数少ないレギュラーだ。ルックスや人当りの良さも含めて丸井に惹かれる人間は男女問わず多い。はテニスをやっていないため、丸井のすごさを今ひとつ理解していないが、丸井がテニスをしているところを見るのはなんとなく好きで練習や試合も応援に行くことがある。
ふたりが他愛もない話をしながら歩いていると、何人かの生徒がブン太に「おはよう」と後ろから声を掛けながら追い抜いて行く。途中、丸井の部活仲間でもあるジャッカルが通り過ぎ「お前ら余裕だな」と言って前を走って行った。いつも女子同士が楽しそうに話していたり、男子同士が朝からバカやってたり、付き合いたてのカップルであろうふたりが微妙な距離感で歩くような、そんな穏やかな毎朝の光景が今日はすこしだけ違うとはようやく気づいた。
「あれ、ちょっと待って…何でみんな走ってるの?」
「俺たち…いつも通りに家出たよな」
「…あー!!わたしの腕時計…止まってる」
「やべえ、今何時だ?!」
「とにかく走ろう!」
ふたりのようにのんびりと歩いている人間は誰ひとりいなかった。遅刻しかけているということに気づいたふたりは当然ダッシュをするが、全国強豪の運動部レギュラーである丸井と運動部でもなんでもないの差は歴然だ。の脚とローファーは悲鳴を上げ、ペースがだんだんと落ちていく。学校まではあと少しだが、普段走ることをしないにとってはその少しがとても遠く感じられた。
「ブン太、わたしのこと置いてって良いから先行って…」
「バカ!お前のそっちの荷物持ってやっから走んぞ!」
まるで何かから逃げるようなどこかのサスペンス映画みたいなやり取りをし、チャイムが鳴る前に校門へ辿りついた。校門には丸井と同じ部活仲間で風紀委員会に所属している真田が立っており「丸井!こんなギリギリに来るなんてたるんどるぞ!」「間に合ったんだから良いだろい」という会話が成されていたようだが、すでに疲れ果てているの耳にはあまり入ってこなかった。何とか予鈴が鳴る前にふたり揃って教室へ辿りつく。丸井とはクラスも同じであり周囲はふたりが幼馴染だという関係を知っているため、いっしょに登校をしても冷やかすような人間は誰ひとりいない。自分でもびっくりするくらい息を切らしているは友達に朝の挨拶をすることさえも出来ず「ギリギリだったね」と声を掛けられても軽く手を上げるくらいしか出来ないようだ。代わりに丸井が「危なかったぜ」などと答え、ようやく着席する。
「相変わらずじゃのう」
声を掛けてきたのは丸井と同じ部活仲間であり、の隣の席でもある仁王雅治だった。幼馴染の友人であり隣の席という、ふつうのクラスメイトよりは近い存在であるはずなのに、どうにもは仁王をよく理解出来ていなかった。同い年なのに周りの男子たちより少し大人っぽく、何を考えているのか分からない。そんなところをミステリアスで素敵だという女子はたくさんいるが、には躊躇いしか生まれなかった。もう一歩、あと一歩仁王に近づいたら自分の中の何かが変わってしまうような気がして、もうそこから抜け出すことは出来ないような気がして、目には見えない境界線のようなものを自ら引いていた。
「相変わらずって、仁王くんの方がいつも遅刻しそうじゃん」
「そっちじゃなか」
「え…じゃあ何のこと?」
疑問を投げかけても笑ってるだけで何も答えてはくれない、かわされる。その度に相反する感情がこころの中で交錯するようで、その時に生まれる感情を何と呼べば良いのかは分からなかった。
行き場をなくした双眸は、教室の窓枠に映るちいさなせまい世界しか見えていない。