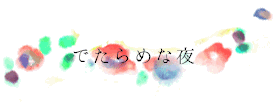朝日に誘われるかのように自然と目が覚めた。眩い光に彩られた朝、目が覚めたら愛する人が隣にいるという幸せそうな光景を何度夢に見たことだろうか。苦手な朝もそれだけで好きになれるのではないかと、少女時代の頃の私はよく希望を抱いていた。けれど、所詮朝は苦手なままで、そんな光景は夢のまま。叶わなかった夢ではなく、幻想を抱きすぎた夢。
相変わらず重い身体を無理矢理起こし、朝の準備に入る。私の隣で健やかに眠っている彼は今もまだ目を閉じたままだ。彼が起きないよう、一通りの身支度を済ませ、軽い朝食を作り、鍵を置いて家を出る。置き手紙を書こうと、ペンを走らせながら書く字は丁寧を心掛けているが、感情は何も込めていない。恋人と一緒に寝て、朝に目が覚めたら隣に恋人がいて、恋人の寝顔を見て、恋人のために朝食を準備して、恋人のために起こさないように家を出る。この場面だけを切り取れば、他人からしたら幸せな朝なのかもしれない。でも、私にとっては間違いなく幸せでも不幸でもない。ただの平凡ないつもの一日なのである。
「…?」
「おはよ」
どうやらこの置き手紙は必要なくなったらしい。けれども、まだ夢の中を彷徨っているような彼は枕に顔を埋めながら、なかなか身体を起こそうとしない。昨日はだいぶ遅かったのだろう、それも仕方ない。一応彼の帰宅を待ってはいたが、あまりにも遅いため私は彼を待たずに先に寝た。昨夜勝手に用意した彼のための寂しい夕飯は、今朝も相変わらず冷たいままだった。
「どっか行くんスか?」
「うん。ってか自分の家戻るだけだけど」
彼とは一緒に住んでいるわけではないし、半同棲というわけでもない。昨日はたまたま友人と遅くまで遊んで、自分の家に帰るより彼の家に行く方が近いため、泊まっただけだ。私としては家が二つあるようで楽である。こういうことは今までにも何回かあったが、彼に咎められたことはもちろんない。利便性だけを求めて勝手に上がり込んだとは言え、合鍵を渡してくれているのだから、彼はそんなつまらないことに興味を示したりはしないだろう。
「ふーん」
「…服離して。伸びちゃう」
「がちゅーしてくれないと離れないっス」
帰ろうと思っても彼の指が私の服に縫い付けられたかのようにくっついており、離してくれる気配がまるでない。「ちゅーしてくれないと」なんて、まるで子犬のような目で見てくる彼に憎らしさを感じつつも、仕方がないのでキスしてやった。途端、先程までの気怠そうな彼の雰囲気は一掃され、彼から伸びた手が私の後頭部を一気に引き寄せる。
何だかんだ言って、こんな朝を過ごしている私たちはやっぱり甘いと言われるかもしれない。けれど、先ほどと同じで私にとってこれは日常の一部。つまり不幸でも幸福でもない、存在しなくても困らない、不必要と言っても良い時間なのだ。自分でも人より冷めているという自覚はある。ただ、そんな私だからこそ、彼には好都合なのだろう。そんな私だから、隣に置いてくれているのだろう。ここで私が可愛らしい猫撫で声を出して、彼に擦り寄れば、彼は私を疎ましく思い邪険にするはず。
「可愛い」
初めてこの言葉を言われた時は柄にも無く照れたものだ。しかし、この「可愛い」という言葉は彼にとって何ら特別ではなく、むしろ挨拶のようなものである。何時からか、私までこの言葉に対して何の感情も抱かなくなってしまった。可愛いと言われてきゅんとするような女の子になりたかった。彼はまたひとつ、私の夢をさらりと奪ってしまったのである。
「あ、明日から3日間くらい多分会えないから」
「そうなんだ、分かった」
自分で言うのも何だが、ここでいちいち「何かあるの?」と聞かないところが私の優秀な部分のひとつである。彼のすることに興味が無いと言えば無いとも言えるが、それ以前に何となく彼が私と会うのを絶つ理由が簡単に想像出来てしまうからだ。それを察しているので、あえて聞かない。こんなのまともな恋人同士ではない。そもそも、本当に恋人同士なのだろうかと疑う日の方が多い。けれども、私は大丈夫。
「ちゃんと良い子にして待ってるんスよ」
「はいはい」
「冷たー。もうちょっと寂しがってくれたって良いじゃないっスか」
何を言う。そんなことをしたら、私のことを疎ましく思うくせに。本当に勝手で酷な男である。分かってて言っているのか、それともわざと言っているのかは分からない。彼と出会ってからもう3年ほど経つだろうか。それでも分からないこと、知らないことはたくさんある。
彼の第一印象はとにかく軽い人だった。彼は私が以前バイトをしていたカラオケ店の常連だったのだ。毎回来る度に違う女性と一緒にやってくるので、嫌でも彼のことは印象に残っていた。おまけに私から見ても分かる端正な顔立ちに、一般人とは思えないほどのスタイル。女性の扱いにも慣れているであろうその雰囲気が、更に彼の印象を深くした。
そんなある日、バイト中にゴミを捨てようと店の裏へ出ると、やたらと慌てた彼に遭遇した。私を見つけた彼は「ごめん、ちょっと」と一言だけ言葉を漏らすと息を切らしながらいきなり私の腕を掴み、抱きしめたのだ。そして拒絶と疑問の訴えを投げかけようとする間もなく、風の如く唇を奪われた。付き合ってもいない、むしろ友達でも知り合いでもない、ただの顔見知りの男にいきなりキスをされたのだ。唇が離れると、ふと誰かがいる気配がした。見覚えがある女性である。そう、前に彼と一緒にうちの店に何回か来たことがあるキレイな女性だ。その女性は先程の私たちの光景を見てしまったのだろうか。美しい顔を歪ませ顔色を青くさせていたのが、他人の私でもよく分かった。彼は「俺、付き合ってる人いるからもう付きまとわないでくれないっスか」とその女性に向かって感情も何もない声で吐き捨てた。女性は怒りと悲しみを抑えられないといった様子で「さいてー」とだけ言葉を漏らし、更には涙も漏らしその場を去って行った。確かに「最低」である。おそらく彼と彼女はそれなりに深い仲であったのだろう。彼女に対しても最低であるが、何より私に対しても最低である。私に謝罪の言葉でもあるのかと思えば「ねぇ、ちょうど良いから俺と付き合ってくんないっスか」と馬鹿みたいなことをいきなり言ってきた。理由を尋ねると、どうやら彼には熱狂的なファンが何人かいるようで、最近それがエスカレートしてきた為、特別な恋人を作ることで打開策を生み出したいとのこと。そんなの私じゃなくても恋人のひとりくらい簡単に作れそうなのだから、そういう人に頼めば良いじゃないかと言うと「そういうの面倒くさいんスよ」と吐き捨てた。それ故、あまり知らないけど顔は知っている私。そして何より今、たまたま遭遇したという理由だけで私を選んだのだ。おまけに「大丈夫っスよ、それなりにちゃんと恋人同士みたいなことはしてあげるから」だなんて、人を見下したような発言をされて平常心でいられるほど、その時の私は大人ではなかった。馬鹿か、と言ってやりたい衝動に駆られたが、おそらくそれを上回る程のある想いが心の奥底に存在した。首を縦に振った自分は今でもよく覚えている。
「んー、じゃあ気が向いたら連絡してね」
「りょーかいっス」
そんなロマンチックのかけらもない馬鹿げた出会いと付き合いからもう3年。あれから何度でも唇を重ねたし、何度でも肌を重ねた。彼が住んでいるこのマンションの合鍵も貰った。ただ、外でデートをしたことは数える程しかなく、手を繋いで一緒に歩いたなんてことは全くない。お互いの誕生日やクリスマスなどのイベントも一緒に過ごした記憶はないが、彼が言う恋人同士らしいことと言うのはおそらく唇や肌で温度を共有するだけ。それが彼の認識している愛なのだと思う。
特に不満はない。私は元々ベタベタした恋人関係は好きではないし、人より冷めた部分を持っていることも自覚しているので、何ら不都合はない。温もりがあるロボットと一緒に過ごしているようなものである。でも、温もりがあるとないのとではかなり違う。人肌と言う温もりがあるのとないのでは、心の隙間の大きさが全く違うのだ。
「じゃあ私行くね」
おそらく彼は私に連絡なんてしてこないだろう。でも、それでも良いのだ。お互いがお互いのことを深く干渉しない、楽な関係である。何度でも思うが、もしかしたらこの関係は恋人同士ではないのかもしれない。友人に「彼氏いるの?」と聞かれて「一応」としか答えられないなんて、恋人と言えるのだろうか。ただ、私はそれでも良いのである。止まり木があれば、それが中身のない木でも細い木でも今にも折れそうな木でも、そういう場所があるということが大事なのである。自分が求める時に一緒にいる人間がいるということ、それだけ。だから彼の過去に興味を持たなければ現在にも未来にも特に興味を持たないし、これから持とうとも思わない。今思えばもう3年も経つのに私は彼の名前と年齢と住んでいるこの場所くらいしか知らない。
私は黄瀬くんのことをほとんど何も知らないのだ。
相変わらず重い身体を無理矢理起こし、朝の準備に入る。私の隣で健やかに眠っている彼は今もまだ目を閉じたままだ。彼が起きないよう、一通りの身支度を済ませ、軽い朝食を作り、鍵を置いて家を出る。置き手紙を書こうと、ペンを走らせながら書く字は丁寧を心掛けているが、感情は何も込めていない。恋人と一緒に寝て、朝に目が覚めたら隣に恋人がいて、恋人の寝顔を見て、恋人のために朝食を準備して、恋人のために起こさないように家を出る。この場面だけを切り取れば、他人からしたら幸せな朝なのかもしれない。でも、私にとっては間違いなく幸せでも不幸でもない。ただの平凡ないつもの一日なのである。
「…?」
「おはよ」
どうやらこの置き手紙は必要なくなったらしい。けれども、まだ夢の中を彷徨っているような彼は枕に顔を埋めながら、なかなか身体を起こそうとしない。昨日はだいぶ遅かったのだろう、それも仕方ない。一応彼の帰宅を待ってはいたが、あまりにも遅いため私は彼を待たずに先に寝た。昨夜勝手に用意した彼のための寂しい夕飯は、今朝も相変わらず冷たいままだった。
「どっか行くんスか?」
「うん。ってか自分の家戻るだけだけど」
彼とは一緒に住んでいるわけではないし、半同棲というわけでもない。昨日はたまたま友人と遅くまで遊んで、自分の家に帰るより彼の家に行く方が近いため、泊まっただけだ。私としては家が二つあるようで楽である。こういうことは今までにも何回かあったが、彼に咎められたことはもちろんない。利便性だけを求めて勝手に上がり込んだとは言え、合鍵を渡してくれているのだから、彼はそんなつまらないことに興味を示したりはしないだろう。
「ふーん」
「…服離して。伸びちゃう」
「がちゅーしてくれないと離れないっス」
帰ろうと思っても彼の指が私の服に縫い付けられたかのようにくっついており、離してくれる気配がまるでない。「ちゅーしてくれないと」なんて、まるで子犬のような目で見てくる彼に憎らしさを感じつつも、仕方がないのでキスしてやった。途端、先程までの気怠そうな彼の雰囲気は一掃され、彼から伸びた手が私の後頭部を一気に引き寄せる。
何だかんだ言って、こんな朝を過ごしている私たちはやっぱり甘いと言われるかもしれない。けれど、先ほどと同じで私にとってこれは日常の一部。つまり不幸でも幸福でもない、存在しなくても困らない、不必要と言っても良い時間なのだ。自分でも人より冷めているという自覚はある。ただ、そんな私だからこそ、彼には好都合なのだろう。そんな私だから、隣に置いてくれているのだろう。ここで私が可愛らしい猫撫で声を出して、彼に擦り寄れば、彼は私を疎ましく思い邪険にするはず。
「可愛い」
初めてこの言葉を言われた時は柄にも無く照れたものだ。しかし、この「可愛い」という言葉は彼にとって何ら特別ではなく、むしろ挨拶のようなものである。何時からか、私までこの言葉に対して何の感情も抱かなくなってしまった。可愛いと言われてきゅんとするような女の子になりたかった。彼はまたひとつ、私の夢をさらりと奪ってしまったのである。
「あ、明日から3日間くらい多分会えないから」
「そうなんだ、分かった」
自分で言うのも何だが、ここでいちいち「何かあるの?」と聞かないところが私の優秀な部分のひとつである。彼のすることに興味が無いと言えば無いとも言えるが、それ以前に何となく彼が私と会うのを絶つ理由が簡単に想像出来てしまうからだ。それを察しているので、あえて聞かない。こんなのまともな恋人同士ではない。そもそも、本当に恋人同士なのだろうかと疑う日の方が多い。けれども、私は大丈夫。
「ちゃんと良い子にして待ってるんスよ」
「はいはい」
「冷たー。もうちょっと寂しがってくれたって良いじゃないっスか」
何を言う。そんなことをしたら、私のことを疎ましく思うくせに。本当に勝手で酷な男である。分かってて言っているのか、それともわざと言っているのかは分からない。彼と出会ってからもう3年ほど経つだろうか。それでも分からないこと、知らないことはたくさんある。
彼の第一印象はとにかく軽い人だった。彼は私が以前バイトをしていたカラオケ店の常連だったのだ。毎回来る度に違う女性と一緒にやってくるので、嫌でも彼のことは印象に残っていた。おまけに私から見ても分かる端正な顔立ちに、一般人とは思えないほどのスタイル。女性の扱いにも慣れているであろうその雰囲気が、更に彼の印象を深くした。
そんなある日、バイト中にゴミを捨てようと店の裏へ出ると、やたらと慌てた彼に遭遇した。私を見つけた彼は「ごめん、ちょっと」と一言だけ言葉を漏らすと息を切らしながらいきなり私の腕を掴み、抱きしめたのだ。そして拒絶と疑問の訴えを投げかけようとする間もなく、風の如く唇を奪われた。付き合ってもいない、むしろ友達でも知り合いでもない、ただの顔見知りの男にいきなりキスをされたのだ。唇が離れると、ふと誰かがいる気配がした。見覚えがある女性である。そう、前に彼と一緒にうちの店に何回か来たことがあるキレイな女性だ。その女性は先程の私たちの光景を見てしまったのだろうか。美しい顔を歪ませ顔色を青くさせていたのが、他人の私でもよく分かった。彼は「俺、付き合ってる人いるからもう付きまとわないでくれないっスか」とその女性に向かって感情も何もない声で吐き捨てた。女性は怒りと悲しみを抑えられないといった様子で「さいてー」とだけ言葉を漏らし、更には涙も漏らしその場を去って行った。確かに「最低」である。おそらく彼と彼女はそれなりに深い仲であったのだろう。彼女に対しても最低であるが、何より私に対しても最低である。私に謝罪の言葉でもあるのかと思えば「ねぇ、ちょうど良いから俺と付き合ってくんないっスか」と馬鹿みたいなことをいきなり言ってきた。理由を尋ねると、どうやら彼には熱狂的なファンが何人かいるようで、最近それがエスカレートしてきた為、特別な恋人を作ることで打開策を生み出したいとのこと。そんなの私じゃなくても恋人のひとりくらい簡単に作れそうなのだから、そういう人に頼めば良いじゃないかと言うと「そういうの面倒くさいんスよ」と吐き捨てた。それ故、あまり知らないけど顔は知っている私。そして何より今、たまたま遭遇したという理由だけで私を選んだのだ。おまけに「大丈夫っスよ、それなりにちゃんと恋人同士みたいなことはしてあげるから」だなんて、人を見下したような発言をされて平常心でいられるほど、その時の私は大人ではなかった。馬鹿か、と言ってやりたい衝動に駆られたが、おそらくそれを上回る程のある想いが心の奥底に存在した。首を縦に振った自分は今でもよく覚えている。
「んー、じゃあ気が向いたら連絡してね」
「りょーかいっス」
そんなロマンチックのかけらもない馬鹿げた出会いと付き合いからもう3年。あれから何度でも唇を重ねたし、何度でも肌を重ねた。彼が住んでいるこのマンションの合鍵も貰った。ただ、外でデートをしたことは数える程しかなく、手を繋いで一緒に歩いたなんてことは全くない。お互いの誕生日やクリスマスなどのイベントも一緒に過ごした記憶はないが、彼が言う恋人同士らしいことと言うのはおそらく唇や肌で温度を共有するだけ。それが彼の認識している愛なのだと思う。
特に不満はない。私は元々ベタベタした恋人関係は好きではないし、人より冷めた部分を持っていることも自覚しているので、何ら不都合はない。温もりがあるロボットと一緒に過ごしているようなものである。でも、温もりがあるとないのとではかなり違う。人肌と言う温もりがあるのとないのでは、心の隙間の大きさが全く違うのだ。
「じゃあ私行くね」
おそらく彼は私に連絡なんてしてこないだろう。でも、それでも良いのだ。お互いがお互いのことを深く干渉しない、楽な関係である。何度でも思うが、もしかしたらこの関係は恋人同士ではないのかもしれない。友人に「彼氏いるの?」と聞かれて「一応」としか答えられないなんて、恋人と言えるのだろうか。ただ、私はそれでも良いのである。止まり木があれば、それが中身のない木でも細い木でも今にも折れそうな木でも、そういう場所があるということが大事なのである。自分が求める時に一緒にいる人間がいるということ、それだけ。だから彼の過去に興味を持たなければ現在にも未来にも特に興味を持たないし、これから持とうとも思わない。今思えばもう3年も経つのに私は彼の名前と年齢と住んでいるこの場所くらいしか知らない。
私は黄瀬くんのことをほとんど何も知らないのだ。