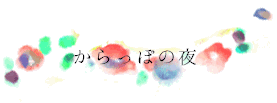彼と3日会えないからと言って、特に違った日常を過ごすわけではない。元々毎日なんて会っていなかったし、3日会わないことや連絡をお互いに取り合わないことなんてザラにある。今思えば、むしろよく3日間会えないなどとわざわざ教えてくれたものだ。
私は恋愛関係だけでなく、友人関係も淡泊だ。自分をあまり見せたくない、知られたくないという思いが心の何処かに存在しているからだろう。無意識のうちに、他人と深い仲になることを避けている気が自分でもする。それでも親友と呼べる人間が何人かいることは有り難いことだと思っている。今日会っているこの人物も、正に私の数少ない友人のひとりだ。
「珍しいね、青峰くんが呼び出すなんて」
「暇で死にそうだったんだよ」
「暇潰しですか」
「どうせだって暇だったんだろ?」
彼、青峰くんはかつでのバイト仲間だった。彼みたいなやる気のないタイプがバイトをしていること自体、疑問ではあったが特にその理由を聞くことはないまま今に至る。興味がない、と言ってしまえば冷たいのかもしれないが、私自身あまり自分のことを知って欲しくないので、他人にも興味を持っていないのかもしれない。
青峰くんは偶然にも黄瀬くんの友人だったらしく、私と黄瀬くんの関係を知っているであろう数少ない人間である。「私と黄瀬くんの関係」と言うのは単なる恋人関係だということだけではなく「見せかけだらけの恋愛関係」でもあるという意味も含んでいる。そんな馬鹿みたいなことにも青峰くんは何となく気づいているだろう。呼び出された居酒屋で青峰くんは既にビールを何杯か飲んでいるようだったが酔ってるようには見えなかった。私も無難なレモンサワーを頼み、特に乾杯も何もせず口へ運んだ。特に期待はしていなかったけれど、甘くもなければ、酸っぱくもない。違うものを注文すれば良かったと少し後悔した。
「で、黄瀬とまだ付き合ってんのかよ」
「まぁ」
「相変わらず曖昧そうだな」
曖昧、青峰くんにしては的を得た便利な言葉である。確かに私と彼の関係は昔も今も変わらぬまま、曖昧だ。おそらくそんな曖昧な関係なんて良くない、と言う人の方が多いだろう。そんな曖昧をずっと見てきた青峰くんにも何か思うことはあるらしいが、説教を聞かされたことは一度もない。仮に言われたとしても、「そうだね」としか私には返せない。そこから先、どうしようとも思えないのだ。
「あいつ、他に女いんだろ」
けど、今日の青峰くんはやたらと人の心へ踏み込んで来た。そんなこと、今まで一回も言ったことがなかったのに、何故今更そんなことを言うのだろうか。おまけにそんな事実、私はとっくに知っているというのに。目の前のグラスに映った私の顔は驚いている。カランと中に入った氷がぐらついた瞬間、私まで崩れるように歪んだ気がした。
「男の浮気を知っていながら責めないって楽でしょう?」
「どーだかな。もしかしたら責めて欲しくてやってるんのかもしんねーし」
「黄瀬くんに限ってそれはない」
私は自分自身で何て都合の良い女なんだと思う。都合が良い、と表現するとあまり良い印象を抱けないだろうが、理解のある女と思ってもらえれば幸いである。だって、浮気を知りながらも知らないフリを続け、責めることもしないのだから。もしかしたら、私が「浮気相手」なのかもしれないが、それならそれで構わない。別れて、と言われれば別れるし、何も言われなければこのまま。現状維持だ。
「男って浮気する生き物なの?」
「人それぞれじゃねーの?」
「ふうん、よくわかんないけど」
「じゃあ女は浮気しねーのかよ」
「…人それぞれじゃない?」
「そんなもんだろ。まぁ、俺にはあんま理解出来ねーけどな」
黄瀬くんが言った3日会えないとは、もしかしたら他の女性と会っているからかもしれない。そんなこと、言われた時から想像のひとつに存在したことである。彼は、私に触れるように、否。私に触れる以上に、優しく愛情をこめて他の女性へ触れたり愛の言葉を囁いているのかもしれない。それでも私は平気なのである。
「相手の浮気分かってて、何も言わずに付き合うなんて」
多くの人間からは理解されない思考回路だと自分でも自覚している。けど多分、彼も私が他の男性と関係を持ったとしても何も言わないだろう。気づいたとしても何も言ってこない。その事実を告白したとしても「へぇ、そうなんスか」と言われて終わり。そう、彼も私と同じ。誰か特別な人間に興味を持つことはなく、必要以上に踏み込まない。だから彼と一緒にいることは楽なのかもしれないと思う。こんな私みたいな女、他の男性は受け入れてくれないだろうから。
「いつからこんな風になったんだろう」
「、お前黄瀬にとってそんな都合の良い女扱いで良いのかよ」
私だって昔は普通の価値観を持つ普通の女だったはず。それがいつ、どの部分の歯車が狂ってしまったのか分からない。グラスの中に入ったお酒をゆっくり掻き混ぜると、カラカラと氷がぶつかる音が聴こえる。やけに脳に響いてくるのは酔っているからじゃない。私に何かを訴えかけているからじゃないだろうか。けど、それを理解する前に氷は溶けて中のお酒は薄く温くなってしまった。負の連鎖とはこういうことだろうか。
「っていうか、そもそも自分が自分のことを好きじゃないのに誰かに、黄瀬くんに好きになってもらおうなんて思ってないからかな」
青峰くんにだからこそ吐露することが出来た紛れも無い本音である。そうだ、言葉は自然と生まれるように出てきたけれど、この言葉は私の心の中でずっと引っ掛かっていたひとつの問題だと思う。自分が自分のことを好きじゃないのに、一体誰がそんな自分を好きになってくれると言うのだろうか。誰かに好きと言われても信じることが出来ない。「どこが?」「何が?」としか言えない悲しい女である。けど、もっと悲しいことに私は彼に「好き」と言われたことがないように思う。「可愛い」などと言う甘い言葉は感情を込めずに何度も吐かれたことがあるが「好き」は無い。もしかしたら言われたことがあるのかもしれないけれど、それは私が意識してなかったか、風が耳を撫でるくらいあまりにもあっさりした言葉で聞き逃したのかもしれない。けれど、記憶を探っても見つからないのでおそらく無いのだろう。取り繕った「好き」を言われるより誠実かもしれないが、それも世間からすれば少し可笑しいのかもしれない。
「は難しいこと考えるの得意だよな」
「純粋な気持ちなんだけど」
常日頃から思っていることである。では、自分のことを好きになれば良いじゃないか、と思われるかもしれないがそんなこと出来たらとっくの昔にやっている。どうしてこんなにも自分を好きになれないのだろうか。こんな自虐的な思考を持っているからだろう。けど、それを言ってしまえば、もう根本的な部分が可笑しい。そして根本的な部分ほど、修正するのは難しい。結局、私は私を好きになれないまま、愛せないまま。そして誰にも愛されないまま、誰を愛することも出来ないまま、過ごすしかないのだ。愛は無くとも傍に人肌があれば良い、という虚しい想いを抱きながら。
「可哀相なヤツ」
青峰くんが誰に対して「可哀相」と言ったのかすぐに理解が出来なかった。会話の流れを拾うと、そんな考え方しか出来ない私が可哀相なのか。それともそんな私にその程度しか思われていない彼が可哀相なのか。けれど彼と私はお互い様である。私も彼からはその程度にしか思われていないだろう。そこに愛なんて幸せな言葉存在する欠片もない。つまり、青峰くんが言った「可哀相」とは残念ながら私にも彼にも当て嵌まるのだ。私たちのことをよく理解してくれている青峰くんだからこそ、遠慮無く真実を言ってくれたのだろう。どちらにしても、どちらともにしろ、不愉快には全く感じない。それに可哀相、だなんて自分では一切思っていないから。こんな考え方を変えたいという気持ちは少しあるものの、私自身そして彼を可哀相とは思わない。ただ少し、悲しいだけだ。
私は恋愛関係だけでなく、友人関係も淡泊だ。自分をあまり見せたくない、知られたくないという思いが心の何処かに存在しているからだろう。無意識のうちに、他人と深い仲になることを避けている気が自分でもする。それでも親友と呼べる人間が何人かいることは有り難いことだと思っている。今日会っているこの人物も、正に私の数少ない友人のひとりだ。
「珍しいね、青峰くんが呼び出すなんて」
「暇で死にそうだったんだよ」
「暇潰しですか」
「どうせだって暇だったんだろ?」
彼、青峰くんはかつでのバイト仲間だった。彼みたいなやる気のないタイプがバイトをしていること自体、疑問ではあったが特にその理由を聞くことはないまま今に至る。興味がない、と言ってしまえば冷たいのかもしれないが、私自身あまり自分のことを知って欲しくないので、他人にも興味を持っていないのかもしれない。
青峰くんは偶然にも黄瀬くんの友人だったらしく、私と黄瀬くんの関係を知っているであろう数少ない人間である。「私と黄瀬くんの関係」と言うのは単なる恋人関係だということだけではなく「見せかけだらけの恋愛関係」でもあるという意味も含んでいる。そんな馬鹿みたいなことにも青峰くんは何となく気づいているだろう。呼び出された居酒屋で青峰くんは既にビールを何杯か飲んでいるようだったが酔ってるようには見えなかった。私も無難なレモンサワーを頼み、特に乾杯も何もせず口へ運んだ。特に期待はしていなかったけれど、甘くもなければ、酸っぱくもない。違うものを注文すれば良かったと少し後悔した。
「で、黄瀬とまだ付き合ってんのかよ」
「まぁ」
「相変わらず曖昧そうだな」
曖昧、青峰くんにしては的を得た便利な言葉である。確かに私と彼の関係は昔も今も変わらぬまま、曖昧だ。おそらくそんな曖昧な関係なんて良くない、と言う人の方が多いだろう。そんな曖昧をずっと見てきた青峰くんにも何か思うことはあるらしいが、説教を聞かされたことは一度もない。仮に言われたとしても、「そうだね」としか私には返せない。そこから先、どうしようとも思えないのだ。
「あいつ、他に女いんだろ」
けど、今日の青峰くんはやたらと人の心へ踏み込んで来た。そんなこと、今まで一回も言ったことがなかったのに、何故今更そんなことを言うのだろうか。おまけにそんな事実、私はとっくに知っているというのに。目の前のグラスに映った私の顔は驚いている。カランと中に入った氷がぐらついた瞬間、私まで崩れるように歪んだ気がした。
「男の浮気を知っていながら責めないって楽でしょう?」
「どーだかな。もしかしたら責めて欲しくてやってるんのかもしんねーし」
「黄瀬くんに限ってそれはない」
私は自分自身で何て都合の良い女なんだと思う。都合が良い、と表現するとあまり良い印象を抱けないだろうが、理解のある女と思ってもらえれば幸いである。だって、浮気を知りながらも知らないフリを続け、責めることもしないのだから。もしかしたら、私が「浮気相手」なのかもしれないが、それならそれで構わない。別れて、と言われれば別れるし、何も言われなければこのまま。現状維持だ。
「男って浮気する生き物なの?」
「人それぞれじゃねーの?」
「ふうん、よくわかんないけど」
「じゃあ女は浮気しねーのかよ」
「…人それぞれじゃない?」
「そんなもんだろ。まぁ、俺にはあんま理解出来ねーけどな」
黄瀬くんが言った3日会えないとは、もしかしたら他の女性と会っているからかもしれない。そんなこと、言われた時から想像のひとつに存在したことである。彼は、私に触れるように、否。私に触れる以上に、優しく愛情をこめて他の女性へ触れたり愛の言葉を囁いているのかもしれない。それでも私は平気なのである。
「相手の浮気分かってて、何も言わずに付き合うなんて」
多くの人間からは理解されない思考回路だと自分でも自覚している。けど多分、彼も私が他の男性と関係を持ったとしても何も言わないだろう。気づいたとしても何も言ってこない。その事実を告白したとしても「へぇ、そうなんスか」と言われて終わり。そう、彼も私と同じ。誰か特別な人間に興味を持つことはなく、必要以上に踏み込まない。だから彼と一緒にいることは楽なのかもしれないと思う。こんな私みたいな女、他の男性は受け入れてくれないだろうから。
「いつからこんな風になったんだろう」
「、お前黄瀬にとってそんな都合の良い女扱いで良いのかよ」
私だって昔は普通の価値観を持つ普通の女だったはず。それがいつ、どの部分の歯車が狂ってしまったのか分からない。グラスの中に入ったお酒をゆっくり掻き混ぜると、カラカラと氷がぶつかる音が聴こえる。やけに脳に響いてくるのは酔っているからじゃない。私に何かを訴えかけているからじゃないだろうか。けど、それを理解する前に氷は溶けて中のお酒は薄く温くなってしまった。負の連鎖とはこういうことだろうか。
「っていうか、そもそも自分が自分のことを好きじゃないのに誰かに、黄瀬くんに好きになってもらおうなんて思ってないからかな」
青峰くんにだからこそ吐露することが出来た紛れも無い本音である。そうだ、言葉は自然と生まれるように出てきたけれど、この言葉は私の心の中でずっと引っ掛かっていたひとつの問題だと思う。自分が自分のことを好きじゃないのに、一体誰がそんな自分を好きになってくれると言うのだろうか。誰かに好きと言われても信じることが出来ない。「どこが?」「何が?」としか言えない悲しい女である。けど、もっと悲しいことに私は彼に「好き」と言われたことがないように思う。「可愛い」などと言う甘い言葉は感情を込めずに何度も吐かれたことがあるが「好き」は無い。もしかしたら言われたことがあるのかもしれないけれど、それは私が意識してなかったか、風が耳を撫でるくらいあまりにもあっさりした言葉で聞き逃したのかもしれない。けれど、記憶を探っても見つからないのでおそらく無いのだろう。取り繕った「好き」を言われるより誠実かもしれないが、それも世間からすれば少し可笑しいのかもしれない。
「は難しいこと考えるの得意だよな」
「純粋な気持ちなんだけど」
常日頃から思っていることである。では、自分のことを好きになれば良いじゃないか、と思われるかもしれないがそんなこと出来たらとっくの昔にやっている。どうしてこんなにも自分を好きになれないのだろうか。こんな自虐的な思考を持っているからだろう。けど、それを言ってしまえば、もう根本的な部分が可笑しい。そして根本的な部分ほど、修正するのは難しい。結局、私は私を好きになれないまま、愛せないまま。そして誰にも愛されないまま、誰を愛することも出来ないまま、過ごすしかないのだ。愛は無くとも傍に人肌があれば良い、という虚しい想いを抱きながら。
「可哀相なヤツ」
青峰くんが誰に対して「可哀相」と言ったのかすぐに理解が出来なかった。会話の流れを拾うと、そんな考え方しか出来ない私が可哀相なのか。それともそんな私にその程度しか思われていない彼が可哀相なのか。けれど彼と私はお互い様である。私も彼からはその程度にしか思われていないだろう。そこに愛なんて幸せな言葉存在する欠片もない。つまり、青峰くんが言った「可哀相」とは残念ながら私にも彼にも当て嵌まるのだ。私たちのことをよく理解してくれている青峰くんだからこそ、遠慮無く真実を言ってくれたのだろう。どちらにしても、どちらともにしろ、不愉快には全く感じない。それに可哀相、だなんて自分では一切思っていないから。こんな考え方を変えたいという気持ちは少しあるものの、私自身そして彼を可哀相とは思わない。ただ少し、悲しいだけだ。