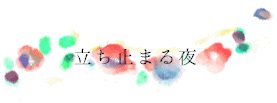つまらない着信音がひとりきりの静かな部屋に鳴り響く。マナーモードにするのを忘れた自分に嫌気が差し、仕方なくディズプレイを見てみると、そこには珍しい名前が映し出されていた。電話ではなくメールだったので、ゆっくり開いて見ると「久しぶり」から始まるメールは何だかひどくよそよそしい。けど、実際何年も会っていないのだからそう感じてしまうのも無理はない。
「…久しぶりだね」
内容は久々に会わないかというものだった。特に断る理由もないので、短く「いいよ」とだけ返信するとまたすぐに返事が来た。指定された場所は渋谷の創作和食ダイニングのお店。渋谷という賑やかな街で会うなんて、今までの彼からは想像もつかなかったけど、この何年かで色々と変わったのかもしれない。和食と言っても堅苦し過ぎる雰囲気は無く、夜の渋谷にも溶け込むような、気軽に入れる雰囲気も持ち合わせているお店である。それでも和食をセレクトしているあたり、やはり懐かしさを感じた。
「赤司くん、少し雰囲気変わった?」
「こそ。キレイな女性になったね」
歯の浮くような台詞は黄瀬くんで慣れてるため、特に動揺なんてものは生まれなかった。それに彼は言葉を巧みに操るので、そんな言葉に喜んでいたら先へ進めない。軽く「そう?」とだけ言って彼が座っているカウンター席の隣に腰掛ける。
「びっくりした、赤司くんがまさか東京にいるなんて」
「ちょっと前に戻ってきたんだ」
私と彼の関係は所謂「元恋人」である。私は小学校の高学年時から高校卒業まで、彼は高校の3年間、共に京都に住んでいた。私と彼の出会いは単純。高校の時のクラスメイトから始まった。しかし、高校生の恋愛なんて人それぞれ。卒業しても結ばれ続けている恋人同士もいれば、卒業を機に別れる恋人同士もいる。私たちは後者だった。私は卒業してすぐに東京へ、彼は卒業しても京都にいるという進路だったため、別れはごく自然だった。遠距離恋愛なんていう選択肢はお互いになかったように思う。
「が東京にいることを思い出してね。久々に会いたくなったんだ」
「そう。赤司くんも元気そうで何より」
別に嫌いで別れたわけではないので、今こうして会っていても気まずいなどという感情は一切ない。むしろ気心を知っている友人のようで、一緒にいて楽な存在ではある。久々に会った彼は以前より少しだけ背も伸びていて、あの頃はまだあどけなさが残っていた顔つきも、今はすっかり大人の男性。端正な顔立ちは相変わらずだけど、少しだけ雰囲気が変わったような気もする。
「それでは最近どうなんだ?」
「どうって言われても…」
これは久々に再会した人間同士で交わされるひどく曖昧な尋ね方であるように思えて仕方がない。どう?とは一体何を差しているのだろうか。けど、その人が感じている日常を知るには一番便利な言葉かもしれない。この問いひとつで、その人が今幸せなのかそうじゃないのかが大体ではあるが判断出来るような気もする。
「楽しいよ、それなりに」
「それなりに、か」
「何?」
「いや、そういうところは相変わらずだなと思って」
私は昔、彼がこわかった。私のことを理解し過ぎているようで。それが嬉しいと思う感覚には残念ながらなれなかったのだ。だから赤司くんと恋人同士だったとは言え、普通の恋人同士よりスキンシップは少なかったような気がする。彼に近づくと、何だかすべてを見透かされてしまうようで。そう思うようになってしまったのはいつ頃からだっただろうか。昔のこと過ぎて、今はもう覚えていない。
「付き合ってる人は?」
「いるよ、一応」
「女性はすぐに「一応」という言葉をつけるね」
確かに「彼氏いるの?」と聞かれて「一応」と答える人は多い気もする。でも、それは大抵恥じらいを隠している場合が多い。残念ながら私はそんな可愛い理由ではなく、事実を答えているだけ。だから悲しいことに「いるよ」とだけ答えることも出来ない。「いないよ」と嘘をつく理由もない。おそらく愛はない気がするので、もしかしたら嘘ではないのかもしれないけど。
「赤司くんは?さぞかしモテるでしょう」
「いないよ」
「嘘?それは意外」
「理想が高いのかもしれないな」
「それ嫌味?」
「まさか。でも、オレは自分が本当に好きになった人とじゃないと付き合えない」
この当たり前な言葉はひどく胸に刺さった。まるで今の私に何かを諭すような、そんな感覚。彼にはまだ何も詳しいことは話していないのに、私と黄瀬くんの関係をすべて読み取られてしまったような、そんな感覚がする。おそらく偶然なのかもしれない。けど、そんな偶然が私には必然に思えてしまった。
彼とはそれから、昔の話から今のお互いの話など、思いの外たくさん喋った。彼はこんなにも話をしてくれる人だっただろうか。そもそも高校時代の彼はバスケが忙しくてあまり一緒にいなかったような気がする。それに加えて、私がだんだんと距離を取るようになってしまったので、もしかしたら彼とこんなに長い時間いっしょに過ごすのは久々というより初めてかもしれない。
「じゃあそろそろ出ようか」
「うん。あ、いくら?」
「オレが呼び出したんだ。気にしなくて良い」
「奢ってもらう理由がない」
「男を立てさせてもくれないのか?」
「…ずるい」
結局彼の好意に甘えて全額彼が支払いをしてくれた。普段、黄瀬くんとはあまり外で食べることはないし、この前の青峰くんの時はワリカンだった。もちろん、男の人と一緒だから奢ってもらおうだとか多く出してもらおうという考えは持っていない。むしろ対等でいたいくらいなので、出来れば自分の分くらいは自分で支払いたいが、先ほどの彼の言葉は私を揺らがせた。一体どこでそんな台詞を覚えてきたのだろうか。それとも天然なものなのだろうか。女性に負担をかけさせないその言葉は、彼を余計大人に見せた。
「遅くまで付き合わせてすまなかったな」
「ううん、明日は特に何もないから」
いったいどれほど話していただろうか。時計の針はあっという間に24時どころか25時を指そうとしていた。元々会い始めた時間も22時前と遅かったが、時が経過する早さに驚いた。この時間になるとスクランブル交差点もずいぶん通りやすくなる。しかし、それでもさすが渋谷というべきか。人もまだ割と歩いており、お店の看板も明るいところが多い。実際の時間ほど遅く感じないのが、この街の特徴のひとつだろう。けど、それは繁華街独特の光景である。住んでいるマンションは住宅街にあるため、出来るだけ早く帰らなければ。最近は物騒な事件も多いので、終電は逃したくない。
「あ、」
「どうかしたのか?」
しかし、ここで必然とも言える偶然が起きる。黄瀬くんを見かけてしまったのだ。もちろん、隣には華奢で可愛い女の子つきで。彼はその女の子と楽しそうに談笑しているので、道路の反対側にいる私には気づいていないだろう。だからと言って特に何の感情も抱かないが。悲しいことに嫉妬や悲しいなどという感情は、とっくの昔にどこかに捨てられてしまっている。
「いや、あそこに一応な彼氏がいたから」
「え?あれは…」
「もしかして知ってる?モデルやってるらしいから世間に顔は売れてるみたいだけど」
「…声、かけなくて良いのか?」
「うん、女の子と一緒だったし」
頭の良い彼はすべてを理解してくれたのだろう。それ以上は特に何も言って来なかった。けど、ここでの若干の戸惑いがタイムロスになってしまったのか、終電まであと3分。ここから駅までもあと3分。絶望に近い。
「はどうやって帰るんだ?」
「んー、途中までタクシーで途中から歩きかな」
「終電ないのか?」
「多分間に合いそうにないから」
家の前までタクシーで帰れるほど、私はリッチではない。歩いて帰れるところまで行ければ充分だろう。今日は高いヒールではなかったことは唯一の幸いだ。ふと、ここからなら自分の家より黄瀬くんのマンションの方が近いことを思い出したが、今日は何となく彼の家に行く気にはならなかった。タクシーをつかまえ乗り込む前に、彼に別れの挨拶を告げると、何やら手渡しをされた。
「何これ?」
「タクシー代。こんな時間まで付き合わせてしまったからね」
「やだ、そういうの好きじゃないって知ってるでしょ」
「こんな夜遅くにをひとりで歩かせるなんてこと出来ないよ」
「大丈夫、私」
「強情だね。仕方ないな」
「え、ちょっ」
彼は私をタクシーに押し込めると、自分までタクシーに乗り込んできた。その勢いで私が住んでいる場所を聞いてきたので、つい素直に答えてしまう。彼がそれをそのまま運転手さんに告げると、タクシーは私と赤司くんを乗せて夜の渋谷を走り出した。
「オレもタクシーで帰ることにした」
「え?」
「ついでだから一緒に帰ろう」
「赤司くんって…そんなに強引で紳士的だったっけ?」
「ついでなだけだよ」
私をこんなにも大事に扱ってくれる人に、久々に出会ったような気がする。もちろん、彼はきっと私じゃなくても、他の女性でも同じようにしただろう。でも、それでもそういう気遣いを見せてくれることが何だかすごく嬉しい。都会の夜は暗いなりにも明るい。今の私の心も彼のおかげで少しは明るく光が灯っているかもしれない。
「はさっき楽しいって言ってたけど、本当にそうなのか?」
「え?」
「が今付き合ってる男は、以外にも恋人がいるんだろう?」
「うん、多分ね」
「そんな男と一緒にいて幸せなのか?」
静かな車内の中で、やけに言葉が響く。幸せ、そんなこと特に考えたことなかった。幸せか不幸かと問われれば、もちろん不幸ではないと答えられる。幸せでもない、不幸でもない。それで良いじゃないか。そんな男と、黄瀬くんと一緒にいて幸せを感じたことなんてないのだから。
「どこが良いんだ?」
「どこだろ。自分と少し似てるからかな」
そう、幸せは感じない。でも少しだけ安心はする。私と黄瀬くんは少しだけ似てる部分があるのだ。黄瀬くんはきっと気づいていないと思う。でも、黄瀬くんが隠しているその部分は私とそっくり。だから、一緒にいて少し安心するのかもしれない。
「はただ、寂しいだけだろう」
「寂しい?」
「彼に対して愛情ではなく、情になってるんじゃないのか?」
「…やっぱりすごいね、赤司くんは」
けど、彼が言ったことが必ずしも正解だとは思えない。間違いでもない。つまり、私に答えなんて分からないのだ。確かにそう言われればそうとも言えてしまう。でも、愛がなかったらもっと寂しいじゃない。なんて、愛なんてとっくに無い。いや、最初から存在していないのに彼の言葉に頷けなかったのは私の中で少しの蟠りがあるからだろう。
「そんな男やめて、オレにすれば良い」
「…久しぶりだね」
内容は久々に会わないかというものだった。特に断る理由もないので、短く「いいよ」とだけ返信するとまたすぐに返事が来た。指定された場所は渋谷の創作和食ダイニングのお店。渋谷という賑やかな街で会うなんて、今までの彼からは想像もつかなかったけど、この何年かで色々と変わったのかもしれない。和食と言っても堅苦し過ぎる雰囲気は無く、夜の渋谷にも溶け込むような、気軽に入れる雰囲気も持ち合わせているお店である。それでも和食をセレクトしているあたり、やはり懐かしさを感じた。
「赤司くん、少し雰囲気変わった?」
「こそ。キレイな女性になったね」
歯の浮くような台詞は黄瀬くんで慣れてるため、特に動揺なんてものは生まれなかった。それに彼は言葉を巧みに操るので、そんな言葉に喜んでいたら先へ進めない。軽く「そう?」とだけ言って彼が座っているカウンター席の隣に腰掛ける。
「びっくりした、赤司くんがまさか東京にいるなんて」
「ちょっと前に戻ってきたんだ」
私と彼の関係は所謂「元恋人」である。私は小学校の高学年時から高校卒業まで、彼は高校の3年間、共に京都に住んでいた。私と彼の出会いは単純。高校の時のクラスメイトから始まった。しかし、高校生の恋愛なんて人それぞれ。卒業しても結ばれ続けている恋人同士もいれば、卒業を機に別れる恋人同士もいる。私たちは後者だった。私は卒業してすぐに東京へ、彼は卒業しても京都にいるという進路だったため、別れはごく自然だった。遠距離恋愛なんていう選択肢はお互いになかったように思う。
「が東京にいることを思い出してね。久々に会いたくなったんだ」
「そう。赤司くんも元気そうで何より」
別に嫌いで別れたわけではないので、今こうして会っていても気まずいなどという感情は一切ない。むしろ気心を知っている友人のようで、一緒にいて楽な存在ではある。久々に会った彼は以前より少しだけ背も伸びていて、あの頃はまだあどけなさが残っていた顔つきも、今はすっかり大人の男性。端正な顔立ちは相変わらずだけど、少しだけ雰囲気が変わったような気もする。
「それでは最近どうなんだ?」
「どうって言われても…」
これは久々に再会した人間同士で交わされるひどく曖昧な尋ね方であるように思えて仕方がない。どう?とは一体何を差しているのだろうか。けど、その人が感じている日常を知るには一番便利な言葉かもしれない。この問いひとつで、その人が今幸せなのかそうじゃないのかが大体ではあるが判断出来るような気もする。
「楽しいよ、それなりに」
「それなりに、か」
「何?」
「いや、そういうところは相変わらずだなと思って」
私は昔、彼がこわかった。私のことを理解し過ぎているようで。それが嬉しいと思う感覚には残念ながらなれなかったのだ。だから赤司くんと恋人同士だったとは言え、普通の恋人同士よりスキンシップは少なかったような気がする。彼に近づくと、何だかすべてを見透かされてしまうようで。そう思うようになってしまったのはいつ頃からだっただろうか。昔のこと過ぎて、今はもう覚えていない。
「付き合ってる人は?」
「いるよ、一応」
「女性はすぐに「一応」という言葉をつけるね」
確かに「彼氏いるの?」と聞かれて「一応」と答える人は多い気もする。でも、それは大抵恥じらいを隠している場合が多い。残念ながら私はそんな可愛い理由ではなく、事実を答えているだけ。だから悲しいことに「いるよ」とだけ答えることも出来ない。「いないよ」と嘘をつく理由もない。おそらく愛はない気がするので、もしかしたら嘘ではないのかもしれないけど。
「赤司くんは?さぞかしモテるでしょう」
「いないよ」
「嘘?それは意外」
「理想が高いのかもしれないな」
「それ嫌味?」
「まさか。でも、オレは自分が本当に好きになった人とじゃないと付き合えない」
この当たり前な言葉はひどく胸に刺さった。まるで今の私に何かを諭すような、そんな感覚。彼にはまだ何も詳しいことは話していないのに、私と黄瀬くんの関係をすべて読み取られてしまったような、そんな感覚がする。おそらく偶然なのかもしれない。けど、そんな偶然が私には必然に思えてしまった。
彼とはそれから、昔の話から今のお互いの話など、思いの外たくさん喋った。彼はこんなにも話をしてくれる人だっただろうか。そもそも高校時代の彼はバスケが忙しくてあまり一緒にいなかったような気がする。それに加えて、私がだんだんと距離を取るようになってしまったので、もしかしたら彼とこんなに長い時間いっしょに過ごすのは久々というより初めてかもしれない。
「じゃあそろそろ出ようか」
「うん。あ、いくら?」
「オレが呼び出したんだ。気にしなくて良い」
「奢ってもらう理由がない」
「男を立てさせてもくれないのか?」
「…ずるい」
結局彼の好意に甘えて全額彼が支払いをしてくれた。普段、黄瀬くんとはあまり外で食べることはないし、この前の青峰くんの時はワリカンだった。もちろん、男の人と一緒だから奢ってもらおうだとか多く出してもらおうという考えは持っていない。むしろ対等でいたいくらいなので、出来れば自分の分くらいは自分で支払いたいが、先ほどの彼の言葉は私を揺らがせた。一体どこでそんな台詞を覚えてきたのだろうか。それとも天然なものなのだろうか。女性に負担をかけさせないその言葉は、彼を余計大人に見せた。
「遅くまで付き合わせてすまなかったな」
「ううん、明日は特に何もないから」
いったいどれほど話していただろうか。時計の針はあっという間に24時どころか25時を指そうとしていた。元々会い始めた時間も22時前と遅かったが、時が経過する早さに驚いた。この時間になるとスクランブル交差点もずいぶん通りやすくなる。しかし、それでもさすが渋谷というべきか。人もまだ割と歩いており、お店の看板も明るいところが多い。実際の時間ほど遅く感じないのが、この街の特徴のひとつだろう。けど、それは繁華街独特の光景である。住んでいるマンションは住宅街にあるため、出来るだけ早く帰らなければ。最近は物騒な事件も多いので、終電は逃したくない。
「あ、」
「どうかしたのか?」
しかし、ここで必然とも言える偶然が起きる。黄瀬くんを見かけてしまったのだ。もちろん、隣には華奢で可愛い女の子つきで。彼はその女の子と楽しそうに談笑しているので、道路の反対側にいる私には気づいていないだろう。だからと言って特に何の感情も抱かないが。悲しいことに嫉妬や悲しいなどという感情は、とっくの昔にどこかに捨てられてしまっている。
「いや、あそこに一応な彼氏がいたから」
「え?あれは…」
「もしかして知ってる?モデルやってるらしいから世間に顔は売れてるみたいだけど」
「…声、かけなくて良いのか?」
「うん、女の子と一緒だったし」
頭の良い彼はすべてを理解してくれたのだろう。それ以上は特に何も言って来なかった。けど、ここでの若干の戸惑いがタイムロスになってしまったのか、終電まであと3分。ここから駅までもあと3分。絶望に近い。
「はどうやって帰るんだ?」
「んー、途中までタクシーで途中から歩きかな」
「終電ないのか?」
「多分間に合いそうにないから」
家の前までタクシーで帰れるほど、私はリッチではない。歩いて帰れるところまで行ければ充分だろう。今日は高いヒールではなかったことは唯一の幸いだ。ふと、ここからなら自分の家より黄瀬くんのマンションの方が近いことを思い出したが、今日は何となく彼の家に行く気にはならなかった。タクシーをつかまえ乗り込む前に、彼に別れの挨拶を告げると、何やら手渡しをされた。
「何これ?」
「タクシー代。こんな時間まで付き合わせてしまったからね」
「やだ、そういうの好きじゃないって知ってるでしょ」
「こんな夜遅くにをひとりで歩かせるなんてこと出来ないよ」
「大丈夫、私」
「強情だね。仕方ないな」
「え、ちょっ」
彼は私をタクシーに押し込めると、自分までタクシーに乗り込んできた。その勢いで私が住んでいる場所を聞いてきたので、つい素直に答えてしまう。彼がそれをそのまま運転手さんに告げると、タクシーは私と赤司くんを乗せて夜の渋谷を走り出した。
「オレもタクシーで帰ることにした」
「え?」
「ついでだから一緒に帰ろう」
「赤司くんって…そんなに強引で紳士的だったっけ?」
「ついでなだけだよ」
私をこんなにも大事に扱ってくれる人に、久々に出会ったような気がする。もちろん、彼はきっと私じゃなくても、他の女性でも同じようにしただろう。でも、それでもそういう気遣いを見せてくれることが何だかすごく嬉しい。都会の夜は暗いなりにも明るい。今の私の心も彼のおかげで少しは明るく光が灯っているかもしれない。
「はさっき楽しいって言ってたけど、本当にそうなのか?」
「え?」
「が今付き合ってる男は、以外にも恋人がいるんだろう?」
「うん、多分ね」
「そんな男と一緒にいて幸せなのか?」
静かな車内の中で、やけに言葉が響く。幸せ、そんなこと特に考えたことなかった。幸せか不幸かと問われれば、もちろん不幸ではないと答えられる。幸せでもない、不幸でもない。それで良いじゃないか。そんな男と、黄瀬くんと一緒にいて幸せを感じたことなんてないのだから。
「どこが良いんだ?」
「どこだろ。自分と少し似てるからかな」
そう、幸せは感じない。でも少しだけ安心はする。私と黄瀬くんは少しだけ似てる部分があるのだ。黄瀬くんはきっと気づいていないと思う。でも、黄瀬くんが隠しているその部分は私とそっくり。だから、一緒にいて少し安心するのかもしれない。
「はただ、寂しいだけだろう」
「寂しい?」
「彼に対して愛情ではなく、情になってるんじゃないのか?」
「…やっぱりすごいね、赤司くんは」
けど、彼が言ったことが必ずしも正解だとは思えない。間違いでもない。つまり、私に答えなんて分からないのだ。確かにそう言われればそうとも言えてしまう。でも、愛がなかったらもっと寂しいじゃない。なんて、愛なんてとっくに無い。いや、最初から存在していないのに彼の言葉に頷けなかったのは私の中で少しの蟠りがあるからだろう。
「そんな男やめて、オレにすれば良い」