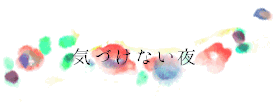気づかない男と、気づいていないフリをする男。どちらが正解でどちらが賢明かなんて誰にも分からない。けれど、どちらも幸せと言い切れないのは確かである。そんな今宵、ひとりの男はある事を確かめたかったのかもしれない。
その舞台となるのは恵比寿、時刻は21:17。渋谷にも目黒にも近いこの街は、サラリーマンやOLなど働き終わりの人間たちで、夜もほどほど適度に賑わっている。その街の一カ所、静かなダイニングバーではやたらと目立つ男性たちが数人。
「っていうか赤ちんは〜?」
「少し遅れるって連絡来てんだろ」
「え〜、呼び出した本人が遅れるってどういうことっスか」
「あいつはそういうヤツだと前にも言っただろう」
「先に始めてて良いそうですから、とりあえず乾杯しましょう」
彼らと赤司は中学時代、バスケでは「キセキの世代」と呼ばれるほどの選手たちだった。高校はそれぞれ別々の学校に進学したものの、やはり強者同士。大会で出会うことは多く、出会えばそれなりに会話をすることも多々あった。しかし、高校卒業後はバスケを本気でする者としない者に分かれ、彼らが会う回数も極端に少なくなる。故に今回の再会、しかも全員揃うのは久々と言っても過言ではない。きっかけは赤司。東京に戻ってきたのを機に、彼は久々にに全員を集めた。皆、バラバラのところにいるにも関わらず、このように全員集合出来るのは、おそらく呼び掛けたのが赤司だからだろう。
「やぁ、皆久しぶり。待たせたね」
22:05、赤司が合流しようやく全員が揃った。この全員での再会に疑問を持つ者も少なくはなく、何故このような場を急に持ち掛けたのか赤司に聞いた者がいたが、「別に。ただ何となくだよ。久々に旧友と会うのも悪くはないだろう」とあっさり言われてしまったのである。やはり赤司は何を考えているか分からない。そう何人かが思った。
話題は過去の事やバスケの事、と言うよりはそれぞれの現状についてである。互いのことに特に興味を抱いていない彼らなので、今日初めてそれぞれが今何をして、どんな風に生きているのかを知った。もちろん、仕事の話、そして当時彼らの間ではあまり語られることのなかった恋愛の話も、大人になった今なら出来るというところだろうか。
「えー!緑間っち婚約してんスか!?あの緑間っちが!?つか早っ!」
「黄瀬、うるさいのだよ!」
「確かお相手は年上の方でしたっけ?」
「まさか真太郎が一番早く結婚することになるとはな」
「意外〜。でもちょっと分かるかもー」
「人生何があるか分かんねーな」
このように恋愛の話で、しかも全員で盛り上がることなど、過去の彼らからは考えられない。時が彼らを大人にしてくれたのだろう。今のこの関係は悪いものではない、誰もが何となくではあるがそう思っていた。夜に映える彼らのこの話題は各々へと移る。それが偶然だったのか必然だったのかを意識する者などひとりもいない。いや、ただひとりを除いてだ。
「良いなー、緑間っち幸せそうで」
「確か黄瀬くんも彼女さんいますよね?」
「いるっちゃいるっスけどー」
「つーか、お前は他にも付き合ってる女いんだろ」
「まぁ付き合ってるっていうか、遊んでる子はそれなりにいるっスけど」
この黄瀬の発言は、同じ男として理解出来なくもない。いや、やはり理解出来ないという者がほとんどだった。おまけに何も悪びれることなく、隠すこともなく堂々としているその姿は共感なんてとてもじゃないけれど出来ない。という黄瀬の「彼女」という存在を知っている青峰は複雑な心境ではあるものの、黄瀬の「今」を全否定したことは今まで一度もないし、これからも恐らくない。しかし賛同することも、もちろんない。
「理解出来ないのだよ」
「でも、彼女はオレがそういうことしてるって気づいてると思う」
「それって黄瀬ちんが浮気してるってこと知ってて何も言わないってこと?」
「浮気っていうか…まぁ、でもそうっスね」
先ほどの緑間の幸せそうな話から一転、黄瀬の話で相殺されたようだ。もしかしたら、他人からしたら普通の恋愛とは少し違う、スリルのある面白い話だと思うかもしれない。けれど、彼らは他人同士ではない。それでも誰も何も言わないのは、黄瀬がこれらのことに対して一切の戸惑いも罪悪感も抱いていない。そしてそれを無理に改めさせるようと誰も思わなかったからだ。哀しいことに、今更誰かが何か言ったところで改まるとはとても思えなかった。
「赤司くんはどうなんですか?」
このままだと夜に消えてしまいそうな明るくない話題に、空気を読んだ黒子が赤司へと話題を移した。中学時代、キセキの世代と呼ばれた彼らはバスケ部内だけでなく、校内でも校外でもやはり目立つ存在であった。表立っての人気はやはりモデルとしての知名度がある黄瀬が一番だったものの、赤司も黄瀬同様、高い人気と評価を集めていた。全国優勝校の主将であり、おまけに頭脳明晰、容姿端麗、品行方正。キセキの世代以外は赤司の性格を奥まで知るものは多くなく、男子にも女子にも紳士的で穏やかそうなその性格は多くの人間を魅了した。けれど、彼のそのような恋愛に纏わる話は誰も聞いたことがない。部活を始め様々な分野で忙しいということもあっただろう。けれど、そのような話を彼の口からは誰も聞いたことがなかった。もしかしたら実は彼女という存在がいたのかもしれない。高校の時にも大学の時にもいたのかもしれない。それはここにいる誰も知らないことである。
「まだ付き合ってはいないけど、好きな女性はいるよ」
「へ〜、赤司っちが惚れる女の子って興味ある。」
「どんな人なんですか?」
「普通だよ。ただ、」
ここで一瞬、本当に一瞬ではあるが赤司は考えた。この「ただ、」に続く言葉を何と言うか。純粋な気持ちを吐露するべきか、それとも―。
赤司にとって今日のこの再会は決して無駄ではなかった。もちろん、純粋に旧友たちと久々の再会をしたかったのも事実。けれども、あるひとつの確信を持つことが出来たからだ。赤司らしくはない、少しだけ迷いや躊躇いが存在していたその感情。しかし、それらは全て星屑となって夜空に吸い込まれたようだ。
「ただ、何なのだよ」
「いや、どうやら恋人がいるみたいなんだよね」
「え!じゃあどうするんスか?」
「どうも何も、そんなこと関係ない」
「…略奪は厄介なことになるんじゃねーの」
この青峰の言葉には一瞬誰もが考えさせられた。赤司がはっきりとした言葉を述べなくても、彼がそんなことで諦めたりするような人間ではない事は、誰もが理解している。彼がこれからどうしようとしているのか想像するのは、ここにいる人間ならば容易かった。しかし、それは必ずしも褒められた行動ではないかもしれない。けれど蔑まれるような行動でもない。諦めるな、という人間もいれば諦めた方が良いという人間もいる。要は人それぞれの価値観なのである。恐らく、赤司のことだから手段は選ばない。けれど、そのように無理矢理手にした、幸せと勘違いしている幸せは果たして誰のためになるというのだろうか。青峰のこの言葉は真実かもしれないし、ただの懸念かもしれない。ただ、確かに誰もを考えさせる発言でもあった。
「ひとつ言っておくが、オレは略奪なんてしないよ」
「どうするつもりなんですか?」
「そんなことしなくても、きっと彼女はオレのところへ来る」
「赤ちんすごい自信だね」
「高校が一緒だったんだが、この前久々に会ってね。何となく分かったんだ」
赤司には絶対の自信がある。もちろん、本人が言った言葉の通り「略奪」、つまり無理矢理奪うなんていうことをするつもりは更々ない。ただ、彼女は絶対に自分のところへ戻って来る、戻ってきたくなるという絶対の自信がある。ましてや、今の人生に充実を感じていない彼女なら尚更。
「彼女にはオレが必要だって」
特に今日、黄瀬の現状を聞くことで確信したのだ。これでもし、黄瀬が少しでも今の自身の行動に罪悪感を抱いていたら違った感情が生まれていたかもしれない。いや、それでも彼女、には幸せになってほしいという根本の想いは変わらない。黄瀬と一緒にいても、きっと彼女は幸せにはなれない。彼女自身、それを望んではいないとは思うが、だったらせめて心の底から笑顔でいられるようにしてあげたいじゃないか。以前、と付き合いのあった赤司だからこそ、そう思うのかもしれない。
「でもその子と付き合ってる男かわいそーじゃない?絶対赤ちんに彼女取られるじゃん」
「いや、その男には他にも関係を持っている女性がいるみたいだから、特に何とも思わないんじゃないかな」
「何だソレ。黄瀬みたいなヤツじゃん」
「ちょっと!何てこと言うんスか!」
「でも、黄瀬くん否定出来ないでしょう」
「まぁそうっスけど」
「そんな男が何人もいるなんて尚更理解など出来ん」
まさか「黄瀬みたいな」が本当に黄瀬本人だなんてここにいる赤司以外、誰も想像していないだろう。だからこそ出来る気楽な会話である。先ほど赤司が夜空へまいた星屑が、そんな彼らを小さな光で照らしながら見守っている。無意味ではない彼らの関係を。
「それなら簡単にその子、彼女に出来そうだね〜」
「それがなかなか一筋縄ではいかなそうでね」
「赤司が女性に手こずるとは意外なのだよ」
「この前、『そんな男やめてオレにしたら良い』 ということを言ったんだが」
「え!もうそんなこと言ってるんスか!」
「流石赤司くん、積極的ですね」
「でも 『赤司くんでもそういう冗談言うんだね』 とあっさり言われてしまったよ」
「へー、ずいぶん落ち着いてる女だな」
けれども、それを全く戸惑うことなく微笑みながら語る赤司に、誰もが驚いた。同時に、赤司がその女性に対して本気だということが、友人である彼らには分かった。彼がひとりの女性に心を奪われる日が来るとは些か信じがたいことでもあるが、彼もひとりの男。確かに超越したものを数多く持ってはいるが、恋愛においてはひとりの男性と変わらないのだ。
「いつか皆にも紹介出来る日が来ると思うよ」
いつかそんな日が―、
その舞台となるのは恵比寿、時刻は21:17。渋谷にも目黒にも近いこの街は、サラリーマンやOLなど働き終わりの人間たちで、夜もほどほど適度に賑わっている。その街の一カ所、静かなダイニングバーではやたらと目立つ男性たちが数人。
「っていうか赤ちんは〜?」
「少し遅れるって連絡来てんだろ」
「え〜、呼び出した本人が遅れるってどういうことっスか」
「あいつはそういうヤツだと前にも言っただろう」
「先に始めてて良いそうですから、とりあえず乾杯しましょう」
彼らと赤司は中学時代、バスケでは「キセキの世代」と呼ばれるほどの選手たちだった。高校はそれぞれ別々の学校に進学したものの、やはり強者同士。大会で出会うことは多く、出会えばそれなりに会話をすることも多々あった。しかし、高校卒業後はバスケを本気でする者としない者に分かれ、彼らが会う回数も極端に少なくなる。故に今回の再会、しかも全員揃うのは久々と言っても過言ではない。きっかけは赤司。東京に戻ってきたのを機に、彼は久々にに全員を集めた。皆、バラバラのところにいるにも関わらず、このように全員集合出来るのは、おそらく呼び掛けたのが赤司だからだろう。
「やぁ、皆久しぶり。待たせたね」
22:05、赤司が合流しようやく全員が揃った。この全員での再会に疑問を持つ者も少なくはなく、何故このような場を急に持ち掛けたのか赤司に聞いた者がいたが、「別に。ただ何となくだよ。久々に旧友と会うのも悪くはないだろう」とあっさり言われてしまったのである。やはり赤司は何を考えているか分からない。そう何人かが思った。
話題は過去の事やバスケの事、と言うよりはそれぞれの現状についてである。互いのことに特に興味を抱いていない彼らなので、今日初めてそれぞれが今何をして、どんな風に生きているのかを知った。もちろん、仕事の話、そして当時彼らの間ではあまり語られることのなかった恋愛の話も、大人になった今なら出来るというところだろうか。
「えー!緑間っち婚約してんスか!?あの緑間っちが!?つか早っ!」
「黄瀬、うるさいのだよ!」
「確かお相手は年上の方でしたっけ?」
「まさか真太郎が一番早く結婚することになるとはな」
「意外〜。でもちょっと分かるかもー」
「人生何があるか分かんねーな」
このように恋愛の話で、しかも全員で盛り上がることなど、過去の彼らからは考えられない。時が彼らを大人にしてくれたのだろう。今のこの関係は悪いものではない、誰もが何となくではあるがそう思っていた。夜に映える彼らのこの話題は各々へと移る。それが偶然だったのか必然だったのかを意識する者などひとりもいない。いや、ただひとりを除いてだ。
「良いなー、緑間っち幸せそうで」
「確か黄瀬くんも彼女さんいますよね?」
「いるっちゃいるっスけどー」
「つーか、お前は他にも付き合ってる女いんだろ」
「まぁ付き合ってるっていうか、遊んでる子はそれなりにいるっスけど」
この黄瀬の発言は、同じ男として理解出来なくもない。いや、やはり理解出来ないという者がほとんどだった。おまけに何も悪びれることなく、隠すこともなく堂々としているその姿は共感なんてとてもじゃないけれど出来ない。という黄瀬の「彼女」という存在を知っている青峰は複雑な心境ではあるものの、黄瀬の「今」を全否定したことは今まで一度もないし、これからも恐らくない。しかし賛同することも、もちろんない。
「理解出来ないのだよ」
「でも、彼女はオレがそういうことしてるって気づいてると思う」
「それって黄瀬ちんが浮気してるってこと知ってて何も言わないってこと?」
「浮気っていうか…まぁ、でもそうっスね」
先ほどの緑間の幸せそうな話から一転、黄瀬の話で相殺されたようだ。もしかしたら、他人からしたら普通の恋愛とは少し違う、スリルのある面白い話だと思うかもしれない。けれど、彼らは他人同士ではない。それでも誰も何も言わないのは、黄瀬がこれらのことに対して一切の戸惑いも罪悪感も抱いていない。そしてそれを無理に改めさせるようと誰も思わなかったからだ。哀しいことに、今更誰かが何か言ったところで改まるとはとても思えなかった。
「赤司くんはどうなんですか?」
このままだと夜に消えてしまいそうな明るくない話題に、空気を読んだ黒子が赤司へと話題を移した。中学時代、キセキの世代と呼ばれた彼らはバスケ部内だけでなく、校内でも校外でもやはり目立つ存在であった。表立っての人気はやはりモデルとしての知名度がある黄瀬が一番だったものの、赤司も黄瀬同様、高い人気と評価を集めていた。全国優勝校の主将であり、おまけに頭脳明晰、容姿端麗、品行方正。キセキの世代以外は赤司の性格を奥まで知るものは多くなく、男子にも女子にも紳士的で穏やかそうなその性格は多くの人間を魅了した。けれど、彼のそのような恋愛に纏わる話は誰も聞いたことがない。部活を始め様々な分野で忙しいということもあっただろう。けれど、そのような話を彼の口からは誰も聞いたことがなかった。もしかしたら実は彼女という存在がいたのかもしれない。高校の時にも大学の時にもいたのかもしれない。それはここにいる誰も知らないことである。
「まだ付き合ってはいないけど、好きな女性はいるよ」
「へ〜、赤司っちが惚れる女の子って興味ある。」
「どんな人なんですか?」
「普通だよ。ただ、」
ここで一瞬、本当に一瞬ではあるが赤司は考えた。この「ただ、」に続く言葉を何と言うか。純粋な気持ちを吐露するべきか、それとも―。
赤司にとって今日のこの再会は決して無駄ではなかった。もちろん、純粋に旧友たちと久々の再会をしたかったのも事実。けれども、あるひとつの確信を持つことが出来たからだ。赤司らしくはない、少しだけ迷いや躊躇いが存在していたその感情。しかし、それらは全て星屑となって夜空に吸い込まれたようだ。
「ただ、何なのだよ」
「いや、どうやら恋人がいるみたいなんだよね」
「え!じゃあどうするんスか?」
「どうも何も、そんなこと関係ない」
「…略奪は厄介なことになるんじゃねーの」
この青峰の言葉には一瞬誰もが考えさせられた。赤司がはっきりとした言葉を述べなくても、彼がそんなことで諦めたりするような人間ではない事は、誰もが理解している。彼がこれからどうしようとしているのか想像するのは、ここにいる人間ならば容易かった。しかし、それは必ずしも褒められた行動ではないかもしれない。けれど蔑まれるような行動でもない。諦めるな、という人間もいれば諦めた方が良いという人間もいる。要は人それぞれの価値観なのである。恐らく、赤司のことだから手段は選ばない。けれど、そのように無理矢理手にした、幸せと勘違いしている幸せは果たして誰のためになるというのだろうか。青峰のこの言葉は真実かもしれないし、ただの懸念かもしれない。ただ、確かに誰もを考えさせる発言でもあった。
「ひとつ言っておくが、オレは略奪なんてしないよ」
「どうするつもりなんですか?」
「そんなことしなくても、きっと彼女はオレのところへ来る」
「赤ちんすごい自信だね」
「高校が一緒だったんだが、この前久々に会ってね。何となく分かったんだ」
赤司には絶対の自信がある。もちろん、本人が言った言葉の通り「略奪」、つまり無理矢理奪うなんていうことをするつもりは更々ない。ただ、彼女は絶対に自分のところへ戻って来る、戻ってきたくなるという絶対の自信がある。ましてや、今の人生に充実を感じていない彼女なら尚更。
「彼女にはオレが必要だって」
特に今日、黄瀬の現状を聞くことで確信したのだ。これでもし、黄瀬が少しでも今の自身の行動に罪悪感を抱いていたら違った感情が生まれていたかもしれない。いや、それでも彼女、には幸せになってほしいという根本の想いは変わらない。黄瀬と一緒にいても、きっと彼女は幸せにはなれない。彼女自身、それを望んではいないとは思うが、だったらせめて心の底から笑顔でいられるようにしてあげたいじゃないか。以前、と付き合いのあった赤司だからこそ、そう思うのかもしれない。
「でもその子と付き合ってる男かわいそーじゃない?絶対赤ちんに彼女取られるじゃん」
「いや、その男には他にも関係を持っている女性がいるみたいだから、特に何とも思わないんじゃないかな」
「何だソレ。黄瀬みたいなヤツじゃん」
「ちょっと!何てこと言うんスか!」
「でも、黄瀬くん否定出来ないでしょう」
「まぁそうっスけど」
「そんな男が何人もいるなんて尚更理解など出来ん」
まさか「黄瀬みたいな」が本当に黄瀬本人だなんてここにいる赤司以外、誰も想像していないだろう。だからこそ出来る気楽な会話である。先ほど赤司が夜空へまいた星屑が、そんな彼らを小さな光で照らしながら見守っている。無意味ではない彼らの関係を。
「それなら簡単にその子、彼女に出来そうだね〜」
「それがなかなか一筋縄ではいかなそうでね」
「赤司が女性に手こずるとは意外なのだよ」
「この前、『そんな男やめてオレにしたら良い』 ということを言ったんだが」
「え!もうそんなこと言ってるんスか!」
「流石赤司くん、積極的ですね」
「でも 『赤司くんでもそういう冗談言うんだね』 とあっさり言われてしまったよ」
「へー、ずいぶん落ち着いてる女だな」
けれども、それを全く戸惑うことなく微笑みながら語る赤司に、誰もが驚いた。同時に、赤司がその女性に対して本気だということが、友人である彼らには分かった。彼がひとりの女性に心を奪われる日が来るとは些か信じがたいことでもあるが、彼もひとりの男。確かに超越したものを数多く持ってはいるが、恋愛においてはひとりの男性と変わらないのだ。
「いつか皆にも紹介出来る日が来ると思うよ」
いつかそんな日が―、