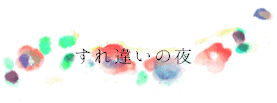金曜日の22:57。家に帰ると玄関には華奢な女物の靴が置かれていた。7cm、という世間では女性の脚を最も美しく見せると言われている高さだろうか。それが彼女の靴だとすぐに分かったのは当たり前のこと。何故ならこの部屋の鍵を持っているのはオレ以外に彼女しかいない。ヒールのない靴もヒールのある靴も、どちらも履く彼女は特にヒールの高さなんて気にしていないのだろう。ただ、この靴を履く彼女と隣を歩いたことは一度もない気がする。
廊下を通ると人がいる雰囲気。それから鼻と食欲をくすぐるニオイ。そういえば今日は仕事が忙しくて夜ご飯を食べ損ねたことを思い出した。リビングのドアを開けるとキッチンに立っている彼女の姿が目に入る。久々に見た彼女は、今までと少しだけ雰囲気が違うような気がする。ただ、どこが違うかと聞かれても答えることは出来ない。
「あ、おかえり。お邪魔してます」
「…ただいま、」
「どうかした?」
「んーん。ってか何作ってんスか?」
「オニオングラタンスープ」
「マジ!?オレ超腹減ってるんスよー!」
「じゃあ、ちょうど良かった」
彼女がこうしてオレの家のキッチンに立って料理を作ってくれるのは初めてじゃない。不思議なのはいつも、オレがいつ・何を食べたいかを理解してくれているということ。彼女からしたら適当なのかもしれないけれど、オレにとってそれはとてもじゃないけれど偶然には思えなかった。荷物を適当に置いて椅子に座って彼女の後ろ姿をボーっと眺める。
そういえば、彼女と会うのは何日ぶりだろうか。彼女といる時だけはとても楽である。自分を作らなくて良い。自分のありのままの姿を見せても彼女はオレを拒絶しない。何より奥深いところに侵入してこないその存在は、オレにとってはとても貴重だった。
出来立てのオニオングラタンスープが運ばれてくると、その湯気に視界が少し歪む。
「はい、お待たせ」
「のご飯久しぶりっス」
「そうだっけ?」
いつからだっただろうか。人が傍にいるということ、人の温もりを感じるということがとても嬉しくて、同時にとても煩わしいと思うようになったのは。この矛盾と戦うこと自体が嫌でたまらなくて、結局今も中途半端に生きている。温もりだって何だって、欲しいものはこの恵まれた自分自身の存在のおかげで大抵は手に入る。でも、満たされたことなんて今まで一度もない。本当に欲しいものが無いからか、それとも本当に欲しいものが何かも分かっていないからか。
腹も満たされたオレは彼女が後片付けをしてくれている間にシャワーを浴びることにした。浴室には彼女がお気に入りだという世間でも人気のボディソープにシャンプーやリンス、トリートメントまで置かれている。同棲しているわけでも頻繁にここに来るわけでもないが、当たり前のように置かれているそれらは、もう残りも少なくあと少しで終わりそうだ。少し前までは同じボディソープにシャンプー、リンスを使っていたのに飽きたからと言って違うものを使い始めた。この香りがする度にオレは彼女を思い出す。例え隣にいる女の子が彼女じゃなくても、この香りがすると思い浮かぶのは彼女の存在。
「あ、また。髪の毛ちゃんと乾かしてきなよっていつも言ってるでしょ」
「すぐ乾くっスよ」
「乾かない。ドライヤー持ってきて」
戻ってきたオレを絨毯の上に座らせると、彼女はソファーに座ってドライヤーのスイッチを入れた。彼女の小さな手で乾かされるオレの髪は、彼女にはどう映っているのだろうか。熱い風が少し心地良い。けれど、数十秒ほどすると彼女はドライヤーをターボにした。ターボになんかしてくれなくても良かったのに。このまましばらく髪なんて乾かなくても良い、そう思った。いや、髪だけじゃない。渇かなくて良いと思ったのは他にもっと大事な―
「あー気持ちー」
「まったくもう」
スイッチが切られた。完璧に乾かされたオレの髪からはもう水は滴り落ちない。でも、先ほど作った絨毯の上に落ちた雫はまだ乾いてはいないようだ。
「今日泊まってくっスよね?」
「うーん、どうしようかなと思って」
「え、もうこんな時間っスよ」
「治ったけど風邪引いたあとだから、もし黄瀬くんに移しちゃったら」
「え、大丈夫っスか!?」
彼女が座っているソファーに勢いよく身体を移すと、オレの重みで少しソファーが軋んで沈んだ。彼女の額に自分の額を合わせる。「もう治ったって言ったじゃん」と言う彼女の言う通り、彼女から熱は感じられない。ふ、っと笑みを見せたオレに彼女はいち早く気づいたようだ。ちゅっと音を立てるようにそのまま唇を重ねると、何だかこの曖昧な感情も重ねられるような気がした。でも、そんな可愛いリップ音だけで満足出来るほど、ガキでもないしオトナでもない。止まらない口づけは彼女の唇をより艶やかにする。
「ね、ベッド行こ?」
「…さっき言ったこと聞いてた?」
「もう今更…ね?」
そのまま彼女を横抱きにして今度はソファーではなくベッドの上を軋ませれば、温もりの出来上がり。白いシーツの上で重なるこの温もりは、決して白に染まることはない。ただどうしようもないくらい温かくて離れたくなくなる。感じる温度も、漏れる音も、揺らぐ視界も、何もかもが麻痺してくる。けれど、それは絶対に悟られたくない。そんな演技をしながら彼女の肌の上を滑るオレは、滑稽に見えるだろうか。
こんなこと、愛がなくても出来る。でも、他の女と重なりたいと思ったことはない。そう思う自分が何より信じられなかった。
最初は少し恋人同士ぽいことをしてあげれば、扱いやすくなるだろうと思った。けど、彼女は強かった。決してオレに流されない。そんなオレの周りにいるような女たちとは違うところに惹かれているのかもしれない。でもだからこそ、彼女がもしオレに惹かれたらと思うとこわいのだ。そんな日が来るとは今のところ思えない。けど、そんなことがあったらオレはきっと彼女を他の女と同じようにしか見なくなる。そしたらこの曖昧で楽な関係も何もかも、すべて終わりだ。
「かわいい」
「ん、その言葉聞き飽きたよ」
「本当つれないっスね」
オレに恋人がいるという噂があるだけで、そしてリアリティがあるだけで、オレにしつこく付き纏ってくる女は確かに減った。遊び程度に近寄って来る女は未だにたくさんいるが、そんなものは簡単にあしらえる。それに誰かといたい時にはそのくらいの女たちといるのがちょうど良い。お互い後腐れがない。何より失っても構わないからだ。そして、そんなオレを知りながらも何も言わない彼女の存在。このふたつのバランスが楽で手放したくなくて、こんなことを続けているのかもしれない。
夜が明けたはずなのに、カーテンのせいでまだ暗い。ほのかに入る光りが彼女の白い肌を輝かせるが、オレにはその光りは届かない。起き上がる気にはまだとてもなれなくて、何となく彼女の身体を抱き寄せる。すでに起きていたらしい彼女が眩しいと、この時オレは初めて思った。
「ねぇ、黄瀬くん」
「何?」
「私、もうここには来ないと思う」
朝だから寝ぼけているのだろうか、それとも幻聴だろうか。紡がれると全く思っていなかった言葉が、この裸にひどく突き刺さる。柄にもなく、少し動揺した。どういう意味だろうか、そういう意味だろう。オレの腕の中にいる彼女は確かに存在しているというのに、まるで温もりが感じられない。先ほどまでの温かさもすべて夢だったというのだろうか。
「どういう意味?」
「止まり木が、 」
「え?」
「…黄瀬くんに付き纏ってくる女の子、だいぶいなくなったんじゃない?」
「まぁ、そうっスね」
「じゃあ何もこんな曖昧な関係をもう続けなくても良いと思う」
もしかしたら「こんな曖昧な関係はやめてちゃんとした恋人同士になりたい」とでも言われるのかと一瞬思った。けれど、すぐに彼女はそんなことを言うような女ではないと思い直した。始まりのための終わり、でないのなら終わりのための終わりなのだろう。
「好きな男でも出来た?」
「まさか」
「じゃあ別に今のままでも良いじゃないっスか」
「中途半端に生きていくことはもう、やめることにしたの」
自分に言われているような気がした。中途半端なのは彼女じゃない、オレだ。毎日、充実はしている。毎日、何気なく過ごしている。毎日、適当に過ごしている。何に一生懸命になることもない。仕事だって向いてるからただ何となくやってるだけだ。恋愛だって―。彼女にも中途半端、愛を注いだなんてとてもじゃないけれど言えない。他の女の子との関係も中途半端。もちろん、こちらも愛情を注いだなんて言えない。そもそも、愛が何かも分かっていないのに、中途半端以外にどうやってこなしていけば良いんだよ。
「別に黄瀬くんのことを嫌いなったわけじゃない」
「でも好きじゃないって?」
「分からない。好きってどう思ったら好きなのかも分からないし」
―ただつまらなさだったり温もりを埋めるために何の感情もなく一緒にいたり、ひとつの「行為」としてこういうことを続けるなんて、虚しさが余計増すだけだって。前から分かってはいたけど、やっぱりそんな虚しさに甘えたくなんてないから。
そんな彼女の言葉は意味が分からないように聞こえて、本当は全部理解出来る。彼女はオレと似ているところがあるから。だからオレのことを他の人間より理解してくれている。でもだからこそ、向き合えないのかもしれない。こんな中途半端、いったい意味があるのだろうか。
「黄瀬くんは?」
「え?」
「…ううん、やっぱり何でもない。答えを聞きたいわけじゃないから」
「、」
「今までありがとう。バイバイ」
腕の中からいなくなった温度に慣れないまま、ベッドの中が冷たくなる。結局光りがオレへ当たることもなく、気がついたらいつの間にか夕暮れの時間に迫っていた。一体どのくらいこうしていたのだろう。いつものように感情のない「ありがとう」を告げることが出来ればそれでリセット出来たのにそれさえも出来ないなんて。オレはこの曖昧な関係に幕が閉じられたことに喜んでいるのか悲しんでいるのか。それとも何の感情も抱いていないのか。そんな迷いに襲われることさえも躊躇いの何者以外でもなくて、煩わしくなったその思考は面倒くさいのですべて捨てることにした。でも、最初から何も持っていないんだから、捨てるものなんて何もない。だから代わりに、テーブルの上に置かれていた鍵を粉々にして捨てようと思った。
廊下を通ると人がいる雰囲気。それから鼻と食欲をくすぐるニオイ。そういえば今日は仕事が忙しくて夜ご飯を食べ損ねたことを思い出した。リビングのドアを開けるとキッチンに立っている彼女の姿が目に入る。久々に見た彼女は、今までと少しだけ雰囲気が違うような気がする。ただ、どこが違うかと聞かれても答えることは出来ない。
「あ、おかえり。お邪魔してます」
「…ただいま、」
「どうかした?」
「んーん。ってか何作ってんスか?」
「オニオングラタンスープ」
「マジ!?オレ超腹減ってるんスよー!」
「じゃあ、ちょうど良かった」
彼女がこうしてオレの家のキッチンに立って料理を作ってくれるのは初めてじゃない。不思議なのはいつも、オレがいつ・何を食べたいかを理解してくれているということ。彼女からしたら適当なのかもしれないけれど、オレにとってそれはとてもじゃないけれど偶然には思えなかった。荷物を適当に置いて椅子に座って彼女の後ろ姿をボーっと眺める。
そういえば、彼女と会うのは何日ぶりだろうか。彼女といる時だけはとても楽である。自分を作らなくて良い。自分のありのままの姿を見せても彼女はオレを拒絶しない。何より奥深いところに侵入してこないその存在は、オレにとってはとても貴重だった。
出来立てのオニオングラタンスープが運ばれてくると、その湯気に視界が少し歪む。
「はい、お待たせ」
「のご飯久しぶりっス」
「そうだっけ?」
いつからだっただろうか。人が傍にいるということ、人の温もりを感じるということがとても嬉しくて、同時にとても煩わしいと思うようになったのは。この矛盾と戦うこと自体が嫌でたまらなくて、結局今も中途半端に生きている。温もりだって何だって、欲しいものはこの恵まれた自分自身の存在のおかげで大抵は手に入る。でも、満たされたことなんて今まで一度もない。本当に欲しいものが無いからか、それとも本当に欲しいものが何かも分かっていないからか。
腹も満たされたオレは彼女が後片付けをしてくれている間にシャワーを浴びることにした。浴室には彼女がお気に入りだという世間でも人気のボディソープにシャンプーやリンス、トリートメントまで置かれている。同棲しているわけでも頻繁にここに来るわけでもないが、当たり前のように置かれているそれらは、もう残りも少なくあと少しで終わりそうだ。少し前までは同じボディソープにシャンプー、リンスを使っていたのに飽きたからと言って違うものを使い始めた。この香りがする度にオレは彼女を思い出す。例え隣にいる女の子が彼女じゃなくても、この香りがすると思い浮かぶのは彼女の存在。
「あ、また。髪の毛ちゃんと乾かしてきなよっていつも言ってるでしょ」
「すぐ乾くっスよ」
「乾かない。ドライヤー持ってきて」
戻ってきたオレを絨毯の上に座らせると、彼女はソファーに座ってドライヤーのスイッチを入れた。彼女の小さな手で乾かされるオレの髪は、彼女にはどう映っているのだろうか。熱い風が少し心地良い。けれど、数十秒ほどすると彼女はドライヤーをターボにした。ターボになんかしてくれなくても良かったのに。このまましばらく髪なんて乾かなくても良い、そう思った。いや、髪だけじゃない。渇かなくて良いと思ったのは他にもっと大事な―
「あー気持ちー」
「まったくもう」
スイッチが切られた。完璧に乾かされたオレの髪からはもう水は滴り落ちない。でも、先ほど作った絨毯の上に落ちた雫はまだ乾いてはいないようだ。
「今日泊まってくっスよね?」
「うーん、どうしようかなと思って」
「え、もうこんな時間っスよ」
「治ったけど風邪引いたあとだから、もし黄瀬くんに移しちゃったら」
「え、大丈夫っスか!?」
彼女が座っているソファーに勢いよく身体を移すと、オレの重みで少しソファーが軋んで沈んだ。彼女の額に自分の額を合わせる。「もう治ったって言ったじゃん」と言う彼女の言う通り、彼女から熱は感じられない。ふ、っと笑みを見せたオレに彼女はいち早く気づいたようだ。ちゅっと音を立てるようにそのまま唇を重ねると、何だかこの曖昧な感情も重ねられるような気がした。でも、そんな可愛いリップ音だけで満足出来るほど、ガキでもないしオトナでもない。止まらない口づけは彼女の唇をより艶やかにする。
「ね、ベッド行こ?」
「…さっき言ったこと聞いてた?」
「もう今更…ね?」
そのまま彼女を横抱きにして今度はソファーではなくベッドの上を軋ませれば、温もりの出来上がり。白いシーツの上で重なるこの温もりは、決して白に染まることはない。ただどうしようもないくらい温かくて離れたくなくなる。感じる温度も、漏れる音も、揺らぐ視界も、何もかもが麻痺してくる。けれど、それは絶対に悟られたくない。そんな演技をしながら彼女の肌の上を滑るオレは、滑稽に見えるだろうか。
こんなこと、愛がなくても出来る。でも、他の女と重なりたいと思ったことはない。そう思う自分が何より信じられなかった。
最初は少し恋人同士ぽいことをしてあげれば、扱いやすくなるだろうと思った。けど、彼女は強かった。決してオレに流されない。そんなオレの周りにいるような女たちとは違うところに惹かれているのかもしれない。でもだからこそ、彼女がもしオレに惹かれたらと思うとこわいのだ。そんな日が来るとは今のところ思えない。けど、そんなことがあったらオレはきっと彼女を他の女と同じようにしか見なくなる。そしたらこの曖昧で楽な関係も何もかも、すべて終わりだ。
「かわいい」
「ん、その言葉聞き飽きたよ」
「本当つれないっスね」
オレに恋人がいるという噂があるだけで、そしてリアリティがあるだけで、オレにしつこく付き纏ってくる女は確かに減った。遊び程度に近寄って来る女は未だにたくさんいるが、そんなものは簡単にあしらえる。それに誰かといたい時にはそのくらいの女たちといるのがちょうど良い。お互い後腐れがない。何より失っても構わないからだ。そして、そんなオレを知りながらも何も言わない彼女の存在。このふたつのバランスが楽で手放したくなくて、こんなことを続けているのかもしれない。
夜が明けたはずなのに、カーテンのせいでまだ暗い。ほのかに入る光りが彼女の白い肌を輝かせるが、オレにはその光りは届かない。起き上がる気にはまだとてもなれなくて、何となく彼女の身体を抱き寄せる。すでに起きていたらしい彼女が眩しいと、この時オレは初めて思った。
「ねぇ、黄瀬くん」
「何?」
「私、もうここには来ないと思う」
朝だから寝ぼけているのだろうか、それとも幻聴だろうか。紡がれると全く思っていなかった言葉が、この裸にひどく突き刺さる。柄にもなく、少し動揺した。どういう意味だろうか、そういう意味だろう。オレの腕の中にいる彼女は確かに存在しているというのに、まるで温もりが感じられない。先ほどまでの温かさもすべて夢だったというのだろうか。
「どういう意味?」
「止まり木が、 」
「え?」
「…黄瀬くんに付き纏ってくる女の子、だいぶいなくなったんじゃない?」
「まぁ、そうっスね」
「じゃあ何もこんな曖昧な関係をもう続けなくても良いと思う」
もしかしたら「こんな曖昧な関係はやめてちゃんとした恋人同士になりたい」とでも言われるのかと一瞬思った。けれど、すぐに彼女はそんなことを言うような女ではないと思い直した。始まりのための終わり、でないのなら終わりのための終わりなのだろう。
「好きな男でも出来た?」
「まさか」
「じゃあ別に今のままでも良いじゃないっスか」
「中途半端に生きていくことはもう、やめることにしたの」
自分に言われているような気がした。中途半端なのは彼女じゃない、オレだ。毎日、充実はしている。毎日、何気なく過ごしている。毎日、適当に過ごしている。何に一生懸命になることもない。仕事だって向いてるからただ何となくやってるだけだ。恋愛だって―。彼女にも中途半端、愛を注いだなんてとてもじゃないけれど言えない。他の女の子との関係も中途半端。もちろん、こちらも愛情を注いだなんて言えない。そもそも、愛が何かも分かっていないのに、中途半端以外にどうやってこなしていけば良いんだよ。
「別に黄瀬くんのことを嫌いなったわけじゃない」
「でも好きじゃないって?」
「分からない。好きってどう思ったら好きなのかも分からないし」
―ただつまらなさだったり温もりを埋めるために何の感情もなく一緒にいたり、ひとつの「行為」としてこういうことを続けるなんて、虚しさが余計増すだけだって。前から分かってはいたけど、やっぱりそんな虚しさに甘えたくなんてないから。
そんな彼女の言葉は意味が分からないように聞こえて、本当は全部理解出来る。彼女はオレと似ているところがあるから。だからオレのことを他の人間より理解してくれている。でもだからこそ、向き合えないのかもしれない。こんな中途半端、いったい意味があるのだろうか。
「黄瀬くんは?」
「え?」
「…ううん、やっぱり何でもない。答えを聞きたいわけじゃないから」
「、」
「今までありがとう。バイバイ」
腕の中からいなくなった温度に慣れないまま、ベッドの中が冷たくなる。結局光りがオレへ当たることもなく、気がついたらいつの間にか夕暮れの時間に迫っていた。一体どのくらいこうしていたのだろう。いつものように感情のない「ありがとう」を告げることが出来ればそれでリセット出来たのにそれさえも出来ないなんて。オレはこの曖昧な関係に幕が閉じられたことに喜んでいるのか悲しんでいるのか。それとも何の感情も抱いていないのか。そんな迷いに襲われることさえも躊躇いの何者以外でもなくて、煩わしくなったその思考は面倒くさいのですべて捨てることにした。でも、最初から何も持っていないんだから、捨てるものなんて何もない。だから代わりに、テーブルの上に置かれていた鍵を粉々にして捨てようと思った。