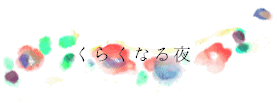女を何人でも抱きしめることが出来るこの手は、女をひとり止めることさえも叶わない。無しか存在していなかったそこに、少しでも愛が存在していたら、こんな真っ暗に覆われた夜空を歩かなくても良かったのだろう。
目の前のグラスには自分の情けない顔が映っている。冷えすぎてグラスに滴る水滴は、温度に耐え切れなくなった涙とでも言うつもりか。そんな目の前のグラスさえも煩わしくて、中身を一気に飲み干しすべてを消した。けど、空っぽになったグラスが今度は可哀相に思えて慌てて追加注文する。これが悪循環の始まりである。
「つーか何なんだよ、お前は」
「別にー。ただ青峰っちと飲みたいって思っただけっスよ」
六本木の街を歩くにしては早い19時頃。土曜日の夜という、世間ではデートや合コン、飲み会で盛り上がる時に男二人で酒だなんて、何とも言えない。そういえば、とは今まで一緒に酒を飲んだことが一度もないような気がする。そもそも彼女は普段からお酒を飲む人間なのだろうか。そんなことさえも知らない自分に今頃気づいた。
カウンターで横に腰掛けている青峰っちは、オレとが付き合っている−否、付き合っていたということを知る数少ない人間である。そして、おそらくオレとの距離感も気づいている。それぞれが知り合いだったという時には流石に全員が驚いたものの、3人とも特に干渉し合わない性格なおかげか特に困るようなことは一切なかった。
「オレ、と終わったんスよ」
「あっそ」
「ええ!?ちょ、それだけっスか!?」
「むしろお前らが続いてたことの方が不思議だろ」
本人たちだけではない、周りから見ても不自然な関係だったらしい。その不自然さに、お互い気づいていたのに気づいていないフリをしてごまかし続けて、その結果がこんな有様だとは情けないにも程がある。
こんな終わりを望んでいたわけじゃない。けれど、どんな終わりを望んでいたかと問われても答えることは出来ない。終わり以外の結末なんて存在していないのだから、いつかは終わりが来る付き合いだったはず。なのに、いつの間にかそんなことも忘れていて、続くわけがないこの関係はずっと続くとまで錯覚していた日々さえも、今となっては懐かしい。
「どっちも避け合ってたのに」
―カラン。持っていたグラスの中の氷が揺れた。自分の迷いや戸惑い、それらすべてが腕から指を伝って中の氷が悲鳴を上げた。崩れた氷の音がやけに響いて聞こえたのは、きっと気のせいなんかではないのだろう。
避け合っていた、と言われれば確かにそれは否定しない。はオレに、オレはに必要以上に踏み込まなかった。踏み込めなかったと言う方が正しいだろう。始まりも簡単なら、終わりも簡単。そんな考えは悲しいことに浅はかだった。滑稽に感じた自分自身に、呆れた笑い声さえ漏れる。
「つーか、お前他にも女いんだから別ににこだわる必要ねーだろ」
「は“一応”彼女だったんスよ」
「じゃあ他の女は何なんだよ」
「そう聞かれると何て答えれば良いか分かんないっスね」
今思えば、と初めて会った時に「付き合う」だとか「恋人」というフレーズを出したからこういう関係になったのだろう。だったらいっそのこと他の女と同じ立ち位置だった方が良かったのかもしれない。そしたらきっと、何も思うことなんてなかったのに。
をあくまで「彼女」に選んだのは偶然だったはずだ。たまたま会って、たまたま抱きしめて、たまたまキスして、たまたまオレに興味がない、たまたまそれなりの容姿だった。そんなは、オレの予想以上に「彼女」を務めてくれた。本当に最低限の付き合いで。
「もっと単純なことなんじゃねーの?」
「単純って?」
「だけは他の女と違う、今までの女とは違うから一応でも彼女なんだろ」
「まぁ多分そうなるんスかね」
そう、彼女は他の女とは違うということだけは明確。「彼女」なんだから当たり前だ。どこが違うと問われたところで答えは出なくても「違う」とだけは断言出来る。今思えば、の肌触りもの香りもすぐに思い出せる。があまり表情を変えずに喋る姿も、儚げに笑う顔も、キスをしたあとの余韻だって思い出せる。靄がかかったようにぼやけていた世界は、オレの家の中にがいる時だけ、少し輪郭が浮き出たような気がしていた。それがオレの錯覚でなければ。
「だから、そういうことなんじゃねーの」
―カラン。すべての思考と動作がコンマ数秒の世界で停止したと思うほど、その言葉は衝撃的だった。そういうこと、他の女とは違うということ。つまり、はオレにとって「特別」だったと言いたいのだろう。そんなこと今まで全く意識したことがなかった。当然、気づくわけもない。けど、紛れもなく特別な存在。曖昧な存在で特別な存在、手を伸ばしたくても伸ばせなかった、伸ばさなかった存在だということだろうか。
そうか、未だに逃げているのはオレだけだ。
あれからしばらくして解散したあと、オレは酔いを冷ますために六本木の街を歩くことにした。驚くことに時間はまだ21時。飲んでいた時間はたった2時間くらいなのに、随分と酔いが回ったような気がする。相変わらず人が多いこの街の音たちは、耳を通り過ぎ頭の中を通り抜けていくようだ。華やかな光やネオンは目に痛い。眩しすぎて、目を閉じてしまいそうになるところを、必死で堪える。目を閉じたら人混みに埋もれてしまう、人にぶつかってしまう。そう思って開けていたこの瞳は、見ない方が良かった世界を捉えてしまった。
横断歩道を抜けたところで遭遇したのは、初めて見た眩しい輝き。きっとオレが隣だったら輝かないそのダイヤは、この光で溢れた街に紛れることなく、一際目立つように存在している。隣がもしオレだったら、きっとそのダイヤは輝くことも出来ずに、この明るいようで暗い夜景に紛れて見つけることすら出来ないだろう。星も見えない都会の真っ暗な空は、光のおかげで明るく見えているのかもしれない。
「あれ、黄瀬くん?」
その声はこの騒音の中でも、ノイズキャンセリングつきのイヤホンから出てくる音のようにクリアに聞こえた。そこまで久々ではない。むしろ「恋人」の関係でいた時でも会わない期間が長いことは度々あったのだから、今更そんなことを気にすること自体、可笑しい。けれどもっと可笑しいのは目に映る光景。どうして、どうしての隣にはかつての旧友が存在しているのだろうか。
「…と赤司っち!?」
「黄瀬じゃないか、偶然だね」
一瞬、声を出すことにさえ戸惑った。何故、彼が。何故、彼女と一緒に。何故、彼女の隣にいる。たくさんの数えきれない疑問を頭の中でぐるぐると回すが、そう思っていたのはどうやらオレだけではないらしい。驚いているを見て、オレはあることを思った。”ってこんなに背高かったっけ?”どうでも良いことに限って、こういう時にやたらと気になってしまう。今までと目線が違うような気がして足元を見ると、この前オレの家に来た時とは違うヒールの靴。そういえばと最後にデートをしたのはいつだっただろう。そもそも数えるくらいしかしたことがない気さえする。そんなオレは、彼女が街を歩く姿をよく知らない。
「え、と赤司っちって知り合い?」
「赤司くんとは高校の時の同級生だったの」
「そう、だったんスか」
「っていうか赤司くんと黄瀬くんこそ知り合い?」
「オレたちは中学の時の同級生で、部活のチームメイトだよ」
「えっ、そうだったの?」
が高校の時は京都にいた、という事実も今初めて知った。どうして関係がすべて終わった今、に関わることを次々と知ってしまうのだろう。
それにしても不思議な巡り合わせである。まさか、あの彼がオレの元恋人と一緒にいるとは。あらゆることを読み取る能力に長けている彼は、まさかオレとの関係性さえも今この一瞬で理解したというのだろうか。驚きを見せずに表情を崩さないその佇まいは、オレを動揺させる以外の何者でもない。もしかして、彼が以前「好きな女性がいる」と言っていたのはのことだったのだろうか。けど、今の二人からは「恋人」という雰囲気は感じられない。僅かに空いている二人の空間に胸を撫で下ろす自分に気づいた時、またしても先ほどと同じようにすべての感覚が一瞬止まったような気がしてしまった。やはり「そういうこと」なのだと思い知らされているのに、この気持ちを何と呼べば良いのかも未だに分からない。
「悪いが、そろそろを家まで送らなければいけなくてね」
「そ、そうっスか」
「まだ21時だし、そもそも送ってくれなくても別に良いのに」
「そうはいかないといつも言っているだろう」
「はいはい。じゃあ黄瀬くん、あんま飲み過ぎないようにね」
「…子供じゃないんスから」
モデルの仕事もそうだけど、前にCMやドラマの仕事をやっていて良かったと思った。普通の人より磨かれたその演技力は、きっとあの二人相手でも欺き通せただろう。いや、二人だけじゃない。三人、か。
彼が言う「オレたち」や「いつも」という大したことない普通の言葉にさえ、妙に意識してしまう。その言葉は二人がこうして出掛けることが初めてではない、と物語っているようで何だか虚しくなった。オレはの家に行ったことがないというのに、オレ以上にのことを知っている彼は一体何者なのだろう。彼はにとって「特別」な存在なのだろうか。
この華やかな夜の中でひとり迷子になった。こんなにも明るいのに、目の前はまるで真っ暗だ。輝きひとつ、夜空には星さえも見えないから永遠に彷徨うことになってしまう。不安になって取り出したスマホの光でさえ、明るくない。だったらもう、輝きなんてどうだって良い。この夜空に埋もれても良い。そんな想いを胸に潜ませ、他の女に電話をしたオレは、一体何がしたいのだろうか。
目の前のグラスには自分の情けない顔が映っている。冷えすぎてグラスに滴る水滴は、温度に耐え切れなくなった涙とでも言うつもりか。そんな目の前のグラスさえも煩わしくて、中身を一気に飲み干しすべてを消した。けど、空っぽになったグラスが今度は可哀相に思えて慌てて追加注文する。これが悪循環の始まりである。
「つーか何なんだよ、お前は」
「別にー。ただ青峰っちと飲みたいって思っただけっスよ」
六本木の街を歩くにしては早い19時頃。土曜日の夜という、世間ではデートや合コン、飲み会で盛り上がる時に男二人で酒だなんて、何とも言えない。そういえば、とは今まで一緒に酒を飲んだことが一度もないような気がする。そもそも彼女は普段からお酒を飲む人間なのだろうか。そんなことさえも知らない自分に今頃気づいた。
カウンターで横に腰掛けている青峰っちは、オレとが付き合っている−否、付き合っていたということを知る数少ない人間である。そして、おそらくオレとの距離感も気づいている。それぞれが知り合いだったという時には流石に全員が驚いたものの、3人とも特に干渉し合わない性格なおかげか特に困るようなことは一切なかった。
「オレ、と終わったんスよ」
「あっそ」
「ええ!?ちょ、それだけっスか!?」
「むしろお前らが続いてたことの方が不思議だろ」
本人たちだけではない、周りから見ても不自然な関係だったらしい。その不自然さに、お互い気づいていたのに気づいていないフリをしてごまかし続けて、その結果がこんな有様だとは情けないにも程がある。
こんな終わりを望んでいたわけじゃない。けれど、どんな終わりを望んでいたかと問われても答えることは出来ない。終わり以外の結末なんて存在していないのだから、いつかは終わりが来る付き合いだったはず。なのに、いつの間にかそんなことも忘れていて、続くわけがないこの関係はずっと続くとまで錯覚していた日々さえも、今となっては懐かしい。
「どっちも避け合ってたのに」
―カラン。持っていたグラスの中の氷が揺れた。自分の迷いや戸惑い、それらすべてが腕から指を伝って中の氷が悲鳴を上げた。崩れた氷の音がやけに響いて聞こえたのは、きっと気のせいなんかではないのだろう。
避け合っていた、と言われれば確かにそれは否定しない。はオレに、オレはに必要以上に踏み込まなかった。踏み込めなかったと言う方が正しいだろう。始まりも簡単なら、終わりも簡単。そんな考えは悲しいことに浅はかだった。滑稽に感じた自分自身に、呆れた笑い声さえ漏れる。
「つーか、お前他にも女いんだから別ににこだわる必要ねーだろ」
「は“一応”彼女だったんスよ」
「じゃあ他の女は何なんだよ」
「そう聞かれると何て答えれば良いか分かんないっスね」
今思えば、と初めて会った時に「付き合う」だとか「恋人」というフレーズを出したからこういう関係になったのだろう。だったらいっそのこと他の女と同じ立ち位置だった方が良かったのかもしれない。そしたらきっと、何も思うことなんてなかったのに。
をあくまで「彼女」に選んだのは偶然だったはずだ。たまたま会って、たまたま抱きしめて、たまたまキスして、たまたまオレに興味がない、たまたまそれなりの容姿だった。そんなは、オレの予想以上に「彼女」を務めてくれた。本当に最低限の付き合いで。
「もっと単純なことなんじゃねーの?」
「単純って?」
「だけは他の女と違う、今までの女とは違うから一応でも彼女なんだろ」
「まぁ多分そうなるんスかね」
そう、彼女は他の女とは違うということだけは明確。「彼女」なんだから当たり前だ。どこが違うと問われたところで答えは出なくても「違う」とだけは断言出来る。今思えば、の肌触りもの香りもすぐに思い出せる。があまり表情を変えずに喋る姿も、儚げに笑う顔も、キスをしたあとの余韻だって思い出せる。靄がかかったようにぼやけていた世界は、オレの家の中にがいる時だけ、少し輪郭が浮き出たような気がしていた。それがオレの錯覚でなければ。
「だから、そういうことなんじゃねーの」
―カラン。すべての思考と動作がコンマ数秒の世界で停止したと思うほど、その言葉は衝撃的だった。そういうこと、他の女とは違うということ。つまり、はオレにとって「特別」だったと言いたいのだろう。そんなこと今まで全く意識したことがなかった。当然、気づくわけもない。けど、紛れもなく特別な存在。曖昧な存在で特別な存在、手を伸ばしたくても伸ばせなかった、伸ばさなかった存在だということだろうか。
そうか、未だに逃げているのはオレだけだ。
あれからしばらくして解散したあと、オレは酔いを冷ますために六本木の街を歩くことにした。驚くことに時間はまだ21時。飲んでいた時間はたった2時間くらいなのに、随分と酔いが回ったような気がする。相変わらず人が多いこの街の音たちは、耳を通り過ぎ頭の中を通り抜けていくようだ。華やかな光やネオンは目に痛い。眩しすぎて、目を閉じてしまいそうになるところを、必死で堪える。目を閉じたら人混みに埋もれてしまう、人にぶつかってしまう。そう思って開けていたこの瞳は、見ない方が良かった世界を捉えてしまった。
横断歩道を抜けたところで遭遇したのは、初めて見た眩しい輝き。きっとオレが隣だったら輝かないそのダイヤは、この光で溢れた街に紛れることなく、一際目立つように存在している。隣がもしオレだったら、きっとそのダイヤは輝くことも出来ずに、この明るいようで暗い夜景に紛れて見つけることすら出来ないだろう。星も見えない都会の真っ暗な空は、光のおかげで明るく見えているのかもしれない。
「あれ、黄瀬くん?」
その声はこの騒音の中でも、ノイズキャンセリングつきのイヤホンから出てくる音のようにクリアに聞こえた。そこまで久々ではない。むしろ「恋人」の関係でいた時でも会わない期間が長いことは度々あったのだから、今更そんなことを気にすること自体、可笑しい。けれどもっと可笑しいのは目に映る光景。どうして、どうしての隣にはかつての旧友が存在しているのだろうか。
「…と赤司っち!?」
「黄瀬じゃないか、偶然だね」
一瞬、声を出すことにさえ戸惑った。何故、彼が。何故、彼女と一緒に。何故、彼女の隣にいる。たくさんの数えきれない疑問を頭の中でぐるぐると回すが、そう思っていたのはどうやらオレだけではないらしい。驚いているを見て、オレはあることを思った。”ってこんなに背高かったっけ?”どうでも良いことに限って、こういう時にやたらと気になってしまう。今までと目線が違うような気がして足元を見ると、この前オレの家に来た時とは違うヒールの靴。そういえばと最後にデートをしたのはいつだっただろう。そもそも数えるくらいしかしたことがない気さえする。そんなオレは、彼女が街を歩く姿をよく知らない。
「え、と赤司っちって知り合い?」
「赤司くんとは高校の時の同級生だったの」
「そう、だったんスか」
「っていうか赤司くんと黄瀬くんこそ知り合い?」
「オレたちは中学の時の同級生で、部活のチームメイトだよ」
「えっ、そうだったの?」
が高校の時は京都にいた、という事実も今初めて知った。どうして関係がすべて終わった今、に関わることを次々と知ってしまうのだろう。
それにしても不思議な巡り合わせである。まさか、あの彼がオレの元恋人と一緒にいるとは。あらゆることを読み取る能力に長けている彼は、まさかオレとの関係性さえも今この一瞬で理解したというのだろうか。驚きを見せずに表情を崩さないその佇まいは、オレを動揺させる以外の何者でもない。もしかして、彼が以前「好きな女性がいる」と言っていたのはのことだったのだろうか。けど、今の二人からは「恋人」という雰囲気は感じられない。僅かに空いている二人の空間に胸を撫で下ろす自分に気づいた時、またしても先ほどと同じようにすべての感覚が一瞬止まったような気がしてしまった。やはり「そういうこと」なのだと思い知らされているのに、この気持ちを何と呼べば良いのかも未だに分からない。
「悪いが、そろそろを家まで送らなければいけなくてね」
「そ、そうっスか」
「まだ21時だし、そもそも送ってくれなくても別に良いのに」
「そうはいかないといつも言っているだろう」
「はいはい。じゃあ黄瀬くん、あんま飲み過ぎないようにね」
「…子供じゃないんスから」
モデルの仕事もそうだけど、前にCMやドラマの仕事をやっていて良かったと思った。普通の人より磨かれたその演技力は、きっとあの二人相手でも欺き通せただろう。いや、二人だけじゃない。三人、か。
彼が言う「オレたち」や「いつも」という大したことない普通の言葉にさえ、妙に意識してしまう。その言葉は二人がこうして出掛けることが初めてではない、と物語っているようで何だか虚しくなった。オレはの家に行ったことがないというのに、オレ以上にのことを知っている彼は一体何者なのだろう。彼はにとって「特別」な存在なのだろうか。
この華やかな夜の中でひとり迷子になった。こんなにも明るいのに、目の前はまるで真っ暗だ。輝きひとつ、夜空には星さえも見えないから永遠に彷徨うことになってしまう。不安になって取り出したスマホの光でさえ、明るくない。だったらもう、輝きなんてどうだって良い。この夜空に埋もれても良い。そんな想いを胸に潜ませ、他の女に電話をしたオレは、一体何がしたいのだろうか。