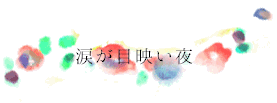自分について冷静に考えるようになってくるくらいの頃から、こんな私は誰からも愛してもらえないんだろうなと漠然と思っていた。だって、自分が他人に興味を持とうとしないのだから。そして、それは自分の中に誰かが踏む込んで来ることに対して抱く恐れの裏返しなのだから。
誰かに甘えていたら、ひとりで生きていけない。だから誰にも甘えたくなかった。もっと強くなりたかった。寂しいだとかそういう感情を抱いてもいけないと思っていた。けど、やっぱりひとりは孤独だから、せめて人肌だけ感じることが出来ればそんな思い誤魔化せると思っていた。黄瀬くんと曖昧な関係を持つことにした一番の理由は気楽だと思ったから。何となく、自分でも彼に対して抱く感情は愛情ではないと思っていた。でも、まさか久々に再会したばかりの赤司くんにそれを悟られるなんて。そして、結局弱い者同士が必死に着飾って、背負いきれない鎧を背負って、無理をしているということに気づかされてしまった。無理をして、強いフリをして、本当は満たされてなんかいない。そしたらもう、そんな自分が嫌になった。そんなんだから中途半端の愛しか送れない、中途半端な愛しか受け取ることが出来ないなんて、一番苦しい。だったら、もっと強くなれば良い。縋りたいなんて思わないくらい強く。
けど、寂しいと思うことが悪いことではないと言われて、私はやっぱり誰かの傍にいたい。誰か傍にいてほしい、と思ってしまったのだ。
△▼△
夢中で逃げ込んで来たのが男の腕の中だなんて、どんなに強いと思っていても結局私はただの女でしかない。黄瀬くんに抱きしめられた時よりも近い位置にある彼の顔に何よりの存在を感じて、ただ抱き締められることしか出来ない。その間、数十秒だったのか数分だったのかはよく分からない。彼が離れたあとに出来た隙間さえも、何だか虚しい。
背中に手を添えられ中に入るよう促されると、彼のリビングと二度目の再会を果たした。相変わらず男の一人暮らしだというのに整理整頓されているこの部屋は、褒められるべきなのだろうけど、完璧過ぎて私には少し敷居が高いようにも感じる。そしてフローリングは、やっぱり冷たい。
「コーヒーで良いかな」
「あ、お構いなく…っていうか」
突然来てごめんなさい、の一言が未だに言えない。ふかふかの高級そうな漆黒のソファーが、私の身体だけでなく言葉まで飲み込んでしまったのだろうか。差し出されたコーヒーを受け取ると、フローリングとは正反対の温もり。コーヒーを飲んでこんなにも落ち着くと思ったのは、いつぶりだろう。
彼が隣に腰掛けると彼の重みでソファーが少し沈む。不意に、ドキっとした。あまりにも自然に作られたこの近距離は、今までとはまるで違うものであり、私の胸を動揺させるのだ。彼は、何も聞いて来ない。きっと彼にとっては私がこの部屋に再びやってきたという事実だけで良いのだろう。それに、きっとすべてを見透かしているはず。沈黙が何となく悪いことをしているようにも感じられて何か喋らなくては、と思いながらも言葉なんて何も出て来てくれない。
「」
そんな静けさを破ってくれたのは彼だった。しかし、今度は私の心臓の音が聞こえてしまうのではないかと思うほど、この心がうるさい。彼に手を触れられて、髪を優しく撫でられれば普通の女性ならきっと甘えたくなるのだろう。でも、ここでもまだ甘えたいと思えなかった、甘えてはいけないと思ってしまった私は本当に可愛くない女である。甘えたいだとかそういう感情の前に立ちはだかる躊躇いと戸惑い。髪から頬へと移動した彼の手が私の頬をすっぽり包み込むと、彼の手はこんなにも大きかったのだと初めて実感したような気さえする。私の髪を耳にかけようとするその仕草でさえ、彼は完璧過ぎて私はピクリと一瞬だけ動いたあと固まって動くことすら出来ない。
「ずいぶんと初な反応をするんだね」
「…もしかして、嫌味?」
嫌味のようにしか感じ取れなかった私は性格が悪いと自分でも思う。私に触れる手はすべて優しいのに、からかわれているようにも感じられて、不愉快というよりは少し疑問を抱いてしまったのだ。それに、まるで黄瀬くんとは散々こういうことをしてきたんだろうと言われているようで、罪悪感に近い感情も生まれてしまった。けど、彼に対しての罪悪感なのかと問われてもすぐには頷けない。自分でも、この感情の正体が理解出来ないのだ。
「まさか。でも、そうだな」
「何?」
「情けないから言いたくはないが、少し妬いただけだよ」
「妬くって…もしかして黄瀬くんに?」
彼が何かを羨ましがったり、嫉んだりするところなんて今まで見たことがない。いや、私のことで誰かが妬いてくれたりだとか、不安に思ってくれたことなんて、今まで一度もない。黄瀬くんも、黄瀬くん以外の人とも、無意識のうちに距離を取って心で深い関係になろうとしなかった私は、今まで誰かに求められたことなんて、一度もなかった。
「どうやらオレは、のことになると嫉妬深くなるようだ」
引き寄せられた顔が以前より、近い。その双眸を前にしたら、もう動けない。
「オレの前で他の男の名前なんて、出すな」
彼の形の良いくちびるが弧を描いたのところを見る暇もなく、強引に近づいたくちびるの距離は重なり合う。重ねられたくちびるは冷たいのかあたたかいのかさえも分からない。それくらい強く強引なくちづけ。彼とキスをしたのは初めてじゃない。高校生の頃、まさに青春と言えるようなあの頃、夕日が射しこむ教室で彼と初めてキスをした事を少し思い出した。けど、あの時とはまるで違う。あの頃は優しく触れただけのくちびるが、今ではこんなにも大人になるなんて。月日の経過を感じさせられた。
もう夕日じゃない。暗い空の中にぼんやりと輝く月が見ているこの部屋で、私は彼にようやく甘える事が出来るのだろう。
△▼△
朝、目が覚めるとふと虚ろな意識でここが自分の部屋ではないということに気づいた。慌てて起きるといつもより柔らかいベッドの上。時間は?と思って時計を見るとカレンダーがついていて、今日が休日ということを知り安堵した。部屋の扉を開けると、そこにはリビングでくつろぐ彼が優雅に経済誌を読みながらコーヒーを飲んでいる。彼の朝を初めて見た。
「おはよう。よく眠れたみたいだね」
「…おかげさまで」
彼は当たり前のように私にコーヒーを用意してくれた。誰かに朝のコーヒーを用意してもらえるなんていつぶりだろうか。いや、初めてかもしれない。昨日差し出されたコーヒーとはまた違う。今朝はおかげで目がよく覚めた。けど、いつまでもここにいるワケにはいかない。自分の家に戻らなければ。特に盗られるようなものなんてないけれど、この物騒な世の中では流石に開けっぱなしの部屋は心配である。
「ありがとう、赤司くん」
「帰るのか?」
「うん、鍵かけないで来ちゃったから」
お礼と言えるほどではないけれど、カップを洗ってキッチンを少しキレイにしてシーツを洗濯して、部屋の掃除をしてから彼の部屋をあとにした。彼はそんな私の様子をテーブルに座って肘をつきながら見ていた。微笑んでいるようにも見えて、何がそんなに楽しいのかと問うと「は良い奥さんになりそうだね」なんてことを言われた。これだけで良い奥さんになれるのなら、ほとんどの女性が良い奥さんになれるんじゃない?と可愛いげのないことを言う私にでさえ、彼は「可愛いな」と言う。「可愛い」なんて見せかけだけの甘ったるい台詞は黄瀬くんのおかげで慣れているはずなのに、むずがゆさを感じたのは何故だろうか。
タクシーに乗っているとようやく見慣れた景色が映ってくる。ようやく着いた自分のマンションは、たった数時間離れていただけで何だか少し入り辛い。けど、そんなことも言ってられないので自分の部屋へと足を進める。エレベーターを降りて角を曲がったところが私の部屋。そこで視界に入った光景は予想とは全く違う、目を疑うものだった。
「え、黄瀬くん!?」
「っ…!」
部屋のドアを背に座り込んでいたのは、世間では輝きを放つ眩しい存在、かと思えば表情を見ると普通の男だった。何故彼がまだここにいるのか。何をしているのか。どうしてー。とっくに帰ったと思っていた彼がいたという事実は私を驚愕させる以外の何物でもない。おまけにずっと外にいたと言うのだろうか。モデルという華やかな仕事をして、世間でも騒がれるような彼が?眠ることもしないで、ずっと?
「え、ちょっ…まさかずっといたの?」
「、鍵かけないで行っちゃったから」
「それで…いてくれたの?」
「最近物騒だし、それにとまだ話が…え?」
彼はこんなにも純粋で素朴な人間だったのか。そんな縋るような目でまたしても私を見るの?あの時、逃げて行った私を追い掛けはしないでくれたのに、結局は待っていたなんて。いい加減、すべてを察して欲しい。どうして私を放っておいてくれないの。どうして、私にこだわるの。どうして、私の中に入って来ようとするの。彼と一緒にいたら私はこのまま何もかも中途半端に生きていってしまう。そんな私自身を変えたいのに−。
「黄瀬」
「赤司、っち…!?」
鍵のかかっていない部屋にもし誰かが潜んでいたら危ないから、という強引な理由で私と一緒にタクシーに乗って来てくれた赤司くんが姿を見せると、黄瀬くんはひどく驚いた顔をしていた。同時に、勘の良い黄瀬くんはすべてを悟ったのだと思う。あのあと、私がどこへ向かったのか。私がどこへ逃げたのか。そして昨晩から今まで、赤司くんと一緒にいたということを。
「そ、っか。そういう、ことっスね」
渇いた彼の自嘲するような笑みと声が脳を掠める。彼のこういう顔を見るのは初めてじゃない。出会ったばかりの頃はよくこんな顔をしていた。そういえば、いつからかそんな表情は見かけなくなっていた気がする。彼と一緒にいる時間が短いから特に気にしたことはなかったけど、もしかしてそうではないと言うのだろうか。
「行かせたオレが…」
ポツリと呟かれた言葉は、私を責めるものではなかった。けど、彼が自身を責めているかのような言葉は理解出来ない。今更何を言っているのだろうかという思いと、どうして今更という、似ているようで正反対の思いが私の思考を狂わせる。彼といるのが楽だったから一緒にいただけ。未練なんてない。彼とは似ている部分があるから、何となくお互いを理解していて、お互いを深く干渉し合わない良い関係だった。でも、今の彼は私とはもう違う。だったら、一緒にいる必要なんてないのに。迷い、躊躇う私を目覚めさせるような言葉が、脳を震わせる。
「それでも…幸せになって、なんて簡単に言えるほど出来た人間じゃねーよ」
なのに、結局そうやって逃げ去る彼の姿は昨晩の私と同じだ。