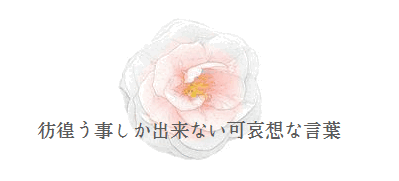
紫原がの全身を包み、その全てを愛そうとしている時、部室に入って来たのは副キャプテンである福井と氷室だった。部活もそろそろ終了の時刻が迫っているが、2人はが部室へ持って行った救急箱を使いたいと思い、を追ってやってきたのだ。一歩前を歩くように福井が、そしてその一歩後ろから入ってきた氷室の2人が目にした光景は、瞬間的には光景と理解出来ず、言葉さえも無音に飲み込まれる。扉が開いた音に気付いた紫原は、一瞬動きを止めた。は顔を扉の反対側に向けていたため、誰が部屋に入ってきたのかまでは気付いていない。紫原は福井と氷室…いや、氷室を一瞥した。
「なっ…お前、部室で何…つーかに何してんだよ!?」
「いや、見れば分かるでしょ」
福井は部室の中へ入ると、氷室を思っての行為だろうか。紫原をから離すように、引きはがすように2人の間へ入った。紫原は素直に離れたが、その表情はいつもと同じで、相変わらず何を考えているのかは想像出来ない。一方、紫原から引きはがされたはというと、先ほど紫原に掴まれていた腕の手首を、胸のあたりでもう片方の手を使って何かを守るようにぎゅ、と抑えていた。制服の首元は若干乱れており、そこには醜い赤がいくつか刻まれている。力が抜けたのか、膝から落ちそうになったところを、氷室が肩を支えて受け止める。
「あ…」
「」
「…え、氷…室先輩?福井先輩、も…?」
思考回路が混乱していたらしいは、どうやらたった今、氷室と福井がこの部室にいることに気付いたらしい。氷室はとりあえずを椅子にゆっくりと座らせ、自身が来ていたジャージをの肩にそっと羽織らせた。もちろん、そんなことでの心は落ち着くことはない。ただ、静かに涙も流しているわけではなく、泣き叫んでいるわけでもない。それでも、今のが少なからず動揺していることくらいは、ここにいる誰の目から見ても分かった。
「お前、自分がしたこと分かってんのかよ?」
「当たり前じゃん」
「…が氷室の彼女ってこと知ってんだろ」
「うん」
「うん、って…おかしいだろ」
「何で?普通にキスして、そのままー…って思っただけじゃん」
何かが破裂する音ではなく、何かが壊れる音がした。氷室が紫原を思いっきり殴った音である。紫原は奇しくも、2日連続でこの恋人同士2人に顔を傷つけられることになる。残念ながら傷ついているのは顔だけで、心が傷ついているとは気づいていない。痛みは感じなくとも、確実に傷がついているということに、この時点では気付いていないのだ。この音が鳴った瞬間、もちろん福井もも驚きを隠せない。ありえない、という行動ではないのだが、やはり実際目にして音にして感じてみると驚いてしまうのだ。紫原の心を壊すように殴ったあと、氷室は紫原の胸倉を掴む。福井が氷室を止めようとしないのは、男としての気持ちが分かるからだろう。
「ふざけるな!」
「いってー…」
発したくても、なかなかその続きの言葉が上手く出てくれない。何を言いたいのか、言ってやりたい事が多すぎて、言葉が喉で詰まってしまっているのだ。ただただ、悔しそうに唇を噛み締めている氷室にはこれ以上どうすることも出来ない。言葉が出てこないことさえも悔しくて、自分自身に腹が立つ。雰囲気を察した福井が、静かに氷室の腕を掴み、制止の合図を送る。これ以上は何も訴えることが出来なくなった氷室は大人しく手を離し、の前に片膝をついた。福井はそんな氷室を見たあと、紫原のほうへと声を掛ける。
「とにかくお前今日はもう帰れ」
「そうするー」
「…ったく」
紫原は先ほど氷室に殴られた衝撃で倒れていた身体をゆっくり起こし、帰り仕度を始める。この間、室内は沈黙に包まれており音も温度もない。ただ、氷室がの前で片膝をついて手を握っている温度だけは確かに存在していた。それでも、の手は少しだけ震えている。今頃になって、恐怖が襲ってきたのだろうか。紫原は部室を出ていく際に、そんな様子を一瞬だけ一瞥したが、すぐに「じゃーねー」と言って帰って行った。紫原が部室から出たのを確認すると、福井は深いため息をつく。相変わらず空気は動揺を放っているが、温度を失ったの震える手を、慈しみながら握るそこには確かに愛情が存在していた。
「」
「あ…ごめ」
「ごめん」
しかし、手から伝わる愛情と違ってには氷室のこの言葉が理解出来なかった。驚いて目を見開き氷室を見ると、そこには自分より切ない表情を孕んだ氷室が映ったのだ。その表情のまま、氷室がの頭を撫でようとすると、反射的にの身体はピクっと硬直してしまった。そんな些細な動きを氷室が見逃すわけがない。氷室はの頭に触れようとしていた手を途中で止め、その場で空気を握り潰した。そして、もう片方の手も離し、の手は外気に触れることになる。温かさを失った手が可哀相に思えた。氷室は立ち上がると福井へ話し掛ける。
「福井先輩」
「ん?」
「すみませんが、今日を家まで送ってもらえませんか」
「そりゃあ構わねーけど…」
「多分、オレは今近くにいない方が良いと思うので」
は2人の会話を静かに聞いていた。何も言葉を吐くことなく、ただ黙って聞いている。福井と一緒に帰る、つまり福井に家まで送ってもらうことは、今までにも何回かあったので氷室も自然に頼むことが出来た。もちろん、福井にも断る理由はないし、今のこの状況を見てもそれが一番正解に近いだろうと思えた。
「それに今2人でいたら…オレもを傷つけてしまうかもしれない」
その氷室の言葉は、独り言のように自分に言い聞かせているのか、宙へと消えていく。その言葉は本当に小さく、この狭い部室の中でも福井にしか聞こえていなかっただろう。近距離にいた福井でさえも、全て聞き取ることは出来ず、後半部分しか聞こえなかったのだが、氷室の真意は何となく理解することが出来た。福井は氷室の肩を叩き、了承の合図を送る。はその間もただ、目線を下に向けていた。何も知らない人間が入ってきたら、間違いなくが泣いているように思えるだろうが、は一滴も涙を落としていないのだ。
「、お前も上がって良いからとりあえず裏門とこで待ってろ」
「…はい、すみません」
の声はまるで生気がなく、ただ与えられた台詞を読んでいる大根役者のようだった。氷室と福井の2人はの表情が読み取れないので、今の声の音から心情を察するしかなかった。はそのまま椅子から立ち上がり扉に手を掛けるが、氷室に後ろから話し掛けられ一時停止する。
「。今日の夜、連絡するから」
「…はい」
静かに、振り向かずに肯定の返事だけ与え、も部室を出ていく。同時に先ほどのとまではいかないが、氷室も自身の力が抜け、ベンチに腰掛けた。福井はそんな氷室を見ながらも、特にその事に触れることなく部室を出て体育館へ戻っていく。その背中には、練習はもう終わるから、体育館に戻るか帰るかしろ、と言っているようだった。しかし、紫原も消えて、までいなくなってしまって、ここで自分が消えたら他の部員に可笑しいと思われるだろうと思い、少ししてから福井のあとを追うように体育館へ戻り、練習締めのストレッチに参加し、他の部員と同じ時間を過ごした。
△▼△
は両手で鞄を持ち、福井を待っていた。着替えに時間をかけた、という言い方は間違いかもしれないが、この裏門に来てからそんなに時間が経たないうちに福井が小走りでやってきた。あえて裏門にしたのは、他の部員に気づかれないための福井なりの気遣いだったのだろう。は「悪い、待ったか?」という福井に対して「ありがとうございます」と言葉を伝えたのは、そういう意味も含めてだった。
「何だかスミマセン」
「良いって。確かにお前ん家、ちょっと暗くて危ないとこにあるしな」
それに…という言葉はもちろん出さない。言葉に出さなくても雰囲気で伝わってしまっているのだが、もあえて何も言わなかった。しばらく他愛のない話をしながら帰り道を歩いているが、もちろんこの2人の共通の話題と言ったらバスケ部のことなので、油断をすればすぐに紫原や氷室の話が出てしまいそうになる。なので福井はレギュラー以外の部員の話などをして、不器用に回避していた。けれども、ずっと話が続くわけではなく、沈黙が訪れるともある。この帰り道2回目の沈黙に出会った時、はポツリと言葉を発した。
「…私、分かったような気がします」
「何が?」
「何で敦くんにあんなことされても涙が出なかったか」
「…え?」
「気づいて、しまったと思います」
「おい、それって…」
「だからもう大丈夫です。ありがとうございます」
ちょうどの家に着いた時だった。彼女は泣くように笑ったのだ。 福井は何も言えなかった。まさか今日、あんなことがあった後での笑顔を見れるなんて思っていなかったからだ。何が分かったのか、何に気づいたのか。聞こうと思っても聞いてはいけないような気がしてそれ以上、何も言わなかった。何より、の顔がそれ以上は聞かないで下さいと言っている。
「戸締まりしっかりしろよ」
福井は何とかその言葉だけを生み出した。それしか言えなかったのだ。部外者として、部外者である彼も何故か心が抉られるような感覚を覚えてしまった。
Back Top Next